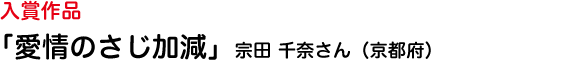
料理をする時、一人暮らしをしている私にはスマートフォンが欠かせない。レシピを見るためではない。生きるレシピのような存在、すなわち母にアドバイスを聞くためである。
しかし最近、母の返事が曖昧で困っている。「味噌はどれだけいれたらいい?」「ちょうどいい味になるまで入れたらいいよ。」「だしはどれだけいれたらいい?」「適量でいいよ。」ちょうどいい味。適量。それが分からないから聞いたのである。しかし母は、「その時の様子を見て味見をしながら作るから数字でいうのは難しい」と困った声で言うばかりだ。
そんな母の手料理は絶品だ。そして私がとりわけ好きなのが、豚汁である。ぶわっと上がる湯気の奥から現れる、色とりどりの野菜。ほろりと崩れるじゃがいもや柔らかい白菜に対して、ごぼうやもやしの歯ごたえが楽しい。さつまいも、油あげ、肉の甘みも優しくまろやかだ。板かすが入った汁を飲み干せば、心も体も温まる。幸せな一杯だ。
しかしその味がどうしても作れない。レシピ通りに作っているが、何か違うのだ。そう悩む私に対して、母は「醤油を少し入れてみるといいよ」と言った。またしても「少し」である。だけど醤油が隠し味ということに興味をもった私は、作ってみることにした。
学校帰りで作り始めてもすぐに出来上がるように、材料は小さ目に切る。その後鍋に豚肉を入れ、さっと炒める。ジュワッと油がでてきたところで野菜を投入し、肉の油と絡ませる。油で野菜がつやっとし、野菜の甘い香りが立ち上ってくる。食欲がそそられる瞬間だ。そこに材料が大方隠れる分量の水をいれ、煮込む。野菜が柔らかくなったところで、いよいよ味付けだ。まずはいつも通り味噌とほんの少しのだしをいれる。美味しい、だけど母の味とは何かが違うという味だ。そこでほんの少し醤油をいれる。味見をすると、味はあまり変わらない。またほんの少し入れ、味見を繰り返す。もう少し、もう少し・・・この味だ!ハッとするほど母の豚汁に似た、優しくて甘くて、ふんわりとした旨味が広がる味。ついに私にも作れたのである。
レシピは一つの答えであるが、誰もに当てはまる正答ではない。今の時期のキャベツは甘いから味を引き立たせよう、今日は野菜が多いから味つけを濃くしよう、あの人は肉が好きだからたくさんいれよう。料理は材料との対話と、思いやりで出来ているのである。思い返せば母の料理もそうだった。お弁当には私の好きな甘い味つけの卵焼きを入れてくれた。頑張った日の食卓には大好物がならんだ。絶品の豚汁も、私が好きなさつまいもと肉をたくさん入れてくれた。母が言うちょうどいい味、適量は愛情のさじ加減だったのだ。
家族がいない食卓は少し寂しい。美味しいねと言い合えないのは心細い。だけど、離れているからこそ気付くことはある。母の愛情を感じながら食べる豚汁は、母の豚汁に負けないくらい、心が温まる一杯だった。
![]()



