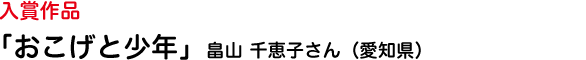
昭和十九年。三月も終り頃の或る日。
私は、県内町村の栄養指導員の一人として、秋田県、能代市近郊の二田(ふただ)という漁村の一画にあった、バラックの仮宿舎に、同じ仲間と合宿していた。
日課は、早朝の麦踏み、食後は食物として野草の見分け方、山野の果実の採取方法、利用法の修得など、居住地に帰って広めるためであった。
その日私は、足を痛めて休んでいた。宿舎には、火の気がない。離れた所にあった大きな宿舎の前方の小屋から、煙の上るのを見て、近づいて行った。三、四人の、中学を出たばかりらしい少年たちが、私を見てひとりが
「おばさん。寒いよ、ここへ来て火に当たればいいよ」
と、言うと
「んんだ、んんだ」
と、他の少年も言った。私は嬉しくなって、火に近づいた。
土で固めたカマドの上に、この地方で使う大きな味噌煮の釜。四人で大勢の朝ごはんを炊いていた。一人が、カマドの火をかき出し、三人が宿舎から、四角の板のおひつを運んできて、カマドの後ろで話し合っていたが、ごはんを移し入れて、何回も運んでいた。
終わったのか、釜の底をしゃもじで、張りついたおこげをはがし始めた時、一人の大柄な少年が、片手に小鉢を大事そうに持ってきて、
「うまいんだよな、これが」
と、小鉢に指を入れて、中のものをパッパとはじくと、にっこりして皆を見た。他の少年たちは、笑いながら頷き合い、おこげを剥がすと、赤子の拳ほどに握り、おひつの上に乗せて、行こうとした。すると、一人の少年がやにわに、その一個を取ると、私の前に手を出して、
「おばさん。一個だけど食べて下さい。なあみんな」
と、後の少年たちに言い、ほほえんだ。私の喉がゴグリと鳴って、少年たちの優しさに、
「ありがとう。いただくわ」
と、涙声になった。少年たちが去った後、少しずつ口に入れ、噛みしめた。黒茶色の一粒一粒は、苦味と交った穀物のかけらと、ひしゃげた米粒の甘味と、少年が指ではじいたしょうゆの香りが、渾然一体となって、口の中に広がった。当時しょうゆは貴重品だった。
「わあ、おいしい」
思わず大声が出た。これほど、おいしいおこげは始めてで、一口を愛おしみながら、独り涙が出た。少年たちは、満蒙開拓青少年団の一員だった。戦後七十年、私は九十七歳になったが、生涯あのおいしさは、忘れない。少年たちは、その後、どうなったのか、未だに心が痛む。
![]()



