「意志は代表されえない」―代議制と人々の受動性の関係をめぐって―
鳴子 博子(なるこ ひろこ)/中央大学経済学部教授
専門分野 社会思想史・政治思想史・ジェンダー論
先月10月31日に行われた総選挙では、投票率の相変わらずの低さ(55.93%)、特に20-30代の低投票率が顕著であった。日本のジェンダーギャップ指数を押し下げている女性議員比率も改善されるどころか減少した (10.1%→9.7%)。さまざまな場から「投票に行こう」とのメッセージが発せられても、なぜ投票率はいっこうに上がらないのだろうか。他方、今月11月9日、作家で天台宗僧侶の瀬戸内寂聴さんが99歳で亡くなった。寂聴さんは毀誉褒貶に晒された激しい人生を歩み、弱者や虐げられた人々の側に寄り添って社会矛盾の解消のために闘った。彼女は若者たちに向かい、人生は「恋と革命だ」と叫ぶ。寂聴さんの動と若者の静。なぜ彼女はそこまで行動するのだろうか。総選挙から寂聴さんへ唐突に話題が転換したと思われるかもしれない。だが、寂聴さんと私の研究対象である18世紀のジュネーヴ生まれの思想家ジャン=ジャック・ルソー(1712-78) との間には意外な共通点がある。生きた時空も性も異なる2人にどのような共通点があるのだろうか。その種明かしは後ほどにして本題に入らせていただこう。
「代議制こそが独裁制を生む」
本小論のテーマは人々の「意志」と代議制の関係についてである。人々の受動性の源を突き止めることと言い換えてもよい。ルソーの政治思想・理論の中核には「意志volonté」、「一般意志 volonté générale」概念があるが、私は「意志」を一種の定点に見立て、ルソーの一般意志を分析視座として、仏独二国でフランス革命からナチス第三帝国までの間に意志がどのように変容していったのか、4点で定点観測を試みた(1)。第1の定点はフランス革命期の最高存在の祭典で表された意志(1794)、第2の定点は仏軍占領下の19世紀初頭のベルリンでフィヒテの「ドイツ国民に告ぐReden an die deutsche Nation」(1807-08)に表された意志、第3はアルザス=ロレーヌをドイツに奪われた第三共和政期のソルボンヌでルナンの「国民とは何かQu'est-ce qu'une nation?」(1882)に表された意志、第4は第三帝国のニュルンベルク・ナチ党大会(1934)で表出された意志である。私は仮説「代議制こそが独裁制を生む」を立てた。独裁は、通常、大衆社会下で代議制が機能不全を起こし、議会の頭越しに指導者が人民投票といった直接民主制的な手法を用いて大衆の同意、支持を取り付けることと結びついて理解される。つまり一般的な理解では、問題なのは代議制なのではなく代議制の機能不全であると見なされるので、私の仮説はその対極にあるものであった。
ナチス「意志の勝利」
歴史順からすれば最後の第4の定点観測から始める。レニ・リーフェンシュタール監督の「意志の勝利Triumph des Willens」(1935)は、ヒトラーが政権を獲得した翌年の1934年にニュルンベルクで開催されたナチ党大会を記録した長編映画である。高い技術力と芸術性を兼ね備えた彼女の映画は、軍の誇る最新鋭の武器にではなく意志を持つはずの人間に焦点を当てる。ナチ党大会で表出されたのは誰の意志なのか、誰の勝利なのか。ナチスの政権掌握の過程は、全権委任法によって政府が議会の有する立法権を簒奪し、政府の立法権は結局、ヒトラーただ一人の独占に行きつく。ヒトラーは国際連盟脱退と総統の創設および自身の総統就任という2つの人民投票により国民の「同意」「承認」を取り付けた。ルソー的視座から結論づければ、ドイツ国民は2つの人民投票によってウルトラ似非立法者ヒトラーに人格譲渡、人格放棄してしまったことになる。ヒトラーの説くドイツ民族の神話、ドイツ生存圏の思想、「力=正義」教の前に、ドイツ国民は良心と理性とをともに働かせて自ら判断する能動性を放棄し、教祖の判断、意志に従うだけの受動的な存在と化した。代議制国家には多元的な団体意志が存在するが、第三帝国の創設では、まず議会の団体意志殺しが強行され、さらにそれに取って代わった政府の団体意志がただ一人の独裁者の意志へと縮減され、ヒトラーの意志が第三帝国を統御する巨大団体意志となった。意志は、ただ一人の主人の意志に縮減され、20世紀の主人-奴隷関係が出現してしまったのである。
ここで、第4の定点と第1の定点の1794年6月の最高存在の祭典とを対照させてみよう。最高存在の祭典はジャコバン独裁期に挙行され、主宰者はロベスピエールであったが、ナチ党大会のごとき独裁者への熱狂は存在しなかった。厳粛さを伴った喜びの感情が人々を自由な者とした人民の神(最高存在)に向けられた。祭典には男女がともに参集し、パリのみならず各都市で同時開催され、広範な人々の下からの発意があった。ルソーは『社会契約論』の実質的最終章で市民宗教を論じた。「人民が、それによって人民になる行為」のそれとは、社会契約の締結を指すものと解されるが、突き詰めれば、それは市民宗教の受容に他ならず、国家創設時の最初の人民集会は市民宗教を受容する集会でなければならない。ルソーは、人民集会に全市民が参集し、政府の提出法案に対して賛否の投票を行い、その表決によって一般意志(法)を発見する人民集会論を展開した(2)。最高存在の祭典は立法集会ではなかったが、人民が人民になる行為に人類が最も近づいた瞬間だったと言えよう。
フィヒテ「ドイツ国民に告ぐ」
次に時間を巻き戻して第2の定点「ドイツ国民に告ぐ」に表された意志に焦点を当てる。「ドイツ国民に告ぐ」は、フィヒテが1807-8年に、ナポレオン率いるフランス国民軍占領下のプロイセンの首都ベルリンで一般の聴衆に向けて行った連続講演である。占領下の講演が国民国家フランスに対する抵抗の言説であることは疑えないが、フィヒテが喚起する国民意識とは何だろうか。彼が重視するのは言語と教育である。ドイツ語によるドイツ国民教育が国民意識を育むことが強調される。フィヒテは種族や民族を生物学的レヴェルで問題にしないが、フランス語を死せる言語、ドイツ語を生ける言語と呼び、生ける言語の優位性を力説する。教会に代わり国家が、宗教に代わり哲学と詩作が重視される。彼はドイツ語圏を一つの国家に団結、連結する政治構想を提示してはいないが、「世界の基幹民族」としての誇りを喚起し、ドイツ語圏の一体性を繰り返す講演は、分立したドイツ諸国がより大きなドイツ国家へと拡大する希求の培養器となった。それでは、彼のいう国民意識とは国民の能動的な意志と言えるのか。答えは否である。国民意識は国家の意志を受け入れ、下支えする被治者の受動的な意識である。フィヒテは国家創設の立法者ではなく、内面的、精神的側面で国家の再編強化を促す上からの改革的な提言者と言えるだろう。
ルナン「国民とは何か」
講演が行われた1882年は帝国主義時代の前夜にあたる。三十年戦争以降、仏領であったアルザス=ロレーヌは普仏戦争後、ドイツに割譲された。鉱産資源に恵まれたこの地の帰属問題は2つの国民国家(第三共和政フランスと第二帝国ドイツ)の国益がぶつかり合う対峙点であった。ルナンは、国民とは「一つの精神的原理」であり、近代の国民は記憶と忘却に基づく歴史的な産物であるとする。彼は、種族や言語は国民の精神的原理の創造にとって不十分なものであり、逆に不可欠なのは意志だとする。彼は係争地の帰属を主張しうるのは係争地の住民自身であるとして、国民の存在は「日々の人民投票」だと訴える。ルナンの「日々の人民投票」という訴えは、精神的なメッセージであり、現実的な提案ではなかったが、その主張には、確かに今日の住民投票や国民投票につながる契機が含まれている。しかし、彼の主張をナイーヴに受け止めるだけでは物事の一面しか見ないことになる。なぜなら仮に住民投票が実際に行われ、フランス参入への多数の賛意が示され、独仏政府が住民の意志を受け入れてこの地をフランスに帰属させたとしても、住民はそれ以後、すでに存在する国民国家フランスの政治的意志決定のシステムに服属することになるからである。結論を示そう。ルナンの「日々の人民投票」は意志のレトリックである。第3の定点で喚起される住民の意志は、真の能動、創造とは結びつかない。そこに、国民国家への「同意」、受動への促しが隠されているからである。
受動から能動へ
日本の戦争を聖戦と信じこんでいた寂聴さんは北京で終戦を迎える。一夜にして変わった世界、外地からの引き揚げが、何事も自分の目で見、自身で判断したことしか信じない新しい人間を生み出した。寂聴さんの反戦、反原発は筋金入りである。そろそろ種明かしをしよう。ルソーは生まれた子を次々に孤児院に置き去りにし、寂聴さんは夫のもとに幼い娘を置いて出奔した。価値観の一変する歴史の大転換を予感し、あるいは遭遇したこと、わが子を捨てたこと、命を削って著した作品で迫害・バッシングを受けたこと、2人の共通点は少なくない。
『社会契約論』刊行から数えて27年後、フランス革命が勃発する。革命期には少なからぬ人々が真の民主主義は直接民主主義であるとの認識を共有していた。女性たちも能動化して家族領域から飛び出し政治行動を繰り広げた。女性たちの能動化、公領域への登場は、女性に、家族の中に留まり夫を介して間接的に政治に貢献する妻となることを求めるルソーの政治構想を超え出ていた。バスチーユ監獄奪取の3ヵ月弱後に起こされた1789年10月の槍や大砲を携えたヴェルサイユ行進は、パリへの強制的な遷都と8月の諸法令や人権宣言を国王に裁可させた。女性たちは第二波フェミニズムの180年も前に、「個人的なことは政治的なことである」を体現していたのである(3)。その後、私たちは前に進めたのか。私たちは今こそ立ち止まって、代議制が人々の受動性を育み、強めてしまった歴史から真剣に学ぶ必要があるだろう。家族を飢餓から救うために立ち上がったパリの女性たちに続いて、受動から能動へ。
(1) 鳴子博子(2016)「ルソーの一般意志と意志の定点観測―フランス革命、フィヒテ、ルナン、第三帝国」『経済学論纂』(中央大学)56-5・6 。
(2) 鳴子(2001)『ルソーにおける正義と歴史―ユートピアなき永久民主主義革命論』中央大学出版部。
(3) 鳴子(2018) 「ルソーの革命とフランス革命―暴力と道徳の関係をめぐって」『nyx』5、堀之内出版、鳴子(2020)「ルソー的視座から見た時間・空間のジェンダー「フランス革命」論―戦争状態を終わらせるものは何か」鳴子編著『ジェンダー・暴力・権力―水平関係から水平・垂直関係へ』晃洋書房。
鳴子 博子(なるこ ひろこ)/中央大学経済学部教授
専門分野 社会思想史・政治思想史・ジェンダー論1957年東京都に生まれ、父の転勤などにより転校を繰り返す。1981年中央大学法学部政治学科卒業。1986年中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了。1994年同博士後期課程単位取得満期退学。前期課程在学中より私塾を経営しつつ研究を続行。博士(政治学)(中央大学、2000年)。中央大学・三重大学・埼玉大学・明治学院大学・作新学院大学などで非常勤講師の後、岐阜聖徳学園大学教育学部准教授を経て、2014年中央大学経済学部准教授、2018年より現職、2021年より同社会科学研究所所長。
研究領域は社会思想史・政治思想史・ジェンダー論。
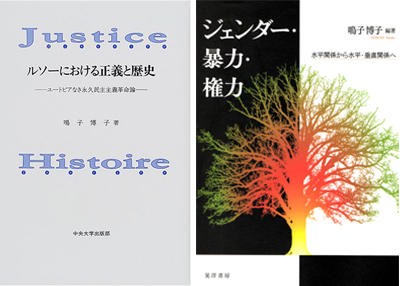
主要著書に、単著『ルソーにおける正義と歴史』(中央大学出版部、2001年)、編著『ジェンダー・暴力・権力』(晃洋書房、2020年)などがある。










