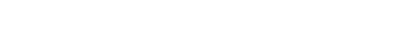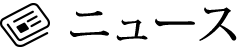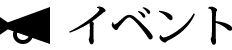1.オウム事件死刑囚の死刑執行を機に
去る7月6日、そして、それから20日をおいた7月26日に、一連のオウム真理教事件で死刑が確定していた教祖・麻原彰晃こと松本智津夫をはじめあわせて幹部13人の死刑が執行された。このことは、6日の、1日の執行数が7人と1989年の法務省の執行公表以降では最大であったことに加えて、3週間のあいだに13人の死刑執行というその規模も戦後最大級ともいわれ、事件の被害者・関係者のみならず社会に大きな衝撃をもって受け止められた。27日の新聞各紙には、「EU加盟国などは、26日、『日本政府に死刑廃止を視野に入れた執行停止を呼びかける』との共同声明を発表。国際人権団体『アムネスティ・インターナショナル』も『死刑の廃止に向けて国内議論を進めるべきだ』と批判した」(読売新聞)、「欧州連合(EU)加盟28カ国とアイスランド、ノルウェー、スイスは6日、今回の死刑執行を受けて『被害者やその家族には心から同情し、テロは厳しく非難するが、いかなる状況でも死刑執行には強く反対する。死刑は非人道的、残酷で犯罪の抑止効果もない』などとする共同声明を発表した。そのうえで『同じ価値観を持つ日本には、引き続き死刑制度の廃止を求めていく』とした」(朝日新聞)など、世界の目が注がれた。
そして、国内でも、これを機に死刑制度への関心が再び高まっているといえよう。「オウム事件に区切りがついた今、制度のあり方を改めて冷静に議論できる時期が訪れたととらえるべきではないか」(井田良教授、7月27日読売新聞)との見解にも現れているように、朝日新聞においてもインターネットアンケートで広く意見が集められており、これらの動きを受けて、識者は、ようやく死刑制度に関する本格的な議論が可能に、と期待を寄せている。
2.死刑存置論と死刑廃止論
あらためて、死刑制度に関する国民の意識をみてみると、約8割は死刑に賛成で、約1割が反対の立場を示しているといわれている。現在わが国では行われていない、仮釈放のない「終身刑」が新たに導入されるならばという条件のもとでは、死刑廃止に反対が52%、賛成が38%となる。その限りでは、死刑の代替刑としての終身刑に対する肯定的評価がうかがえる【出典:「平成26年度 基本的法制度に関する世論調査」(内閣府)(https://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-houseido/2-2.html)】
さて、そのような国民の意識のもとを探るに、死刑賛成・存置論の論拠としては、以下のような事柄が挙げられよう。まず、人を殺したものは自らの命をもって贖うべきことは国民の法的確信であるとの考え方であり、また、死刑の存在によって殺人等の凶悪犯が抑えられているという、その威嚇力による犯罪の抑止効果であり、さらに、そのような危険な犯罪者から社会を保護する最終的かつ有効な手段であるとの考え方である。これに対して、死刑反対・廃止論の側からは、国家が法律で殺人を禁止している以上、国家による殺人を肯定することは背理であり、これを断じて認めることはできない。また、死刑に犯罪抑止効果があるということはこれまで立証されておらず、むしろ死刑になることを願って殺人を犯す犯罪者がいるのは事実である。そして、誤判の可能性は否定できないところ、死刑執行の後に誤判が判明した場合には取り返しがつかない、との主張がなされている。
しかし、これらの各側のいずれの見解も、その主張するところの論拠としては十分なものではないといわれている。社会契約説の論者の間でも、賛成論、反対論が相半ばするのであり、犯罪の抑止効果についても、有意なデータが出ている訳ではない。誤判の問題についても、たしかに廃止論の主張は納得させるものであるが、他方、無期刑の受刑者が長きにわたり収容され死亡した後に誤判が判明した場合と比較して、いずれが残酷であるとはいえないであろう。
3.無期懲役刑と死刑の代替刑としての終身刑
ところで、その無期刑については、現在の法律では、10年を過ぎると仮釈放が認められるとされている。この点だけを取り上げれば、どのような残虐な罪を起こした者であっても何年かの服役の後には社会へ戻ることが可能となるように思われがちであるが、その数は、実は、約1800名の無期刑受刑者のうちほぼ一桁台であるのが実際である(なお、施設収容中に死亡する者は年に20名前後である)。 しかも、実際には、(現在では懲役刑の事実上の上限は30年であることから)服役年数が30年を超えない場合には仮釈放が付されないという運用がなされている。このような事実に照らせば、わが国では事実上、仮釈放のない終身刑の運用がなされえているのと同じであるといってよいであろう。
そこで、では、それならば死刑の代替刑として終身刑を導入してもよい、差し障りはないのでははないか、という意見もあるであろう。だが、無期刑と終身刑との両者には実は、決定的な相違が存している。すなわち、無期刑の受刑者にとって我が身に仮釈放の可能性が存するということは、暗い天井に一点の光が差しているということであり、刑に服する者は、社会へ再び帰ること、それを目指すことを自らへの生きる光、希望として、日々を送ることができる。もちろん、彼らの多くは他の受刑者とは異なる自らの境遇について知悉しているが、それでも「光」を信じ、自らに光明を言い聞かせて日々を過ごすことができる。無期刑の受刑者のそのような胸中についての理解は、そのような彼らに日々対している刑務官においても共有されているであろう。おそらくは仮釈放はないであろうことは思いつつも、受刑者、刑務官ともに、希望を掲げることが生きる、または生かす心の拠り所となり、更生、社会復帰に向けてともに歩んでいるのである。しかし、一方、仮に終身刑を導入するとしたならば、受刑者は社会への戻り道のかすかな希望や社会との接点を完全に絶たれることとなり、その絶望は計り知れない。刑務官は社会に戻らないことを約束された受刑者を前に何をその人生の目標と認めて彼に接すればよいのであろう。そのような任務を担う刑務官の精神的負担は計り知れず、ストレスも強いことは現場からも指摘されているところである。
4.終身刑はよき代替刑たり得るか
あらためて考えるべきであるが、人としての希望を失って獄中にあることは、極悪な罪を犯した者であるからとして受け入れなければならない罰の一端なのであろうか。受刑者といえども闇の中で光を見ることは、人間として許されてしかるべきなのではなかろうか。終身刑の導入によって、このような可能性を奪い去ってよいものであろうか。
さらに、終身刑が導入された場合には、これまでであれば死刑が想定される事案に終身刑が、また、重罰化を望む、処罰感情が高まっている世論を背景に、現在であれば無期刑が言い渡されるべき事案のそのかなりのものに終身刑が言い渡されることになるであろう。例えば、現在の量刑相場でいえば、強盗殺人事件の被害者が3人という事案の場合にはほぼ死刑が、被害者が2人という場合にはその3分の2に死刑が、被害者が1人の場合には原則無期刑が宣告されるといるという現在の構図がくずれ、被害者が2人であっても1人であっても終身刑が宣告され、それに引きずられる形でこれまで有期刑であった事案に無期刑が言い渡されるという方向に量刑の運用がスライドしていくことが懸念されるのである。
死刑制度の存廃論を論じるにあたって、代替刑として仮釈放の付かない終身刑の導入を考えることには、大いなる疑問が存するところである。
- 只木 誠(ただき・まこと)/中央大学法学部教授
専門分野 刑事法学 - 福島県出身。中央大学法学部法律学科卒業。
中央大学大学院法学研究科刑事法専攻博士前期課程(修了)・後期課程(退学)。
法学博士(中央大学)
獨協大学法学部教授を経て、2002年より現職。
専攻分野(研究テーマ):生命倫理と法、故意論・錯誤論
主な著書:『コンパクト 刑法総論』(新世社、2018年)、『罪数論の研究[補訂版]』(成文堂、2009年)、『刑事法学における現代的課題』(中央大学出版部、2009年)など。

-
2019年冬号
学生記者が、中央大学を学生の切り口で紹介します。外務省主催「国際問題プレゼンテーション・コンテスト」最優秀の外務大臣賞に 及川奏さん(法学部2年)/赤羽健さん(法学部1年)

-
Chuo-DNA
本学の歴史・建学の精神が卒業生や学生に受け継がれ、未来の中央大学になる様を映像化Core Energy
世界に羽ばたく中央大学の「行動する知性」を大宙に散る無数の星の輝きの如く表現
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局