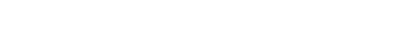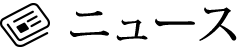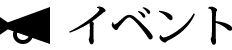はじめに
近年アメリカ文学関係の国際学会や、アメリカ人研究者による講演会などで、アメリカの大学における〈英文科〉の不人気をよく耳にするようになった。英文科に入学する学生、さらには英文学を研究しようという若き学徒が、ガクンと減ってきているというのだ。アメリカの大学のことなので、これはいわばアメリカ〈国文科〉の凋落ということになる。念のため、日本の大学とは事情が違うし、ましてや中央大学文学部にはそのような兆しはないのだが、たんに対岸の火事と見物しているわけにはいかない。日本でも文系学部に対する風当たりが厳しくなっていることは、周知のところだからだ。すこしその原因や影響、そして日本でアメリカ文学を研究するものにとって、このことが持つ意味を考えてみたい。
アメリカ文学史のパラダイム・シフト──フェイク・ニュースの起源ここにあり?
たいへんおおざっぱな話をすれば、アメリカでは60年代の黒人公民権運動、70年代の女権拡張運動、さらには80年代レーガノミクス以来着実に進行しつつある貧富格差の顕在化に対応して、大学での文学研究はここ40年ほどで大きく左傾化している。マイノリティや社会的弱者の権利主張を背景として、文学研究においても社会正義を訴えるものが「正しい」文学としてますます賞賛され、ぎゃくにそれまでのような審美主義一辺倒の文学研究は次第に時代遅れのものとされるようになる。
こうなってくると、いわゆる文学史的な巨匠作家たちもうかうかとはしていられない。昨今のアメリカにおける〈国文学史〉(アメリカ文学史)の教科書には、新大陸発見以前のインディアン──このことばを嫌って別のいいかたをするひとたちがいるが、それも歴史的経緯の隠蔽とするものが多い──たちの口承詩や、コロンブス以前にアメリカに渡来していたというヴァイキングたちの詩が巻頭に掲載されるようになり、「若い」国家だったはずのアメリカが、じつは古くからの文学的遺産を抱えた国であると考えられるようになった。さらには、それまで真剣に文学作品として研究されることのなかった黒人奴隷やインディアンのテクスト、女性大衆作家たち、そのほかの少数民族系作家らの作品が、さまざまな政治的抑圧に抵抗する政治的テクストとして大きく評価されるようになった。ぎゃくにそれまで巨匠とされてきた作家たちは、憂き目を見ることになる。
これは日本でいえば、万葉集や記紀、さまざまの和歌集・物語集など、貴族文化を中心とするテクストからはじまるとされていた文学史の王道に、アイヌの民や琉球人、加えてさまざまの抑圧のもとにある異文化系作者らのテクストが殴りこみをかけてきたようなものだ。それまで絶対的権威とされてきた作品が、じつは抑圧的権力に迎合するもので、むしろそれに立ちむかおうとする作家のほうが偉いとされるようになる。こうなると、文学的価値というものは大きく揺らぐだろう。きのうまでの文学的真実は、一夜にして欺瞞に変わってしまう。ものの見かた、見るひとの立ち位置によって、なにが文学的価値かということが大きく変わることを、アメリカの若い世代は教えこまれてきているのだ。こんにちの〈フェイク・ニュース〉の横行も、このようなリベラルな文学史教育を受けてきた世代にとっては、当然のことだったといえるだろう。
英文科不人気とトランプ大統領の密かなつながり
ある国にとっての〈国文科〉とは、その国のアイデンティティを確かめる場所なのだろう。本来なら、歴史的に武力闘争や政治的交渉のなかで、さまざまに引きなおされてきた〈国境〉を基準にして、確たる文化的統一体が存在すると考えるのは、幻想に過ぎないはずだ。それでも自国の文学の脈々たる連続性を信じようとするのは、ある種のアイデンティティ・ポリティクスだし、それによって国家の統一意識は担保される。(文学史が国家統一を支えるというのは日本では笑い話かも知れないが、アメリカのような多文化的状況のなかではそれなりに真剣なことだ。)
それまで国家的アイデンティティの牙城と思われていた〈国文科〉が、しかし、どんどん左傾化していることを知ったら、普通のひとはどうするだろう? ふたたび日本でいえば、夏目漱石は日本帝国主義の回し者、川端康成は男尊女卑の封建主義者というような研究ばかりが〈国文科〉で横行するようなったとすると、一般のひとはそのような研究をおこなう高等教育機関をどう思うだろう。(あらためて注釈すれば、これはあくまでたとえ話で、中央大学文学部で、そのような研究がはびこっているというようなことはけっしてない。)アメリカでいえば、白人の、ある程度以上の年齢の(つまり、上で述べたようなリベラルな文学史教育を受けていない)、しかもあまり教育程度の高くない労働者は、そのような〈国文科〉の打ちだす修正主義的な〈文学史〉を素直に受けいれるだろうか? さらには自分の娘や息子を〈国文科〉に送ろうと考えるだろうか? どうも反知性的な現在のアメリカ大統領と、アメリカにおける英文科の凋落とは、このようなかたちで結びついている気がしてならないのだ。
それでは日本の外国文学研究はいかにあるべきか
皮肉なことに、アメリカにおいてこのように英文科人気が低下していることは、日本人の学生や若手研究者にとっては大いなるチャンスである。アメリカの中堅どころの大学英文科のいくつかが、すでに学生確保のために留学生の獲得に本腰を入れはじめているからだ。それまでは自国の学生に独占されていた奨学金や入学者枠が、留学生に対しても開放されるようになってきており、ある程度の英語運用能力と文学的感性を兼ねそなえたものであれば、これまで以上に有利な立場で留学することができるようになった。
しかしそのような実利的な影響とは別に、アメリカにおける英文科の凋落から学べることはないか。こういう風に考えることはできないだろうか? アメリカのアイデンティティ確定の場所としての英文科が衰退したことは、ぎゃくにアメリカ文学を〈世界文学〉として学ぶ可能性を、日本人の(というか世界中の)研究者たちに開くことになるのではないか、と。多文化的状況を突きつめるなかで、たんに一国の文学史として機能しなくなったアメリカ文学とは、ぎゃくにいえば、〈世界文学〉として読まれることを意識しはじめているといえないだろうか、と。
19世紀中葉にアメリカで暮らし、ゴールドラッシュの時代にはカリフォルニアで金鉱を探ったジョン万次郎(中濱萬次郎)は、そこで習いおぼえた当時の流行歌「おおスザンナ」(フォスター作曲)を日本に戻ってから高知に伝えたという。フォスターの歌はそもそも人種差別意識に当てこんだ大衆芸能ミンストレル・ショーで歌われるために作曲されたもので、アラバマからルイジアナに旅する黒人の芸人の口調を面白おかしく歌詞にしている。どうもこの歌が当時のカリフォルニアでは、ルイジアナではなく「カリフォルニアへ」と替え歌で歌われていたらしい。ジョン万次郎なら「日本の土佐へ」と替えたところだろう。ともかく、幕末の暗雲に覆われ、当のアメリカに隷属させられようとしていた日本において、万次郎の歌ったこの歌は、すでに〈世界文学〉の地位に達しているといえるのではないか。万次郎は黒人蔑視の意識に充ちたこの歌を、自虐的にみずからに重ねて歌ったのかも知れない。しかし、そうすることで同時に祖国への思慕を恋人への愛に重ね、さらには黒人奴隷たちのしめすしなやかな抵抗の意識を、みずからのものとしていたのではないか。そのように読みこめる可能性がそもそもあったというのも、アメリカ文学の多文化性のなせるわざである。この多文化性が、文化を越境して新しい〈面白さ〉──新しい文化的価値──を生みだす現場になってゆく。いまそのようにアメリカ文学を読みとくことができるようになってきたことこそ、アメリカにおける英文科凋落というパンドラの箱のうちに逆説的に見られる、新たな希望といえるのだ。
- 髙尾 直知(たかお・なおちか)/中央大学文学部教授
専門分野 近代アメリカ文学 -
ニューヨーク州立大学バッファロー校大学院人文科学研究科英文学科博士課程修了(1997/09)
東京大学大学院人文科学研究科英語英文学専攻博士課程単位取得満期退学(1993/09)
東京大学大学院人文科学研究科英語英文学専攻修士課程修了(1988/03)
東京外国語大学外国語学部英米語学科卒業(1985/03)
中央大学文学部教授(2002/04-)
中央大学文学部助教授(2000/04-2002/03)
東京学芸大学教育学部助教授(1997/02-2000/03)
東京学芸大学教育学部専任講師(1993/10-1997/02)

-
2019年冬号
学生記者が、中央大学を学生の切り口で紹介します。外務省主催「国際問題プレゼンテーション・コンテスト」最優秀の外務大臣賞に 及川奏さん(法学部2年)/赤羽健さん(法学部1年)

-
Chuo-DNA
本学の歴史・建学の精神が卒業生や学生に受け継がれ、未来の中央大学になる様を映像化Core Energy
世界に羽ばたく中央大学の「行動する知性」を大宙に散る無数の星の輝きの如く表現
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局