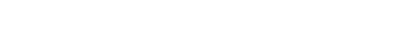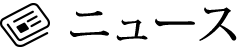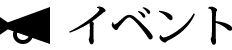2017年6月23日ついに、莫毅の個展が、六本木のZen Foto Galleryでオープニングを迎えた。この展覧会は、莫毅の作品を歴史に留めるべく、20年を越えて継承されてきた、ひとつひとつの思いの多重露光なのである。
中国・平遥から、フランス・アルルへ
1985年9月、留学先の北京で、人波が広い歩道を埋めて押し寄せ、避けようもなく肩をぶつけながら歩いていくと、無数のざわめく感情が一つの生命体となり、押し包まれる。
27年後、恵比寿のギャラリーMEMで、莫毅の個展『囚(ママ)獣―三个十年』(囚われた獣ー三つの十年)を見た瞬間、突然その感触がよみがえってきた。
「社会の喧騒や不安感、ダイナミズム、それに激情や抵抗、すべてがそのなかにあるではないか。映像には、力に満ちた「情绪」の痕跡がある。この映像こそ真実なのだ。一瞬にして、80年代のあの都市が私に与えたさまざまな味わいや感覚を思い出した。20年後、再び私は自分の作品によって感動させられたのである」(莫毅2005年)
「情绪」とは中国語で、不安の内圧に揺らぐ感情である。中国は市場経済の滝つぼへと落下を始め、天安門事件が四年後に迫っていた。なにかが起きている感覚は共有しながら、地殻変動の揺らぎに翻弄されるがままの違和感である。

右の写真の中央、揺らいでいるランドマークは、天津の西開カテドラルである。莫毅の作品集『我虚幻的城市・中国1987』では全40作品中11作品にフレームインする執着対象である。ロマネスク・リバイバル様式の威容は、当時の宗教文化の象徴であり、植民地の歴史の象徴であり、そして天津の近代文化の象徴ともいえよう。だからこそ1966年、カテドラル(=司教座)の屋根を占拠して紅旗を振る紅衛兵たちを撮影した王端陽は、旧世界を征服した歓喜を表現するため、建物も人物群も克明に描出しなければならなかったのである。
しかし、莫毅の作品においては、建物も人波も輪郭を失い、痕跡となって浮遊している。複数の時間、位置からの多重露光は、撮影者自身の視座の揺らぎをも内包する。無秩序に全てが揺らぐことで、集団生命体のエネルギーが湧出した。1987年、一センテンスの中に、複数の時間を多重露光することで、集団生命体の無時間的エネルギーを湧出させたのは莫言(ノーベル文学賞2012年)の『赤い高粱』であった。同質の匂いを発している。
莫毅は時代の変化とともに新たな表現を探しあて、その活動は三期に分期できよう。しかし、そこには変わることなく湧出しているものがある。部材が人波の痕跡である影であれ、人々の生活の痕跡である布団や窓の意匠であれ、それらがコラージュされることで、ゆらぎ、増殖する過程自体のエネルギーである。
2005年、莫毅による莫毅の再発見は、引用部のように発生した。再発見はようやく世界へ広がっていく。2008年には平遥国際撮影展で中国優秀写真家大賞をおくられ、2015年には北京民生現代美術館開館展で「民間の力」の金賞をおくられ、同年、半世紀近い歴史を持ち写真界のカンヌともいわれるフランスのアルル国際写真フェスティバルで、Manuel Rivera Ortiz国際撮影基金によるドキュメンタリー・フォト賞がおくられた。
北井一夫から、ZEIT-FOTO SALON、Zen Foto Galleryへ、そして
日本では、90年代から莫毅は再発見され、いまも再発見されつづけている。
1993年、写真家北井一夫が再発見する。1993年とは、莫毅が第一活動期を天安門事件(1989年)によって切断され、チベットを漂泊するも見切りをつけ、しかし仕事もなく、95年に噴出する第二活動期の表現には未だたどり着けない苦難の時期である。その時、北井は第一活動期の作品を発見し、「誰も知らなかった中国の写真家たち」と題して『アサヒカメラ1994年5月増刊号』の特集を用意する。そこで莫毅は11頁を占める。新人としては破格の扱いである。更に北井は96年NHK日曜スペシャル『中国の素顔を撮る』でも莫毅に同伴し、ナレーションで「今の中国では理解されず」、「批判も評価もされない無視された写真家」であること、そして「紀実撮影(中国的ドキュメンタリー・フォト)の枠を超える高い芸術性」を静かに語る。莫毅の価値を伝えようとする強靭な思いは、2016年世界で初めて莫毅の写真集がオフセット出版された際に寄せた跋文まで、変わることはない。
北井が撮る北京の古い家屋の窓辺には、夢のような光と時間が揺蕩っている。満州生まれの幼児体験と、北京は「街路樹と四合院と胡同がどこまでもつづき、歩いているとその落ち着きがまるで夢のなかのようなところ」という母親の言葉を携えている北井の内には、複数の風土が多重露光されているようだ。
日本初の写真のコマーシャル・ギャラリーZEIT-FOTO SALONの創始者であり、『写真をアートにした男』(粟生田弓)である石原悦郎により莫毅は再発見される。1996年には第一回個展「城市空間―紀実写(マ)真(マ)―莫毅」を開催し、1999年には第二回個展「Recent Works 莫毅」までを開催する。1978年以来402回にわたる展覧会の歴史で、最初の中国人写真家の個展として莫毅を選び、中国人写真家として初めて二回目の個展開催を、石原は決断した。破格の扱いである。石原は写真の芸術的価値を日本に認知させたのみならず、莫毅をはじめとする中国のアートの価値も伝えようとした。
石原の思いを継承したのは1981年に来日したマーク・ピアソンで、内にZEIT-FOTO SALONの残響をとどめるZen Foto Galleryの創始者である。2009年のオープン以来、2011年「赤色の風景」、2015年「80年代Part1:父親、風景」、2016年「80年代Part2 莫毅1987-1989」、2017年「研究―紅1982-2017」と個展を開催した。日本で唯一、中国人写真家をも体系的に紹介するギャラリーではあっても、147回に及ぶ展覧会の中で4度にもわたって個展を開催したのは莫毅だけである。しかも、莫毅が莫毅として出発する以前の作品群も収載し、第一期の作品を包括的に扱い、詳細な年譜も完備した写真集『莫毅1983-1989』を出版した。基礎研究の出発点を準備した世界初の試みは歴史的決断といえよう。
ギャラリー開設にあたって中国を主要テーマの一つに決めた理由を、彼は莫毅の写真集跋文で吐露した。「It was fascinating to see China, a country even then still in the throes of wrenching change」。凄惨な変化の痛みに対するレセプターは、多様な領域や文化を横断してきた重層的感性によるものか。
4度の個展を、質的な破格さに昇華させたのは、羅苓寧(Amanda Ling-Ning Lo)である。台湾で生まれ、日本に留学し、当該ギャラリーで写真集の編集やアートディレクションに携わって来た羅にとって、出生以前の、80年代初頭の中国は、時代も社会状況も未知のものである。それを膨大な資料を基に、莫毅と対峙して結実したのが『莫毅1983-1989』である。
それまでの莫毅の写真集は、一辺が45cmあまりで、サイズ自体が作品のスタイルであった。羅は21.5×15.5cmのサイズとし、両手で持てるばかりか視線を動かさずに作品全体を凝視できる版型とした。複数のシリーズを一冊の中に収め、シリーズによっては紙質を変え、周囲を断ち切り、黒のインクを深いものとし、個々のシリーズの価値を突出させた。何よりそれ以前の莫毅の写真集は手工芸品だった。線装本のように紐とじで手作りされてきたため、制作部数がいずれも僅か100部程度であった。それを初めて印刷物とすることで、広く価値を伝えることを可能とした。俯瞰的視座による再発見といえよう。受容史は第二世代に入ったことを意味する。
しかも今回の展覧会は、2011年に中国で開催された「有紅色的風景」とも、同年Zen Foto Galleryで開催された「赤色の風景」とも質的に異なる。過去のシリーズの枠を越え、「紅」を補助線とし、自作品の中から再発見したものと新たに撮影したものとをコラージュすることで、新たな価値を提出する創造的再発見である。莫毅とZen Foto Gallery との協働的コラージュは、展覧会に合わせて出版された写真集『紅 1997-2007』に結実した。
「中国現代写真家の両極の一方」という顧錚の言葉は、莫毅のポジショニングを語る際の常套句である。莫毅の先端性を発見、周知させた顧は日本に留学経験を持ち、中国の写真界を牽引するのみならず、世界に中国写真家の価値を発信し続けている。東方輝は書店「二手舎」という武器を活用し、知られざる写真家の価値を発信し続けている。
古典化へ
時代や国境、ジャンルを越えた人々によって莫毅の価値は再発見され続け、日本で伝えられてきた。その人々はいずれも重層的な文化のコラージュをレセプターとして内に有していた。受容史が受容対象の質を語る典型であろう。これら奇跡のような連鎖の果てに今回の展覧会がある。「ひとつひとつの思いの多重露光」と書いた。しかし、ビジネス的には多大なリスクをとる以上、その決断は、思いというよりは覚悟という言葉がふさわしい。
風土の粋が溶けこんで湧出する泉質の稀有な価値を、それぞれの時代で再発見し、守り伝えるべく湯守となる覚悟をする、その連鎖が名湯の歴史を創っていく。ならば、「紀実撮影」というジャンルや莫毅の作品も、各時代の要請に応じうるその多義性において再発見され続けることで、古典化していく。そのとば口を今、目撃しているのかもしれない。
翻って日本における中国研究の観点から見ると、「紀実撮影」の研究水準は、映像学に一片の知識もない私がこの文を書いている事実が、全てを物語っている。示唆を与えてくれるのは畏友である中高の国語教員だけ、という現状である。
「秩序は崩壊し、混沌がとって代わろうとしていた」。莫毅がもみ合っていた時代状況をピアソンは跋文でそう表現した。その歴史的周期は当時の中国にのみ訪れるものではない。今、莫毅は再び発見されるべきなのかもしれない。
- 山本 明(やまもと・あきら)/中央大学商学部 教授
専門分野 中国文学・文体論 -
北海道出身。1962年生まれ。1987年早稲田大学第一文学部卒業。
1989年早稲田大学文学研究科修士課程修了。
1993年早稲田大学文学研究科博士課程単位取得退学。
中央大学専任講師・助教授を経て2004年より現職。

-
2019年冬号
学生記者が、中央大学を学生の切り口で紹介します。外務省主催「国際問題プレゼンテーション・コンテスト」最優秀の外務大臣賞に 及川奏さん(法学部2年)/赤羽健さん(法学部1年)

-
Chuo-DNA
本学の歴史・建学の精神が卒業生や学生に受け継がれ、未来の中央大学になる様を映像化Core Energy
世界に羽ばたく中央大学の「行動する知性」を大宙に散る無数の星の輝きの如く表現
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局