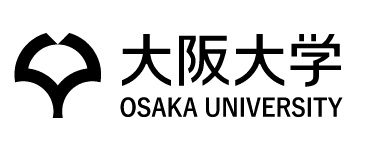【広告】企画・制作/読売新聞社ビジネス局
大阪大学 感染症克服へ総合知で挑む
読売新聞全国版朝刊
新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)で得た教訓から、今後を考察する「パンデミックの"今"と"これから" ―私たちは次の感染症にどう備えるか―」(大阪大学・感染症総合教育研究拠点〈CiDER・サイダー〉主催、読売新聞社後援)が2月3日、よみうり大手町ホール(東京都千代田区)で開催された。会場とオンラインで参加した約1200名が、専門家の講演や議論に耳を傾けた。
大阪大学シンポジウム・感染症総合教育研究拠点(CiDER サイダー)シンポジウム

主催者あいさつ
大阪発世界へ 21世紀の適塾
西尾 章治郎(大阪大学 総長)
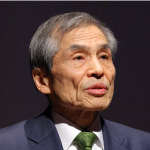
1838年に緒方洪庵が創設した適塾を精神的源流とする大阪大学は、特に免疫学や感染症分野で世界トップレベルの研究を推進してきた。新型コロナウイルス感染症の拡大を機に設立したCiDERは、感染症対策の総合知を形成する国際的拠点として、基礎研究を中心に活動を行う。本学のモットーである“地域に生き世界に伸びる”を体現し、すべての人々が心身の健康を保ちながら社会参画ができ、多様な幸せを実現する社会の創造を目指す。
来賓あいさつ
荒木 裕人 氏(厚生労働省健康・生活衛生局 感染症対策部 感染症対策課長)
高島 義裕 氏(Osaka University Global Alumni Fellow)
拠点紹介
感染症克服目指し 叡智を結集
松浦 善治(大阪大学感染症総合教育研究拠点 拠点長)

CiDERは大阪大学の文理の枠を超えた叡智(えいち)を結集し、感染症の克服を目指して2021年に設立された。病原菌や医療の基礎研究、医療人材育成、情報発信・政策提言を中心に活動している。「宇宙船地球号」をコンセプトとする安藤忠雄氏監修の新棟(写真下)も25年2月に竣工(しゅんこう)予定だ。今後も活動を広げていく。

設計監修:安藤忠雄建築研究所
基本計画:大阪大学、明豊ファシリティワークス株式会社
設計・施工:大成建設、日建設計特定建設工事共同企業体(デザインビルド)
講演
迅速な情報共有 重要
データシェアリングによる医療課題の解決 新型コロナからの教訓
末松 誠 氏(実験動物中央研究所 所長、慶應義塾大学 名誉教授、日本医療研究開発機構 初代理事長)

コロナ以前、医学領域での国際連携体制は脆弱(ぜいじゃく)だった。一方で、感染症の脅威は当時から分かっており、その対策として各国が連携しデータを共有することで立ち向かう「データシェアリング(共有)」の重要性が言われていた。
具体的な動きが出てきたのは、2016年、蚊が媒介するジカ熱が流行した時だった。各国の研究費配分機関のトップが集まる会議体が、感染症のように多くの命が危険にさらされる領域においては、研究者の論文やデータを科学雑誌への投稿前に公開することを推奨し、これによって国際的な情報共有が速やかに行われるようになった。
データ共有の重要性は国際連携の場面だけではない。ワクチンや治療薬開発、限りある医療資源をどこに充てるかといった判断においてもデータの共有は非常に重要だ。
例えば、入院患者のデータを用いて重症化した患者のウイルス変異体の特徴をゲノム解析することで、新しい薬の成分が作用するか否かを判断できるようになる。臨床研究と基礎研究をそれぞれの専門家が手分けしつつ一体で行うことが非常に重要だ。またこれまでに国内の様々な医療機関で得られたデータを共有・統合し、連携して同一の基準をもって「振り返り分析」を行うことも必要だ。
個人情報保護の観点も一方では重要だが、データを国全体で共有することで多くの人の命を救えることを踏まえ、今後のデータ共有のあり方、重要性を考えるべきである。
「予兆」期 緊張のピーク
パンデミックと社会心理学
三浦 麻子(大阪大学大学院人間科学研究科 教授)

社会心理学とは、人の心理や行動において、個人を取り巻く状況や環境の影響を重視し、そのメカニズムを探る研究領域だ。この意味において、今回のパンデミックは社会心理学的に非常に重要な意味を持つ。今回、「日本人のコロナ・パンデミックの受け止め方の変化」を調べたパネル調査結果を紹介する。
パネル調査とは、一定の期間をおいて同じ対象者に同じ質問への回答を求めることで、その変化を観察するものを指す。今回の調査では、「コロナ感染症への関心」「どの程度恐ろしい、未知のものだと思うか(リスク認知)」「自分が感染する可能性があると思うか(感染可能性推測)」「予防する行動をどの程度行っているか(感染予防行動実施数)」について、2020年1月末から24年1月末までに29回、のべ23,201件のデータを集積した。
4年間の調査の結果、20年3~4月、感染禍の気配が漂い始めた「予兆」の時期(第1回緊急事態宣言時)が人心の緊張のピークであったことが分かった。その後の感染拡大後も大きな推移はなく、緊張状態が維持されていたことが分かった。また緊急事態宣言を地域に分けて段階的に発出・解除した点について検証したところ、リスク認知や予防行動に、発出の有無による違いはほとんどなかったことも分かった。
私たち自身が当事者として経験した大きな状況の変化をリアルタイムで記録することが、次のパンデミックに備えることに資すると考える。
パネルディスカッション
テーマ①「私たちは次のパンデミックにどう備えるか?」
テーマ②「医療崩壊はもう起きない!?」
領域またぐ共通認識 必要
ファシリテーター
大竹 文雄(大阪大学感染症総合教育研究拠点 副拠点長)

政府のコロナ分科会に経済学者として出席し、医療・公衆衛生の専門家である押谷先生とは激論を交わした。例えばPCR検査一つとってみても、医療の立場からは「陽性者」を発見して治療を行うためのものだが、経済学者からすると「陰性」を示すことで経済社会を活性化する意味がある。互いの認識のギャップを埋め、共通理解とすることが今後重要だと感じた。また分科会で意見を統一することよりも、それぞれの専門家が様々な意見とエビデンスを示し、選択してもらうことが重要。今以上に多様な分野の専門家が加わることも必要だ。
ワクチン開発の遅れについての議論では、末松先生から基礎研究と開発を一体で行うユニットが少ないことが世界にも共通の原因であり、これを自らのキャンパスで同時にできるCiDERの役割は大きいとの指摘と期待もあった。期待に応えられる存在になるべく邁進(まいしん)したい。
噂が敵意になった史実も
パネリスト
澤田 瞳子 氏 (小説家)

日本史上においては、奈良時代の天然痘(あるいは麻疹〈はしか〉)、江戸時代のコレラ、大正時代のスペイン風邪が主な感染症流行の史実として残されている。奈良時代や平安時代のまだ外国との行き来が限定的だった頃から、江戸時代に鎖国政策が撤廃されて以降、そして今回に至るまで、時代の変化、特に外国との往来によって日本がどのようにパンデミックにさらされてきたかが分かる。
一方、時代が変わっても変わらない人の心もある。安政5年にコレラが流行した際には、当時日本に住んでいたポンぺというオランダ人医師が「開国がコレラの原因だとの噂(うわさ)が立ち、自分たちにも敵意の目が向けられている」と手記に書いている。感染症はそれ自身が歩いてくるわけではなく、誰かにのってやってくる。その時、その人に対して敵意が向けられがちになることは、今回にも起こったこととして記憶に留めたい。
感染症危機管理 検証が必須
パネリスト
押谷 仁 氏(東北大学大学院医学系研究科 教授)

医療・公衆衛生の立場からは、最初の緊急事態宣言を最大限の人流制限を伴う形で実施したことによって被害が最小限で済んだと考えている。2020年5月末までの死者数はアメリカで12万人、イギリスで5.5万人、日本は891人だった。一方、2回目以降については本当に必要だったか、より柔軟な運用ができなかったのか、検証が必要だ。
検査体制や感染症危機管理体制が脆弱だった点は反省もある。当初は医療体制も不十分だったが、治療法が徐々に確立され致死率が下がったことは評価できる。インフルエンザによるパンデミックしか想定しておらず、その想定外の事態に対応できなかったことは今後の課題だ。
政府のコロナ分科会のあり方にも課題があった。分野の異なる専門家の意見を集約する必要はなかった。それぞれの意見を聞いて、政治家が最終決断する本来の姿から外れていたのではと考える。
緊急事態宣言 体制整備を
パネリスト
武見 綾子 氏(東京大学先端科学技術研究センター 准教授)

国民への情報発信については課題が多い。情報は多すぎても少なすぎてもいけない。たどっていけば細かな情報も開示されていた一方、人々が心配に思う点については集約が十分でなかったという指摘もある。また情報の窓口や指揮命令系統を明確にすることや、市民との対話の場が不足していたことも課題に挙げられる。
緊急事態宣言などの行動制限については、各国で対応が分かれた。初期から経済学者の声が大きかったスイスや、徹底した行動制限を行った中国やインドなどだ。マクロ経済だけでなく政策効果の測定も重要で、各国の知見を共同して今後に向けた生産的な議論を深めたい。日本では根拠法によらず自ら行動変容を行ったが、このことが対応の遅れを招いたとの見方もある。今後事前の法整備を行うとともに、CiDERが提唱するように総合知を用いたアプローチの推進が重要と考える。
通常医療に戻す時期 課題
パネリスト
内田 勝彦 氏(全国保健所長会 会長)

第1波から第5波のころを中心に、コロナ病床が不足し自宅療養が増えたことが問題になった。様々な要因があったが、なかでもコロナに特化した医療体制をいつまで続けるのか、という点が最も課題だと感じる。通常の場合と異なり、コロナでは入院先が限定されることで、病床があふれるのはある意味で仕方のないことだった。通常の医療体制に戻すタイミングの見極めが今後の課題と考える。
また情報発信についても課題があった。情報発信は多くの場合、保健所というよりも、設置自治体、特に今回は首長が前面に立って行っていたが、個人情報との兼ね合いに注意が必要だった。特に地方では情報公開する内容によっては個人の特定や誹謗(ひぼう)中傷につながる恐れがあったからだ。情報発信はもちろん必要だが、詳し過ぎると的が絞られてしまい、そのバランスに各自治体の悩みがあったと考える。
研究・教育体制 平時から
パネリスト
忽那 賢志(大阪大学大学院医学系研究科 教授)

ワクチン接種は先進国と比べて数ヶ月遅れて始まった日本だが、感染力が強いオミクロン株が広がるまでに他の先進国を超える高い接種率を達成できた。他国と比べても重症化する人が比較的少なかった要因と考える。今回は海外の製薬会社が作ったワクチンを輸入したが、今後に向けて、平時からワクチンや治療薬開発の国内研究体制を整えることが重要だ。
また感染症やパンデミックに対応できる知識を、多くの医療従事者が身に付けることも重要だ。国の医療計画で次のパンデミックに備えた病床数の計画は立てられているが、医療従事者が対応できるかはまだ課題。20年前と比べて内科医が減っている現状もある。
感染症専門医だけが診るのではなく、感染症に対応するのが医療従事者として必要なスキルと認識すること、またそのための人材育成や教育が急務だ。
閉会あいさつ
世界の命救う 研究を推進
金田 安史(大阪大学統括理事)

大阪大学は、国のワクチン開発拠点にも認定され、CiDERで行うウイルスや生体防御に関する基礎研究を基に、実際のワクチンを作ることも可能になっている。CiDERでは情報発信、人材育成も可能だ。ワクチン開発拠点との有機的な連携を通じて日本や世界を救っていきたい。
主催:大阪大学、大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)
共催:JSPS学術知共創プログラム「コロナ危機から視る政策形成過程における専門家のあり方」、大阪大学先端モダリティ・DDS研究センター(CAMaD)、JSTムーンショット型研究開発事業「ウイルス-人体相互作用ネットワークの理解と制御」
協賛:塩野義製薬株式会社、中外製薬株式会社
後援:読売新聞社