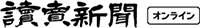広告 企画・制作 読売新聞社広告局
読売ICTフォーラム2022
~生命(いのち)の本質からICTの未来を考える~
進化するICTにより実現する未来の日本社会やライフスタイルについて識者とともに考える「読売ICTフォーラム2022」を3月29日に開催した。2001年にはじまり、今回で20回目をむかえた「読売ICTフォーラム」。
今回は「生命(いのち)の本質からICTの未来を考える」をテーマとし、継続するコロナ禍で見えてきたICTの恩恵や課題、人間の本質やあるべき姿について考え、テクノロジーと豊かに共存し、サステナブルな社会をいかに構築していくかについて議論した。
基調講演〈1〉
生命の本質からICTの未来を考える
澤田 純 氏 日本電信電話株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
経営に求められるピュシスの重要性

澤田 純(さわだ・じゅん)
日本電信電話株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
1978年、日本電信電話公社(現NTT)入社。NTTコミュニケーションズ経営企画部長、同社副社長、NTT副社長などを経て、2018年6月から現職。
ロシアのウクライナ侵略から始まった悲劇が1日でも早く終わるようにと心を痛めておりまして、その願いをこめてプレゼンテーションを始めさせていただきます。
経営をやっていくにあたって大切なこととして「経営の見える化」がいわれます。これは論理の世界で、古代ギリシャの言葉でいえばロゴスです。ただ、理屈だけでは組織や人は動いてくれません。情熱や共感が必要です。これはパトスです。より大きな組織をみるにあたっては、品格や倫理、エトスが求められます。さらに、ここにきて自然、ピュシスが必要とされているのではないかと感じており、いろいろな方々と議論を深めています。
ICT技術は加速度的に進化しています。NTTでは米国西海岸にNTTリサーチという機関を設け、それぞれ「量子」「暗号」「医療」をテーマとする3つの研究所を運営しています。その医療の研究所では、サイバー空間上でリアルと同じようなものを再現するバイオデジタルツインの研究に取り組み、心臓の3Dモデリングを実現しました。これにより、将来それぞれの患者に合った医療を的確にシミュレートできるようになることを目指します。また、ある人の筋肉の動きなどをセンシングして、それを伝送することでロボットや機械類、あるいは別の人の体を動かす人間拡張の技術も実現しつつあります。
21世紀になって、人間を機能主義的にとらえる考え方が注目されています。未来学者のレイ・カーツワイルさんは、やがてコンピューターの能力が人間の知性を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)を迎え、その恩恵を受けた人類がポストヒューマンに変わっていくのではないかと予測しています。歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリさんは、テクノロジーの進化によって、人類が神に愛されし人、「ホモ・デウス」に進化すると唱えます。しかし、こうした機能主義的人間観は、突き詰めると、不老不死のために人間の器官をパーツごと取り換えるといった考え方にも通じるようで、個人的には賛成しかねます。
福岡伸一先生が、2007年の著書「生物と無生物のあいだ」で解説された「動的平衡」とは、生命は最初に分解があって合成が起きるというサイクルを動的に、たえまなく繰り返すことでエントロピーの増大を止め、安定化をはかっているという非常に卓越したアイデアです。ただ、合成より先に分解があるという概念は、死が生きることに先行するという、論理的にわかりにくいところもあります。しかし、おそらくそれが生きることの本質です。DNAの4つの酵素を並べても生物にならず、その裏に何らかのダイナミックな動きが働いている。それを私たち自身は解析できないのだと思います。
俯瞰(ふかん)的な神の目で世界を解析していくというのが自然主義の考え方で、デジタル化とは、一種こういう構造だと思います。しかし、はたしてそれですべてを表すことができるのでしょうか。例えばフッサールの現象学は、主観を重視し、主観における確信によって客観的な世界が存在していると考えます。いわゆる客観的なものだけではないものが世の中にある。主観は千差万別です。自然主義で生命を理解しようとしても、おそらく解明できないと考えています。
より自然に近い多様な世界をICTで実現
生物学者のユクスキュルが唱えた「環世界」とは、生物はそれぞれの種特有の世界を生きているという概念です。例えばイルカが見ている世界、感じている世界は人間とはまったく違います。イルカの可聴領域は人間の6、7倍となる100ヘルツ~150キロヘルツ。海中で視覚が及ぶのは30メートルほどですが、音波で2.5キロメートル離れている仲間ともコミュニケーションすることができます。イルカが主観的に人間の世界を見たら、どうとらえるでしょう。イルカに限らず、生物は自分の世界を持っていて、無為な殺害をすることもなく必要に応じたことをしています。つまり利他的です。生物というのは利他的なのです。
環境に応じて自然淘汰が進むというダーウィンの理論がありますが、もし現実に自然淘汰が進めば、生物は一種類になってしまいます。実際には多様な生物が棲みわけをし、多様な環世界が存在しています。こうした多様性を認めるだけではなく、ある一定の共通理念のもと、それらが包摂される社会が必要になるのではないかと考えています。最近アンコンシャス・バイアスという言葉を聞きますが、ある考え方から外れたものをバイアスととらえると多様性は喪失してしまいます。それも個別の文化と認め、多様な世界が望ましいという共通理念が求められると思います。
こうした概念をもとに考えられる、これからのICTの方向性を3つご用意しました。1つはより自然に近い状態の実現を目指すために、人間以外の環世界で行われているものの見方や音の聞き方を、人間の環世界で活用しようというものです。2つ目は、最近よくエコーチェンバーという言葉が聞かれますが、SNSなどで個人が自分の心地よい世界に浸って、分断が進んでしまう構造があります。それをつないで、どのように自然に近い状態を作りだしていくかというものです。例えば、五感を伝えるコミュニケーションのようなものが考えられます。3つ目はSelf-as-We。これは京都大学の出口康夫先生の言葉ですが、「私たちとしての自身」という考え方で、人間だけでなく、システムやモノもWeの一部とします。
メタバースが今注目されていますが、アバターもWeの一部ととらえることで、サイバー空間での主観や主体性、法的概念が明確化されるのではないかと思います。Self-as-Weは、つながる人同士、みんなが幸せになっていこうという概念にも通じ、基本的に利他、自然に近い構造になるでしょう。多様性を包摂し、1人ひとりのウェルビーイングを最大化しようという社会を実現するためには、デジタル技術はもちろん必要条件です。しかし、その十分条件として、技術を社会に実装するためのルールや基本的な法律も熟成させていかなければ、ICTを使いこなすことはできないと考えています。
新しい情報通信インフラIOWN
NTTの取り組みを紹介します。2030年の実現に向けて、Innоvative Optical and Wireless Netwоrk、IOWN (アイオン)という構想を掲げています。IOWNは新しい情報通信インフラで、ハード面でいうと光、半導体レベルでいえば光電融合、あるいはその向こうの光半導体、ソフトウェアでいうと、いろいろなシステムを横つなぎできるようなコグニティブ・ファウンデーションです。先に触れたバイオデジタルツインのような一連のコンポーネントから成り立っています。他の生物だけでなく、個々の人間においても環世界が生じつつある中で、それをつないでいくメディアではないかと定義しています。
NTTはまた、オリィ研究所が運営する分身ロボットカフェを技術的にお手伝いしています。分身ロボットカフェでは、病気などで外出が困難な方が遠隔操作するロボット、OriHime-Dが接客します。お店は東京・日本橋にありますが、ロボットのパイロットは遠方の名古屋や病院などにいます。通常のネットワークではロボットの操作に合計で0.06秒くらいの遅延が生じますが、IOWNの技術でこの遅延を3分の1以下に実現することができています。デジタル化せずに自然をそのまま送る技術ともいえ、今年はeスポーツや医療現場でも展開していきたいと考えています。
東京オリンピックの時に限られたエリアで、XR(Extended Reality)の技術を使って透明な画面端末にお店の情報を提示する実験を行い、成功させました。技術が進めば、画面を介さずに直接脳に情報を伝達する時代が訪れるのではないかと思います。日比谷地区の再開発プロジェクト、TОKYО CRОSS PARK構想にも関わっています。「人を大事にする街づくり」というコンセプトをデジタル技術で支えます。
お話ししたことをまとめますと、まず生命は動的平衡で、自然は多様であるということです。社会から多様性が欠如してはいけません。何か1つのことを正しいとみなすのではなく、多様なものをどう包摂するかというのが重要な視点になります。そういう考えのもと、ICTが求められることは2点あると考えます。多様で自然であることをデジタルで実現するというのは矛盾しています。そこでパラコンシステント、同時両立という概念が必要だろうと思います。もう1つは、異なる環世界をつないでいくことです。技術と制度、技術とルールを同時に実現していくことも必要ではないかと考えています。