 一覧
一覧

緑川 晶【略歴】
感覚の過敏性を通じた理解
緑川 晶/中央大学文学部教授
専門分野 臨床神経心理学
認知症の症状
認知症はその定義[i]にもあるように、脳の病気を背景として「覚える」「考える」「認識する」などの脳の高次な機能(認知機能や高次脳機能とも呼ばれています)が次第に低下する状態です。
古くは有吉佐和子の原作で映画やテレビドラマともなった「恍惚の人」や、近年でも渡辺謙が主演し日本アカデミー賞を受賞した「明日の記憶」などの作品にも表現されるように、認知症は治らないし、ひとたび発症すると本人も家族も苦しむため、認知症になるのは嫌だ、認知症は怖いという先入観がもたれているようです。
残念ながら認知症は治らないというのは医療や技術が発達した今日でも変わりありません。ただ、実際に認知症の方々に認められる症状は実は複合的で、覚えることの障害である「物忘れ」や考えることの障害である「遂行機能障害」のほかに「物盗られ妄想」や「徘徊」などの症状も含まれますが、前者は脳の病気を直接反映したもので、以前は中核症状、最近では認知機能障害と呼ばれています。これらは脳の特定の領域が担っていた機能が脳の病気によって失われたと考えられています。一方、後者は周辺症状、また最近では「認知症の行動・心理症状:behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD)」と呼ばれています[ii]。その一部は認知機能障害と本人達を取り巻く周囲の環境との間の相互作用によって生じるとも考えられています。
たとえば物盗られ妄想は、認知機能障害の物忘れとともに、それまでの自身が担っていた家族の中での役割の喪失感や不安が背後にあるとも考えられています。BPSDは介護負担感に影響することが知られていますが、一方で、家族の中での役割の見直しや不安の軽減などによって落ち着くこともあります。したがって、認知症は治らないというのは、実は認知機能障害の方であり、BPSDについては対処の可能性は残されていますし、家族でも実践することができます。
認知症の背後に隠された過敏性
私たちの研究グループでは、BPSDの原因の一つとして感覚の過敏性があるのではないかと考えています。これはある患者さんの家族の対応から気づかされたことですが、それまでとても温厚だった旦那さんが認知症の症状の進行とともに、大好きだった孫にもイライラを示すようになりました。最初は奥様も理由が分かりませんでしたが、もしかしたら孫達の声が気に障るのではと考え、家族とは距離を置いた「離れ」に夫婦で過ごすようにしたところ、それまでのイライラを示すことはなくなり、以降は穏やかに過ごすことができたそうです。本来は嬉しいはずの子ども達の元気な声が実は本人には苦痛だったようです。
このような事例をヒントに、認知症を発症してからの変化を低下以外の面から捉える試みを開始しました。その結果、多くの患者さんで感覚面での変化(過敏性)やポジティブな方向での認知的な変化が生じていることが明らかとなりました(図)[iii]。
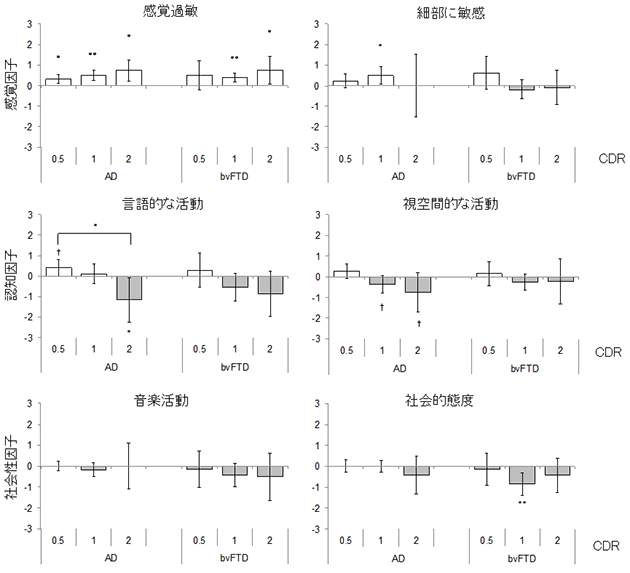
〔略語〕CDR:臨床的認知症尺度,AD:アルツハイマー病,bvFTD:前頭側頭型認知症(行動異常型)
図中のプラスは認知症を発症して増加した機能、マイナスは減少した機能。アルツハイマー病と前頭側頭型認知症(行動異常型)のいずれも認知症を発症すると感覚の過敏性が増加することが明らかである。また一部の患者では視空間的な活動、たとえばパズルや描画などの取り組みの増加が見られた。
類似性としての理解
過敏性は実は認知症に限ったことではありません。発達障害の分野では、以前から当事者の方々は感覚の過敏性に悩まされていることが知られています。聴覚だけではなく、視覚や触覚においても定型的な発達の人と比べると鋭敏な感覚があり、それによって悩まされていることも少なくありません。
このように感覚の過敏性という切り口で見ると、認知症や発達障害の間に類似性があるのかもしれません。また頭痛がある人々の中には特定の視覚刺激が不快感を誘発することが知られています。そのような意味では、感覚の過敏性は特別なものではないのかもしれません。
そこで2018年の4月から日本学術振興会の基盤研究(A)の支援を受けて「過敏性を通じた発達障害や認知症の連続的理解」と題したプロジェクト(筑波大学小山慎一氏、国立障害者リハビリテーションセンター研究所井手正和氏との共同研究)を開始しました。この研究を通じて、当事者の方々の主観的な世界を理解した上で、その軽減方法を探り、過ごしやすい環境の構築を目指したいと思います。
- ^ 「通常、慢性あるいは進行性の脳疾患によって生じ、記憶、思考、見当識、理解、計算、学習、言語、判断等多数の高次脳機能の障害からなる症候群」ICD‐10 精神および行動の障害―臨床記述と診断ガイドライン(医学書院,2005)
- ^ 認知症疾患診療ガイドライン2017(医学書院,2017)
- ^ Midorikawa, Akira, et al. "All is not lost: positive behaviors in Alzheimer’s disease and behavioral-variant frontotemporal dementia with disease severity." Journal of Alzheimer's Disease 54.2 (2016): 549-558.
- 緑川 晶(みどりかわ・あきら)/中央大学文学部教授
専門分野 臨床神経心理学 -
東京都出身。 1971年生まれ。 1995年中央大学文学部卒業。2002年中央大学大学院文学研究科博士後期課程修了。 博士(教育学)。脳の機能障害によって生じるマイナスの変化だけではなく、プラスの変化についての研究を行っている。
主要著書に『臨床神経心理学』(共編著)(医歯薬出版、2018年)、『音楽の神経心理学』(医学書院、2013年)、論文に、『The emergence of artistic ability following traumatic brain injury』(共著)(Neurocase誌、2014年)などがある。








