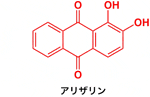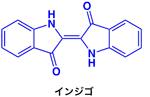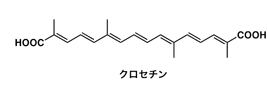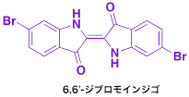一覧
一覧
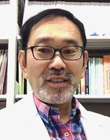
福澤 信一【略歴】
有機化学文学館–文学作品の中の有機化学
福澤 信一/中央大学理工学部教授
専門分野 有機合成化学
はじめに
有機化学は難しい化学構造式のせいか、多少の化学の知識があっても、一般の人々には敬遠される学問かもしれない。しかし、有機化合物は、染料、香料、医薬品から液晶、有機ELまで広範囲にわたって人々の身の回りに溢れており、現代の日常生活になくてはならないモノである。有機化合物は人々の日常生活に入り込んでいるので、幾つかの文学作品の中で垣間見ることが出来る。文学と化学という懸け離れた世界ではあるが、人々に文学作品の中に有機化学を発見して、文学と化学の両方の教養を身につける楽しみを感じてもらいたいと考えている。なお、この解説では、あくまで有機化合物およびそれらに関連した人々が主体であり、文学作品の内容については、間違った解釈をしているかもしれないことを了承していただきたい。
タカジアスターゼと明治時代の化学者達–「吾輩は猫である」(夏目漱石)
この有名な作品は、猫の目から見た人間の世界を風刺したユーモア小説である。猫(吾輩)の主人こと苦沙弥先生は胃が弱いにもかかわらず大食家で、大飯を食った後でタカジアスターゼを飲んでいる。ところが、しばらくすると、妻にタカジアスターゼを飲むように勧められてもそれは利かないからと頑固に拒む。
さて、ここで出てくるタカジアスターゼとは明治時代の化学者、高峰譲吉博士が発明したデンプン消化酵素で胃腸薬である。タカジアスターゼのタカは高峰の名前とギリシャ語で強い・最高の意味に由来しているらしい。また、高峰譲吉と助手の上西啓三は1900年に副腎からアドレナリンを結晶として世界で初めて取り出すことに成功している。アドレナリンとは、ホルモンの一種で交感神経興奮作用をもたらす物質で、血管収縮作用がある。夏目漱石と高峰譲吉とは小説上の接点しかないが、実生活では化学者、池田菊苗と接点があった。池田菊苗は、かつお節の旨味成分がグルタミン酸ナトリウム(味の素)であることを発見したことで知られている。池田菊苗は東京帝国大学の助教授時代にドイツとイギリスに留学しているが、ロンドンで夏目漱石と同じ下宿で暮らしている。漱石は「処女作追懐談」の中で、菊苗との出会いは自分には大変な利益であったと述べている。
ヘリオトロープ–「三四郎」(夏目漱石)
夏目漱石の作品からもう一つ、「三四郎」を取り上げる。東京帝国大学に合格し九州から上京した小川三四郎は真面目な田舎者で、女性関係には全く初心な青年である。ある日、三四郎は大学構内の池(現在の三四郎池)のほとりで若く美しい女性、里見美穪子を偶然目にする。三四郎は美穪子に恋心をいだいたようだが、美禰子は、今風で言う小悪魔的、あざとい女なので、三四郎は彼女に翻弄される日々が続く。ある日、三四郎がシャツを買いに出かけたとき美禰子も買い物に出かけており、彼女から香水の相談を受ける。「ヘリオトロープ」という瓶をもってこれはどうですかというと、美禰子はそれにしましょうと言う。美禰子が別の男と結婚することになり、三四郎との別れのシーンで、美禰子のハンカチが三四郎の顔の前に来たときに鋭い香りがし、美禰子は「ヘリオトロープ」と言う。
ヘリオトロープは、ムラサキ科ダチルリソウ属の植物の総称であり香水草と言われている。三四郎が選んだ香水ヘリオトロープは、ヘリオトロープの香りがするヘリオトロピンという合成香料である。ヘリオトロピンは芳香族アルデヒド系の香料であり、天然に存在するサフロールから合成される。ヘリオトロープがこの作品の中で、三四郎の心を惑わす小道具として用いられているようである。人々は、匂いは異性を誘惑する道具となると信じて、天然の香料を追い求めている。例えば、ジャコウジカの雄の精嚢から発するムスコン(麝香)はメスを惹き付ける力があるので、これを手に入れれば、人であっても異性を誘惑できるかもしれないという欲望に駆られる人たちが存在する。

図1 ヘリオトロピンとサフロールの構造式
シコニン、アリザリン–万葉集(額田王(ぬかたのおおきみ)、大海人皇子(おおあまのみこ))
匂いは人を惹きつける効果があるように、また色も人を魅了する。色には色彩というモノの表面の状態を表す意味と、男女の情愛に関するものごとの意味がある。ここでは、万葉集の中から額田王と大海人皇子の情愛と色彩のもと即ち色素に関する作品を紹介する。額田王と大海人皇子は恋愛関係にあったが、大海人皇子の兄である天智天皇の妻にされてしまう。額田王は人妻であるが、かつての恋人の大海人皇子への気持ちは変わらない。万葉集の中に、額田王が思い人である大海人皇子に対して詠んだ句がある。
「あかねさす紫野行き、しめ野行き、野守はみずや君が袖振る」(あなたは、あかね色に帯びている紫草の生えている野やしめ野を行ったり来たりして、私に袖を振ったりしている。こんな様子を野の番人に見つかったらやばいよ)。
大海人皇子からの返し歌として、「紫草のにほえる妹を憎あらば、人妻ゆえに、われ恋いめやも」(紫草のように綺麗なあなたを憎いはずがないよ。もし憎かったら、私はこんなにあなたのことに夢中になることはないよね)。叶うことのない恋愛に対する2人の切ない気持ちが読み取れる。
井上靖の小説「額田女王(原題)」の中に、紫草は根を紫色の染料にすると聞いているが、小さい白い花を見ていると、額田には紫色は思い浮かばなかったという一節がある。紫草の根にはシコニンという紫色の色素が含まれている。あかねさすは紫の枕詞であるが、あかね(茜)自体は植物でもあり、その根からアリザリンという赤色の染料が抽出される。シコニンとアリザリンは、化学的にはキノン系染料であり、古代日本の2人の男女が読んだ歌には、奇しくも共通した化学構造の物質が関係しているとは、ロマンを感じざるを得ない。ちなみに、大海人皇子、中大兄皇子(天智天皇)と額田女王の三角関係の物語が、宝塚歌劇団で「あかねさす紫の花」という演目で上演されている。
クロセチン、インジゴ、カルタミン–枕草子(清少納言)
古典から色素に関する作品をもう一つ紹介する。清少納言の随筆、枕草子に、「指貫(さしぬき)はむらさきの濃き、萌葱(もえぎ)、夏は二藍(ふたあい)、いと暑きころ、夏虫の色したるも涼しげなり」(はかまは濃い紫色、萌葱(もえぎ)が良いよね。夏は二藍、めっちゃ暑いときは薄緑色が涼しげで良いよね)という一節がある。たわいもない、衣装の色に関する趣味を述べた文である。
萌葱は葱が萌え出る色で明るい緑色である。この色は、青色の藍と黄色のクチナシの色素を混合して調合する。藍の色素はインジゴであり、現代ではアニリンを原料に工業的に合成されている。クチナシの色素はクロセチンであり、炭素–炭素二重結合が7つ直線上に連なった化合物である。炭素–炭素二重結合の数が多くなると、次第に色は赤みがかる。例えば11個連なった化合物として、トマトやスイカの赤色としてリコピンや、ニンジンのオレンジ色としてβ–カロチンが知られている。化粧品(アスタリフト)に含まれるアスタキサンチンもこれらの仲間で、抗酸化作用を持つと言われている。二藍は紅花で染めた上から藍で染めた青紫色であるが、紅花の赤色の色素はカルタミンである。紅花の花の色は黄色であり、黄色の色素サフロールイエローと赤色の色素カルタミンが含まれている。カルタミンは紅花にわずか1%程度しか含まれていないが、水に対する溶解度の差を利用してサフロールイエローから分離できる。
貝紫(6,6'-ジブロモインジゴ)–貝紫幻想(芝木好子)
この作品は題目通り、色にまつわる話である。圭子は、東京に暮らし、出版社の編集部に勤めている。ある日、京都から母の異母弟である泰男が鎌倉を訪ねてくる。泰男は京都の大学の講師であり、アクキガイからとれる染料「貝紫」を研究している。圭子は、泰男に惹かれながら同じく貝紫の魅力にもとりつかれていく。実は、圭子と泰男は血の繋がった叔父と姪という間柄でありながら、男と女として愛し合ってしまうという、かなりきわどい話である。
貝紫とは6,6'-ジブロモインジゴ(6と言う数字は臭素がインジゴに結合している場所を指している)で、藍から取れるインジゴに二つの臭素基が結合した構造である。臭素基がインジゴに結合することで、色は青色から濃い紫色に色調が変化する。6,6'-ジブロモインジゴはアクキガイ1000個から1グラム しか取れない非常に貴重・希少な色素である。そのせいか、貝紫は帝王紫とも言われ、権力者に好まれた。古代日本においても、冠位十二階の制度では濃い紫色は最上位、大徳の色と指定されており、身分の最も高い人の服装の色である。貝紫は天然には僅かしか産出されないが、有機合成化学の研究で、容易な合成方法が提案されている。この化合物の、炭素–臭素結合を切断して、別の有機化合物とのクロスカップリング反応を行うと、インジゴに機能を持たせることが出来、太陽電池の増感剤などへの応用が期待されている。
終わりに
以上、古典から近代文学の中の有機化学の世界の一端をお見せした。ここでは、文字数の関係で僅かな作品しか紹介できなかったが、古典、純文学だけでなくミステリーやSFも含めると、私自身は50くらいの文学作品の中に有機化学を見つけている。卒業研究のテーマとして調査してくれた学生もいたので、その成果は、私のホームページに掲載している。
- 福澤 信一(ふくざわ・しんいち)/中央大学理工学部教授
専門分野 有機合成化学 - 新潟県出身。 1956年生まれ。 1979年京都大学工学部卒業。
1984年京都大学大学院工学研究科博士課程修了。工学博士(京都大学 )
1991年中央大学理工学部助教授を経て1999年より現職、
現在の研究課題は、有機合成化学、有機金属化学(立体選択的および多様性合成のための新手法および新反応剤・新触媒の開発)などである。
また、著書に、『ベーシックマスター 有機化学』(共著、オーム社、2011年)などがある。論文数150以上。