 一覧
一覧

山科 満 【略歴】
教養講座
大学における発達障害者支援の背景
山科 満/中央大学文学部教授
専門分野 臨床心理学
筆者は2012年度から中央大学共同研究プロジェクト「中央大学における発達障害を抱える学生の実態把握と教育・発達的支援に関する研究」の一員として、文学部心理学専攻の都筑学教授(研究代表者)、緑川晶教授、上林靖子元教授、新たに加わった法学部の宮崎伸一教授とともに、調査研究に従事している。昨年度は多くの教職員のご協力を得て全学的な調査を行い、その一部は中間報告書という形で学内に配布することができた。本稿ではこの調査研究の背景となる事柄について述べる。
1.発達障害とは~法律面から~
発達障害という言葉はわかりにくい。「発達」も「障害」もごく一般的な言葉あるが、両者が合体した途端に狭く限定された特別な用語となる。その本質論への深入りは避け、ここではプラクティカルな観点からの発達障害の定義を参照したい。2004年に制定された発達障害者支援法において、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされている(図1)。
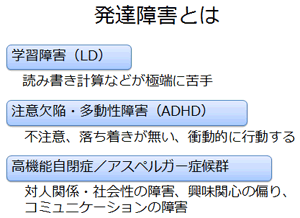
図1:発達障害の種類と特徴
この法律制定以前から、全般性発達障害(いわゆる精神発達遅滞)や典型的な自閉症に対する施策は教育・福祉両面で行われていた。この法律で改めて発達障害を上述のように定義したのは、通常級に存在し時には大学まで進学し社会に出た人の中に、支援が必要な人が相当数存在するということが、現場からの報告と調査研究の両面から切実な問題として浮かび上がってきたからである。
そのため、同法第8条第2項には、「大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする」と明記されている。このことをわかりやすく例えるなら、車いす利用者を迎え入れるために大学の施設をバリアフリー化するように、また視覚障害や聴覚障害の人に対してはノートテイクのボランティアを差し向け教員も授業方法を工夫するように、発達障害の人にも教育上相応の配慮をしなさい、ということであろう。
2.発達障害における「脳機能障害」
「脳機能障害」という言葉には説明が必要かもしれない。機能障害に対比されるのは、器質性障害である。後者は、脳が出血や外傷、あるいは腫瘍の存在によって脳細胞の死滅など物理的な変化を生じ、それに対応して神経症状(運動障害、意識障害など)や精神症状を呈するものをいう。一方機能障害というときは、脳の物理的な変化は同定されず、もっぱら表出される言動(検査や本人の自己申告も含む)に異常が認められるものを指す。
言動に表れる異常は、質的な異常と量的な異常に分けられる。質的な異常とは、本来なら存在しない現象が認められるもので、例えば幻聴という現象は脳機能の質的な異常といえる。量的な異常とは、通常は誰にでも存在するものだがその量(ないし強さ)が著しく偏っているものをいう。例えば「こだわり」は誰にでも何かしらあるものが、その強さが極端で適応に支障を来している、というような場合である。もっとも、直接測定できないものの量を論じるには、測定のための物差し(評価尺度)を用いて対象を計量化する手続きを経て初めて可能になる。この手続きが煩雑であるため、臨床現場では専門家といえども経験に基づく直感を頼りに症状を同定し評価している場合が多い。専門家の評価が今ひとつ信頼性に欠けると感じられる所以であろう。
脳とは、進化の過程で獲得されたさまざまな機能の寄せ集めで成り立っている、という考えがある。その考えに則すれば、学習面での機能、注意集中の機能、対人関係にまつわる機能といった特定の機能のひとつないし複数の領域で障害(量的な異常)が生じたのが発達障害なのだといえよう。つまり、ベースにある脳機能障害に対応して能力に著しい偏り(凸凹)が生じ、社会適応に困難を来しているのが発達障害なのである。また、発達障害における障害とは固定されたものではなく、むしろ発達の「遅れ」が本質であり、成長促進的な支援こそ必要であるという見解があることも付け加えておきたい(滝川一廣『こころの本質とは何か』)。
3.誤解されやすい発達障害者
目に見えない障害であるため、大学に進学した発達障害者を、専門知識を持たない人がそれと気付くことは極めて難しいに違いない。例えば、履修登録の際にごく基本的なルールや係員からの指示が理解できない人には、「よくあれで大学に入れたものだ」という声が上がるかもしれない。ゼミで自分の興味関心事ばかり話し他人とのディスカッションができない人は「自己中心的な人」と言われてしまうであろう。教員が口頭で指示した課題をやってこなければ、「やる気のない人」と見なされるのではないか。忘れ物が多く時間を守れない人は「ルーズな人」として就職活動場面では真っ先にふるい落とされる。そのような「困った学生」たちの中に、実は発達障害に該当する人が存在している可能性がある。発達障害を有しながらも大学まで事例化することなく進んできた人がつまずくきっかけは入学時の出だしであり、3年時のゼミであり、就職活動場面である。
前述の特徴は、本人はさほど困っておらず周りが対応に苦慮している場合もある。特に対人関係での共感・協調の欠如といった特徴についてはそのような事例が散見される。しかし筆者の経験では、関係が深まった後でよくよく尋ねてみると、彼らの言動に表れる共感・協調の欠如は彼らなりの防衛(心の鎧)であって、一定の合理性のある言動である場合も少なくない。逆に周囲からの評価をよく認識できている人は、それゆえに低い自己評価に苛まれていることもある。努力しても改善の兆しがなければ、周囲は「性格の問題」とみなしがちであるし、本人も否定的同一性(「どうせ自分は・・・」という思考・態度)を身につけ希望を失っていくことになる。
4.大学における支援~他大学を参考に~
大学における発達障害者への支援は端緒についたばかりであり、多くの大学は手探りで行っている段階である。共同研究プロジェクトでは先進的な取り組みを行っている富山大学を視察し、さまざまな示唆を得た。ここにその一部を紹介する。
富山大学の場合、「学生支援室」に「トータルコミュニケーション支援部門」を設置して発達障害学生を多角的に支援するシステムを作っている。支援部門には特任准教授と嘱託(常勤)の心理士を貼り付け、学生支援室所属の専任教員2名と合わせて専従4名体制で支援にあたっている。ユニークなのがソーシャルネットワーキングサービスの活用であり、これにより学生は24時間サポートシステムへのアクセスが可能となる。教務やキャリア支援との連携も円滑である。そもそもワンストップサービスを提供すべく「学生支援室」が運営されており、学生の立場からは、「どの窓口に行ってもたらい回しに遭うことなく必要な支援をそのときその場で受けられる」ことになる。
ここで「必要な支援」とは、必ずしも学生が自覚し表明するニーズとは限らない。学生の自己理解には幅がある。また、医学的な診断の有無も関係ない。「困っている学生に対し、困り具合に応じた最適な支援を」提供する、という姿勢が重要なのだという。この支援システムを構築しようとした直接のきっかけは学生の自死が続いたためであり、真に実効性のある対策を立てようとした結果、現在のシステムにたどり着いたとのことである。
中央大学ではどのようなシステムが構築可能であるのか、そもそもどのようなニーズがあり、何を目指すべきなのか。プロジェクト内でも議論は始まったばかりである。
5.終わりに~精神科医として~
筆者は精神科医としてクリニックや企業内の健康管理センターで診療やカウンセリングを行っており、就職後1~2年のうちに不適応で事例化する発達障害の若者には以前から出会ってきた。この数年「アスペルガー」という言葉が一般に流布するようになり、さらに昨年あたりから ADHDに関する製薬企業の啓蒙活動が盛んとなった影響であろうか(その是非はここでは触れない)、自ら発達障害の診断と治療を求めてクリニックを受診する若者がこのところ急激に増加しつつあり、最近の筆者の外来はさながら「青年期発達障害外来」の様相を呈するようになっている。
受診する彼らの多くは、「自分はどこか変だ」「他人と違っている」という意識をある時点から抱きつつ、苦労しながらここまで育ち上がってきていた。しかし、そのことを他人に相談することはないまま孤独な闘いを続け、行き詰まっての受診である。医学モデルでの支援に限界があることは彼ら自身知っているのだが、強い抑うつ感から藁にもすがる思いで来院している。そのような若者に出会うたびに、筆者は「もっと早い段階で支援が入っていたら、違った展開があっただろうに」と思わずにはいられなかった。
理想論ではあるが、発達障害者が過ごしやすい社会とは、そうでない人にとっても過ごしやすい社会であるに違いない。もし大学のキャンパスが発達障害者にフレンドリーで、その中で彼らが安心して自己理解を深め成長していけるような場であったとしたら、それはキャンパスを構成する多くの人にとっても居心地の良い場になるであろう。私が願っているのは、大学という場がそのようなものになっていくことである。
大言壮語は慎まねばならない。私たちは、まずは現にいる発達障害を抱えつつ行き詰まり途方に暮れている学生に対して、彼らが大学時代のうちに人生の方向性を見いだし展望が開けるような支援を、手探りで行っていくことになるであろう。調査研究と臨床活動は支援システム構築のための車の両輪である。多くの同僚からの助力を得ながら目標に向かって進んでいきたい。
- 山科 満(やましな・みつる)/中央大学文学部教授
専門分野 臨床心理学 - 青森県出身、1961年生まれ。
1989年新潟大学医学部卒業。
東京都立松沢病院医員、順天堂大学医学部助手・講師、文教大学人間科学部教授を経て、2010年より現職。
医学博士(順天堂大学)、精神科専門医、臨床心理士。
専門は青年期精神医学、精神分析的精神療法。臨床現場と心理学教育の架け橋となることを目ざし、臨床研究に取り組んでいる。
著書として『精神分析的発達論の統合②』(共監訳)、『精神分析的診断面接のすすめ方』(共著)、ほか。








