 一覧
一覧

浅田 統一郎 【略歴】
教養講座
安倍新政権の金融政策の経済学的根拠について
浅田 統一郎/中央大学経済学部教授
専門分野 マクロ経済学、特にマクロ経済動学
2012年12月16日に行われた衆議院総選挙で、安倍総裁率いる自民党が議席を総選挙前の2.5倍に増やして過半数の議席を獲得し、連立政権を組むことを予定している公明党を含めると衆議院の3分の2以上の議席を占め、史上2度目の安倍政権が誕生することが確実になった。総選挙前に政府与党であった民主党は、議席を総選挙前の4分の1以下に減らす大敗を喫した。今回の総選挙は合計12の政党が乱立して行われたが、結果的に「脱原発」「憲法改正」等は大きな争点にはならず、そのかわりに大きく浮上したのが「景気対策」、特に「金融政策」であり、結果的に自民党の圧勝に終わった。現に、テレビで報道された世論調査によれば、選挙民の約半数が、投票にあたって「景気対策、雇用対策」を最も重視したと答えている。
安倍総裁が率いる自民党は、今回の衆議院選挙の政権公約として、「年間2%の物価上昇目標(インフレ目標)を明確に設定して、日銀法の改正も視野に、政府・日銀の連携を強化する仕組みを作り、大胆な金融緩和によってデフレ・円高からの脱却をはかる」ことを掲げた。同様の政策は従来からみんなの党などによっても主張されていたが、政府与党になる可能性が高い大政党によって選挙公約として正面から掲げられたのは初めてであり、これによって、日本の総選挙史上、「金融政策」が初めて大きな争点の一つとして浮上した。このことは、画期的な出来事として記憶するに値する。筆者は自民党の原発政策や憲法改正案を支持していないが、安倍新政権が総選挙前から打ち出した金融政策は基本的に正しく、妥当であると考える。このような金融政策は、日銀は決して実施しようとはしなかったが、米国のFRBをはじめとして、日本以外の先進国の中央銀行が普通に実施している世界標準の金融政策に過ぎない。以下では、この金融政策の経済学的根拠を簡潔に述べる。そのためにまず、現在では「失われた20年」と形容される1990年代から2000年代にかけての日本経済のパフォーマンスを示すマクロ・データを概観しよう。
日本経済の「失われた20年」の実体
図1は、1980年から「サブプライム・ショック」直前の2007年までの28年間にわたる失業率とインフレ率(消費者物価上昇率)の関係を示す日本の「フィリップス曲線」である。この図によれば、年率平均2%程度の緩やかなインフレを継続した1980年代の「完全失業率」は2%台であったのに対し、インフレ率が年率平均マイナス1%前後の緩やかなデフレ(物価下落)に陥った2000年代には、「完全失業率」は5%前後になった。日本の「完全失業率」という指標は、欧米の指標に比べて「失業率」が極端に低く出るバイアスを持っているが、重要なことは、同一の指標で測った日本の「失業率」が2000年代には1980年代のほぼ倍になったという事実である。なお、1996年から1997年にかけてインフレ率が1年間だけ約2%上昇したが、それは、橋本政権下で消費税が3%から5%へ2%分引き上げられたことを反映しており、このことは、その後のデフレ不況の悪化を助長してしまった。
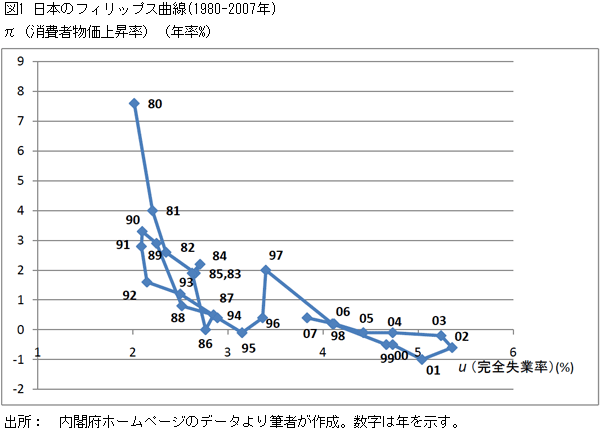
このように2000年代の日本経済は、年率1%前後の緩やかな持続的物価下落(デフレ)を伴う長期停滞に陥ったが、この過程で、失業率が上昇しただけではなく、図2に示されるように、金額で測った国民の総所得を表す指標である名目GDPの成長率(名目成長率)と国民の実質的な経済的豊かさの指標である実質GDPの成長率(実質成長率)の双方が、密接に連動しながら低下していった。このように、年率1%前後の緩やかなデフレでも、国民の名目所得のみならず実質所得や失業率に深刻な影響を及ぼすことが、問題なのである。
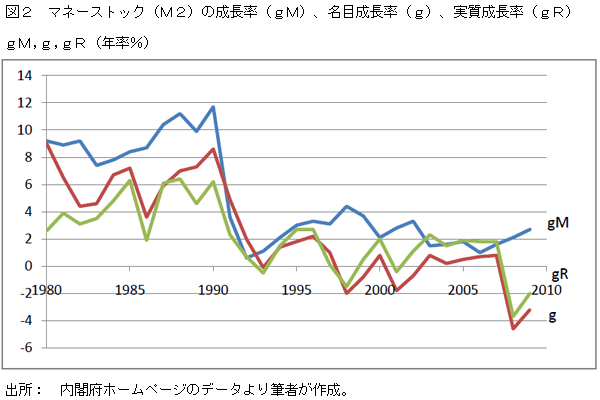
デフレ不況の根本原因
それでは、20年間にもわたって続いた日本のデフレ不況の主要な原因は、何であろうか。結論を言えば、その主因は、20年間にもわたって続いた、日本銀行(日銀)による極度に消極的な金融政策である。この結論は、「ある国のインフレ率は中長期的にはその国に存在するマネーの成長率によって最も大きな影響を受け、マネーの成長率を制御する能力と権限を持っている機関は中央銀行だけである」ことを認める限り、否定することはできない。
高橋洋一氏(嘉悦大学教授)が示しているように、各国のインフレ率とマネーストックの成長率の間には統計的に密接な関係があり、2000年代における日本のインフレ率とマネーストックの成長率はいずれも、同時期の他国に比べて極端に低い(文献[2]参照)。同様の事実は、図2によっても確認することができる。この図は、過去30年間の日本経済において、名目成長率(g)および実質成長率(gR)が、マネーストック(M2)の成長率(gM)と極めて密接に連動して動いていることを示している。また、この図において、gとgRの差(g-gR)は、GDPデフレーターの上昇率(ある種の指標で測ったインフレ率)を示している。すなわち、インフレ期にはgがgRを上回り、デフレ期にはgがgRを下回る。この図は、1980年代には年率平均10%程度のマネーストックの成長率が年率平均6%程度の名目成長率、4%程度の実質成長率と2%程度のインフレ率を支えていたのに対し、1990年から1993年にかけて「バブルつぶし」を意図した日銀の金融引き締めによる急激なマネーストック成長率の低下に誘発されて名目成長率も実質成長率も急降下したことを示しており、また、図1に示されるように、その過程でインフレ率は低下し、失業率は増加した。1990年代以降は、約20年間にわたって、日銀はマネーストックの増加率を1980年代の5分の1の年率2%前後に抑えるようになり、その結果、平均名目成長率は年率マイナス0.7%程度、平均実質成長率は年率0.6%程度、平均インフレ率は年率マイナス1.3%程度になった。
すなわち、極度に消極的な日銀の金融政策が、20年間にもわたるデフレ不況を定着させたのである。なお、図2において、1997年の景気の落ち込みは消費税増税の影響により、2008年の急激な落ち込みは、米国発の「サブプライム・ショック」による世界金融恐慌の影響により、引き起こされている。日銀の金融政策以外の原因によるこれらの落ち込みを除いて、マネーストックの変化に1年から2年程度のタイム・ラグ(時間の遅れ)を伴って名目成長率と実質成長率の変化が追随しているのがわかる。
日本の名目GDPは1997年に記録した521兆円が最高であり、2011年の大震災の影響をまだ受けていない2010年においてさえ、1997年より41兆円も少ない480兆円にまで低下してしまった。もし1997年以降日本の名目GDPがOECD諸国の平均である年率4%で成長し続けていたら、現在の日本の名目GDPは約900兆円になっていたであろう。この場合には、現在日本で顕在化している税収不足問題も、国債残高の対GDP比の急上昇も、社会保険や社会保障の財源の不足問題も発生せず、財務省も消費税率を引き上げる口実を失っていたであろう。
人口減少デフレ説の誤りと円高デフレについて
日銀の金融政策はデフレ不況に責任がないということを主張する論者(直接の利害当事者である日銀を含む)は、インフレ率は「マネー以外の何か」、したがって、「中央銀行の金融政策以外の何か」によって主として決定されると主張する傾向がある。その中でも最も大きな影響力を持ち、日銀の白川総裁も講演で利用した仮説として、藻谷浩介氏(日本政策投資銀行参事役)が流布した「デフレの原因は人口減少による少子高齢化である」という「人口減少デフレ説」がある(文献[4]参照)。しかし、岩田規久男氏(学習院大学教授)と高橋洋一氏が統計データに基づいて指摘しているように、各国の人口成長率とインフレ率の間には実際には何の相関関係もない(文献[1][2]参照)。
最後に、「デフレの原因は円高にある」という説について考えよう。確かに、円高により輸入財の国内価格が低下するので、このことによりデフレが促進される。しかし、浜田宏一氏(イェール大学名誉教授)が指摘しているように、「国際金融論のマネタリー・アプローチ」によれば、中長期的に為替レートを左右するのは、各国に存在するマネーストックの相対比率である。すなわち、他国に比べて相対的にマネーストックを増やした(減らした)国の通貨は、それ以外の国の通貨に比べて相対的に安く(高く)なるのであり、この命題は実証的にも支持されるのである。すなわち、2008年のサブプライム・ショック後の急激な円高の原因は、日銀の金融緩和が他国(特に米国)の中央銀行に比べて極度に消極的だったことにある(文献[3]参照)。結局、デフレの原因と円高の原因は同じなのである。
総選挙の翌日である12月17日の読売新聞によれば、浜田宏一氏がデフレ・景気対策の助言役として、新内閣の内閣官房参与(経済担当)に起用された。浜田氏は、日銀法の改正を視野に入れた安倍政権の金融政策において、重要な役割を果たすことが期待される。
参考文献
- [1] 岩田規久男(2012)『日本銀行デフレの番人』(日本経済新聞出版社)
- [2] 高橋洋一(2012) 『グラフで見ると全部わかる日本国の深層』(講談社)
- [3] 浜田宏一・若田部昌澄・勝間和代(2010)『伝説の教授に学べ! 本当の経済学がわかる本』(東洋経済新報社)
- [4] 藻谷浩介(2010) 『デフレの正体 -経済は「人口の波」で動く』(角川書店)
- 浅田 統一郎(あさだ・とういちろう)/中央大学経済学部教授
専門分野 マクロ経済学、特にマクロ経済動学 - 現職:中央大学経済学部教授。
1954年愛知県生まれ。1977年早稲田大学政治経済学部卒業。1982年一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位修得満期退学。経済学博士(中央大学)。駒澤大学経済学部助教授、中央大学経済学部助教授を経て、1994年より現職。現在の研究課題は、マクロ経済動学の方法に基づく経済変動およびマクロ経済政策の研究。また、主要著書に、「成長と循環のマクロ動学」(日本経済評論社、1997年、単著)、"Monetary Macrodynamics(Routledge, London, 2010, 共著)などがある。








