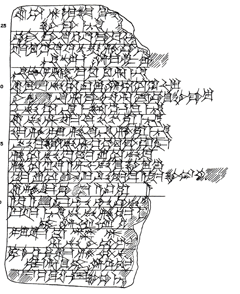トップ>研究>楔形文字文書と過ごす日々―シュメール語の文法を再構成する仕事―
 一覧
一覧

唐橋 文 【略歴】
教養講座
楔形文字文書と過ごす日々―シュメール語の文法を再構成する仕事―
唐橋 文/中央大学文学部准教授
専門分野 古代オリエント学
楔形文字とシュメール語文書
紀元前4千年紀末期、メソポタミア南部(今日のイラク南部)に住む人々が、粘土板に楔形文字を刻んで取引などに関わる文書を作成し始めた時、人類は「書く」という普遍的な行為の第一歩を踏み出した。その文字が表す言語はシュメール語であったと考えられている。書かれている文書の言語が、間違いなくシュメール語であるといえるようになるのは、それより少し時代が下って作成された文書からである。シュメール語文書の発掘と解読は、19世紀の後半、欧米の研究者たちによって開始され、1870年代には、シュメール語の文法書も出版された。シュメール語の研究史を振り返るたびに、私は、この研究の進度の速さに驚嘆する。
シュメール語はどの語族にも属さない孤立言語であるが、類型学的には、動詞や名詞の語幹に接頭辞や接尾辞がつく膠着言語(日本語もその一つ)で、他動詞の主語が能格、自動詞の主語と他動詞の目的語が絶対格をとる能格言語の一つである。語順は、一般的な文章では、主語・目的語・動詞となる。なお、シュメール語をトルコ語や、ハンガリー語、日本語などと関連づけようとする試みもあったが、いずれも学問的基盤が危うく、徒労に終わっている。
シュメール語で書かれた文書は実に多様である。王の功績を記す碑文や、王室の会計収支を扱う行政・経済文書、家屋や耕作地、奴隷などの売り買いに関する文書、裁判の判決を記す文書、単語を樹木や動物、魚、皮、などのテーマ別に集めた語彙集、英雄ギルガメシュなどの活躍をうたう叙事詩、シュメール・パンテオンの主神エンリルや、愛と戦争の女神イナンナ、知恵の神エンキなどにまつわる神話などがある。これらの文書は、紀元前3千年紀後半から2千年紀前半の長い年月にわたって作成されているので、シュメール語文法の再構成に用いられる際は、時代別に扱われるのが常である。大まかに、紀元前2500-2300年頃、2100-2000年頃、2000-1700年頃の三つに分けられる。
シュメール語の表記法
シュメール語は楔形文字で書き表される。楔形文字は一般的に表意文字とされるが、その文字には表音文字としての機能もある。例えば、![]() という文字を表意文字として使えば「水」という意味(発音は「ア」)になるが、同じ文字を(意味が取り除かれた音だけの)表音文字「ア」として使うと、後置詞となったり(日本語の助詞「~に、~で」にあたる)、動詞の接頭辞になったりする。表意文字としての漢字と、漢字を表音的に用いた万葉がなを混ぜ合わせて日本語の文章を書いているような状態を想像してみるのがよいかと思う。また、シュメール語の文章では、句読点も用いられないし、語と語の間にスペースも保たれない。このような表記法であるから、同じ文章を読んで違う解釈が出てきても、全く不思議はない。
という文字を表意文字として使えば「水」という意味(発音は「ア」)になるが、同じ文字を(意味が取り除かれた音だけの)表音文字「ア」として使うと、後置詞となったり(日本語の助詞「~に、~で」にあたる)、動詞の接頭辞になったりする。表意文字としての漢字と、漢字を表音的に用いた万葉がなを混ぜ合わせて日本語の文章を書いているような状態を想像してみるのがよいかと思う。また、シュメール語の文章では、句読点も用いられないし、語と語の間にスペースも保たれない。このような表記法であるから、同じ文章を読んで違う解釈が出てきても、全く不思議はない。
さらに、シュメール語の文書には、文法的に正しい文章に必要とされる要素が、いつも全て書かれていたとは限らない。例えば、接頭辞や接尾辞など、必要がないから書かれていないのか、あるいは、必要だが、省略されて書かれていないのか、現代の私たちには判断が下せない場合が少なくない。ネイティヴ・スピーカーに聞けばすぐにわかるようなことも、紀元前2千年紀初頭に話し言葉として用いられなくなってしまったシュメール語の場合、それは不可能である。すなわち、情報提供者もおらず、知識の連続性もないのである。また、同じ語族に属する言語との比較は、言語解釈の大いなる助けとなるはずであるが、孤立言語であるシュメール語には、その道も閉ざされている。ある著名な古代オリエント学者が、「シュメール語文法はシュメール語学者の数ほどある」と言ったが、その理由はここにある。そして、シュメール語文法解釈の多様性は、発言からおよそ半世紀が経った今もほとんど変わっていない。
書記のたまごたちが書いた文書
研究の振り出しからとても乗り越えられそうもない難題山積みであるが――そして、私自身、シュメール語文法再構成は果たして可能であろうかと、悲観的になることも度々あるのだが――実は、もう一つ心に留めておくべきことがある。それは、文法解釈に用いる重要なテキスト群を構成する英雄叙事詩や神話の多くが、前2千年紀前半、すなわち、シュメール語が町の通りから消えた時代に粘土板に書かれていることである(先述の文書の時代区分の第三番目にあたる)。しかも、それらは、後代に残すことを目的にオリジナルに忠実に書き写されたものではない。シュメール語以外の言語(セム系のアッカド語など)を母語とする子供たちが、文字を書くことを生業とする「書記」となる過程で、練習に書いた、それもお手本を見ながらではなく、聞き取り、あるいは暗記した文章を文字にしたものなのである。当時、シュメール語が修得語であったことは、「お前の舌はシュメール語には適さない」とか、「僕はシュメール語でも会話ができるよ」、また「シュメール語を知らない書記が、一体どのようにして正しい翻訳をするというのだろう」というような、書記になることを目指す子供たちの半ば罵りあいの会話に読み取ることができる。
シュメール語の複合動詞
私はこれまで、シュメール語の「複合動詞(compound verb)」、「持つ」と「持たせる」や「立つ」と「立たせる」といった動詞の使役の用法、強調構文のときの語順、文と文がどのような繋がり方をしているのか(従属関係か並列構文か)など、主として文章の構造(統語)上の問題を、様々な異なる言語と比較対照しながら研究してきた。ここでは、シュメール語の動詞全体のなかで大きな割合を占めている複合動詞を見てみよう。シュメール語文法でいう複合動詞とは、例えば「頭」+「与える」=「攻撃する」や、「木」+「触れる」=「(供物を)ささげる」など、名詞と動詞が対になって、それぞれの意味を足し合わせた以上の新しい意味を帯びた動詞のことを指す。特に数の多いのが、一番目の例のような「目」や「耳」「首」「頭」「手」「足」「心」など、身体の一部を表す名詞と動詞(必ずしもその動詞自体の意味が明らかではない)が対になる複合動詞である。シュメール語には、「見る」「眺める」などといった行為を一語で表す動詞がない。いずれも「目」という名詞が何らかの動詞とともに用いられて、個々の意味をなしている。
- 例:
- 「目」+「開く」=「見る」
同様に、「考える」「忘れる」などという「思考」に関する行為も、それを表す一語の動詞はなく、シュメール人が知能の在処とみなした「耳」という名詞が何らかの動詞とともに用いられる。
- 例:
- 「耳」+「動詞(意味不明)」=「忘れる」
「手」や「足」が実際に動作・行為に関わる場合は、その名詞が複合動詞の構成要素となる。
- 例:
- 「手」+「近づける」=「受け取る」
「足」+「追う」=「踏む」
感情を表す複合動詞には、「心」という名詞が含まれる。
シュメール語の複合動詞のパターンが少し見えて来たところで、問題を一つ。
問い:「心」+「つかむ」はどういう意味でしょう。
答え:「怒る」
名詞抱合との比較
複合動詞は、しかしながら、シュメール語独自のものという訳でもない。名詞と動詞が結びついて新たな動詞を作る言語学的現象は、一般的には「名詞抱合 (noun incorporation)」と呼ばれ、世界中の少なからぬ言語に見られる。例えば、かつてカリフォルニアで話されていたアメリカ・インディアンの言語の一つ、タケルマ(現在は死語)においては、「鼻」+「見つける」=「においを嗅ぐ」や「耳」+「見つける」=「聞く」、「胸」+「見つける」=「考える」のように身体の各部分を表す名詞と「見つける」という意味の動詞が結びついて、新たな動詞を形成する。オーストラリア原住民の一言語、ワルマジャリでは、「耳」+「立つ」=「聞く」という例が知られている。また、ウト・アステカ言語の一つウテでは、「手」という名詞と様々な動詞が結びついて「絞る」「こねる」「平手で打つ」などの動詞が作り出される。
ここで、名詞抱合とシュメール語の複合動詞は同じ現象かどうかという疑問が生ずる。両者は、名詞の構成要素と動詞の構成要素が結びついて、新たな意味を帯びる動詞を作るという意味論においては似ているが、統語論的には異なると、私は考えている。先述のような一般的な名詞抱合においては、名詞が新たに構成された動詞に組み入れられて、名詞自体の意味を失い、それに伴って統語論上の位置も失う。従って、タケルマの「耳」+「見つける」=「聞く」という例では、「耳」が、たとえば「良い」という形容詞を取ることはない。これに対して、シュメール語の複合動詞においては、身体の各部分を表す名詞は、いずれの場合も、動詞の目的語として絶対格を与えられていて、名詞はそれ自体の意味を失うが、統語論上は元来の絶対格の位置を保持する。この特殊性ゆえに、シュメール語の複合動詞の名詞は、時に意味論上もその独自性を取り戻し、たとえば、先述の「目」+「開く」=「見る」という例でいえば、「目」が「清らかな」あるいは「やさしい」という形容詞を取ることができるのである。すなわち、両者の違いは、名詞の構成要素が統語論上独自の位置を保持するか否かにあると言える。
今後の研究
数年前から私は、ペンシルヴァニア大学の研究者と、電子化されたシュメール語テキストにさらに形態論・統語論的分析を加えたコーパスを作るプロジェクトを進めている。シュメール語の解釈やコンピューターのプログラミングなど問題点がいろいろあって、なかなか進展しないのであるが、なるべく近いうちに、このコーパスの第一段階を完成させたい。そして、それを用いて、制約の多い古代の言語を扱いながらも、資料に裏付けされた精確な研究をし、シュメール語文法のより合理的な解釈を目指していきたいと思う。文法再構成という地味な仕事ではあるが、シュメール研究の核と自分を励まし、楔形文字文書の山の中に埋もれる毎日である。
- 唐橋 文(からはし・ふみ)/中央大学文学部准教授
専門分野 古代オリエント学 - 福島県生まれ。筑波大学比較文化学類卒業。“Sumerian Compound Verbs with Body-Part Terms” で博士号取得(シカゴ大学)。バルセローナ大学、ミシガン大学、シカゴ大学、ペンシルヴァニア大学でアッカド語とシュメール語の講師を勤め、2007年より中央大学文学部勤務(古代史担当)。専門はシュメール語文法。古代オリエントとギリシアの神話にも興味があり、東西文化交流の資料集めもしている。