 一覧
一覧

中川 洋一郎 【略歴】
教養講座
資本主義の多様性論は、負けたのか?
中川 洋一郎/中央大学経済学部教授
専門分野 フランス現代経済史
「(資本主義の多様性論は)負けたようです」(ロナルド・ドーア教授)
中央大学商学部は、今年(平成21年)、創立100周年を迎えている(商学部100周年記念ページ![]() )。その記念行事の一環として、日本の社会・経済研究において世界的に著名なロナルド・ドーア教授(ロンドン大学名誉教授)による講演が、先日(11月7日)行われた。
)。その記念行事の一環として、日本の社会・経済研究において世界的に著名なロナルド・ドーア教授(ロンドン大学名誉教授)による講演が、先日(11月7日)行われた。
ドーア教授は、「日本の近代化:戦後の民主化から構造改革まで」と題するこの講演において、資本主義にはいくつもの多様な形態があり、アングロ・サクソン型の資本主義は市場志向型だ。それに対して、日本型資本主義は、市場志向と言うよりは、「総じて言えば、組織志向だ」と語った。世界経済の発展のありさまは、あたかも一本道を全ランナーが走るマラソンレースのようであり、先頭ランナーのアングロ・サクソン型の資本主義が世界を席巻し、やがては世界中の資本主義がそれに収斂してくるという「マラソン歴史観」がある。ドーア教授は、過去の業績において、日本型資本主義の性格を明らかにし、その存在を強調することで、かかる「マラソン歴史観」に果敢に挑戦してきたのである。
しかし、1990年代のバブル崩壊以降、日本の企業を取り巻く環境は大きく変わった。「企業は誰のものか」という問いかけに対して、従業員主権から株主主権へ。成果主義という旗印の下に、経営者に厚く、一般従業員に薄い所得分配へ。業績重視という株式市場からの圧力を受けて、内部留保・研究開発費の重視から配当重視へ。すなわち、ドーア教授が見るところ、日本の資本主義は、過去20年間において、それまでの「組織志向」から、露骨に利益を追い求めるアングロ・サクソン型へ大きく舵を切った。
もし、日本型資本主義がアングロ・サクソン型にすり寄ったのだとしたら、世界にはさまざまな資本主義が存在するという「資本主義多様性論」が大きく揺らいだことになる。ドーア教授が講演の最後で、「私は一生をかけてマラソン歴史観と戦ってきましたが、どうやら負けたようです」と締めくくったのが、印象的であった。
リーマンショックで市場の欠陥が露呈した。だが、今のところ自由な市場に代わる仕組みはない。
では、「各国の資本主義はやがてアングロ・サクソン型の資本主義に収斂する」という「マラソン歴史観」は、そんなに手堅いのか。
平成20(2008)年9月に、アメリカでサブプライムローンが破綻して以降、世界中で株価や地価は低迷し、成長率も減速した。世界経済は不況に陥った。グローバルな資本主義・市場主義の欠陥が露呈した。大量の資金が世界中を駆け巡り、投機市場に費やされて、非生産的な分野に投資されている。その結果、一部の人々に巨額の収益をもたらす一方で、大量の低所得者を生んでいる。市場に対する信頼が大きく損なわれている。
では、代替案として、社会主義的な経済統制はどうか。しかし、それに纏わる悲惨な記憶がまだ生々しい。レーニンがロシアで権力を掌握したのは、1917年であった。それ以来の共産党による一党独裁体制の歴史は、人類の歴史に惨たらしい爪痕を残した。
ベルリンの壁が崩壊したのは、1989年。わずか20年前である。その後、東ヨーロッパの諸国が相継いで社会主義体制を放棄した。1991年には、ソビエト連邦自体が崩壊し、ヨーロッパでは社会主義体制はほぼ消滅した。
「おごるな、資本主義!」とか、「横暴な市場主義反対!」などのスローガンとともに、陰に陽に社会主義の復活をめざすかけ声は、これからも囁かれるであろう。しかし、少なくとも一党独裁をイメージさせるような統制経済が復活することはありえない。世界経済には、何らかの新しいルールが必要であり、やがて規制をかけるようなルールが成立するであろう。しかし、市場に代替するような少数のエリートが一元的に管理する組織・体制は、今のところ構想できない。 リーマン・ショック以降、市場がこれほど大きく揺れているのに、市場経済を廃棄して社会主義へ戻ろうという声は(少なくとも明示的には)全く聞こえてこない。一元的な統制経済ではなく、自由な市場という基本的な枠組みを維持しつつ、せいぜい規制をかけて、行き過ぎを抑えるという微調整を行ってゆくのだろう。
競争のグローバル化が続く
そうである以上、当面、競争がますます激化するほかない。競争は国内だけでなく、地球的規模で行われている。競争がグローバル化したのだから、競争相手は、国内企業だけでなく、海外企業も含まれる。国内だけを対象としてきた企業も、いつの間にか海外からの競争にさらされてしまう。
メーカーなどの生産者は、当然、自分のイニシアティブで、販売価格を決めたい。メーカー自身のイニシアティブに任されている場合、原材料費・部品費、労務費、一般経費などの総コストに、適切な利益を加算して、販売価格を決める。しかし、今や世界的規模で見て、供給過剰なのである。競争が恒常的に激化すると、値段は低下傾向になる。デフレの恐怖。生産者にとっては辛い日々が続く。
競争のない平穏な世界から、競争が支配的な世界への移行は、生産者にとって、恐ろしい事態を招来する。その商品が売れる価格、すなわち、適正な価格(と、適正な利益)は、もはや生産者が決めることはできない。生産者(メーカー)は、コストに利益を加算して、自分のイニシアティブで販売価格を決定できなくなる。誰が決めるのか。市場である。その商品が実際に売れた価格が「適正な価格」となる。
「売れた値段こそが、適正な価格だ」という考えを否定する経済学者もいるだろう。しかし、競争に揉まれてきた優秀な日本人経営者なら、首肯するに違いない。すでに30年以上も前に、大野耐一(トヨタ生産方式の創始者)が「商品の値段は生産者が決めるのではない。お客様が決める」と言っていた。かかる哲学を、現場での経験を通じて練り上げてきたのが、トヨタ生産システムである。すなわち、日本の製造業は、早くから今日のような競争のグローバル化に備えてきた。
日本の貿易構造は、耐久消費財から生産財・資本財へ
競争のグローバル化が最も顕著なのが、家電や自動車などの耐久消費財産業である。日本も、オイルショック前は、「集中豪雨的輸出」などと批判されたように、耐久消費財が代表的な輸出品目であった。耐久消費財は一般大衆を相手にするので、どうしても輸出先で目立ってしまう。
耐久消費財の生産には、たいていの場合、最終組み立て工程で大量の人手が必要である。だからこそ、低賃金国がこの分野で競争力を発揮する。しかし、単純な価格競争において日本企業が戦ってゆくことは、高賃金・高コスト体質の日本では至難の業である。低賃金諸国が続々と世界市場に参入してくる結果、雑貨などの日用品の生産では、コストの面で、中国を初めとする低賃金諸国に到底かなわなくなっている。生き残るために日本のメーカーは、日本でなければできないような高品質・高性能・高機能の商品(つまり、日本ブランド)を売り出してゆかなければならない。それこそが、高度の技術とノウハウが集約されているので、高水準の企業しか生産できない生産財・資本財(部品・材料・機械など)であった。
1973年と79年の二度にわたるオイルショックが勃発したとき、このことにいち早く気がついたのが、日本のメーカーであった。それまでの汎用品ではなく、いわば「日本ならでは」の製品をつくるために、研究・開発に力を注いだのである。
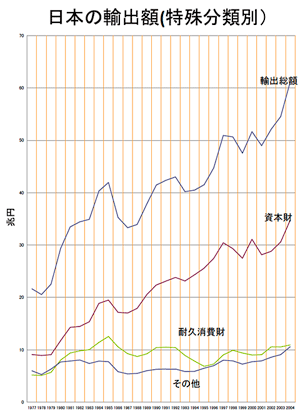
輸出額・特殊分野別(1977-2004)![]()
【出所】総務省統計局「日本の長期統計.18-1-c 輸出額-特殊分類別(昭和40年~平成16年)」
( http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/18-01-c.xls![]() )より、筆者が作成。
)より、筆者が作成。
この転換は当該企業にとっても、産業界にとっても、大きな挑戦であった。ここではその成功の理由を2つだけ挙げよう。第一が、企業内における階層間の垣根の低さである。エンジニア・テクニシャン・ワーカーに区分される職層間での軋轢が少ないために、全社を挙げて、生産製品の転換などの困難な事業ができた。第二が、協力メーカーの真摯な支援である。日本の工業界では中小メーカーで構成される幅広い裾野産業があったこと、しかも、部品や材料などを供給する協力メーカーが、「我がこと」のように捉えて全知全霊をかけて知恵を出したことが大きかった。
とどの詰まり、企業内においても、企業間においても、欧米企業であれば疎外されてしまうような周辺的なメンバーが、日本では当事者意識を持って、「我がこと」のごとく、それぞれの課題に取り組んだ。これこそ、オイルショック後、日本企業が耐久消費財から生産財・資本財へと大きく舵を切れた理由なのである。
確かに市場は、今日、ますます拡大・深化し、グローバル化している。競争も、新興諸国の参入で、激化する一方である。「アングロ・サクソン型資本主義の世界制覇完成目前」とでも言うべきか。しかし、日本企業は、グローバル化に対して、依然として日本社会の底力で対応しようとしているように見える。
ドーア先生、資本主義の多様性論、まだ負けたわけではありませんよ。
- 中川 洋一郎(なかがわ・よういちろう)/中央大学経済学部教授
専門分野 フランス現代経済史 - 1950年東京生まれ。1974年東京外国語大学外国語学部フランス語学科卒業。1976年東京大学大学院社会学研究科国際関係論専門課程修士課程修了。
1981年パリ( I )大学大学院社会経済史研究所博士課程修了(経済史学博士)。1983年東京大学大学院社会学研究科国際関係論専攻博士課程単位取得退学。
中央大学経済学部助手・助教授を経て1994年から現職。2005年11月より2009年4月まで入学センター所長、2008年12月より副学長となり、現在に至る。
主要な研究領域は,フランス現代金融史、日仏自動車産業史、左翼全体主義。現在の研究課題は、(1)日本型システムが欧米の産業システムに与えた影響(いわゆるジャパナイゼーション)、 (2)左翼全体主義の生成・展開・崩壊におけるフランスの役割。なお、台湾で李登輝氏総統就任後、「日本語族」の魂の叫びに大いに共感、サイド・テーマとして「日本の鏡・台湾」。
主要著書に、『フランス金融史研究』(中央大学出版部、1993年)、『ヨーロッパ《普遍》文明の世界制覇』(学文社、2003年)など。








