 一覧
一覧

和田 光平 【略歴】
待ったなし! 人口減少
和田 光平/中央大学経済学部教授
専門分野 人口統計学、応用人口学
人口減少社会の到来
先日、国勢調査の速報値が公表されました。これまでのような右肩上がりの増加もなくほぼ横ばい状態でしたが、大きなトレンドとしての人口減少が目前にあることは示唆されました。このように少子高齢化や人口減少という言葉をよく見聞きしますが、皆さんは日本の人口の将来についてどのようなイメージをお持ちですか。次の図は西暦1年から2105年までのわが国の人口を示したものです。2005年から2105年までの推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によるものです。高度経済成長期に急増していた人口が、今世紀初め頃からは一転急落すること予想されます。いま私たちはこの山頂に立っているわけです。
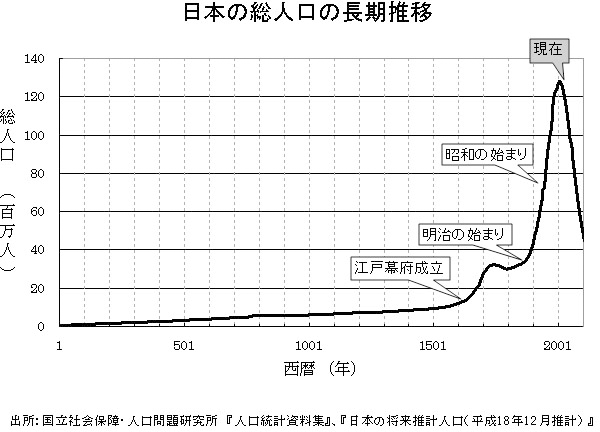
日本の人口、絶滅の危機
1世代分の時間を人口統計学では安定人口平均世代間隔と言い、正確には30.17年(2005年時点)と推定されますので、3世代では30.17×3=90.51年です。国勢調査によると2005年の総人口は127,767,994人で、先ほどの将来推計人口によれば2096年の総人口は50,449,303人ですから約60.5%の減少となります。なぜこのような計算結果を持ち出したかといえば、やや卑近な例ですが、この場合、環境省のレッドデータブックのカテゴリーでは、ゼニガタアザラシ、クマタカ、アカウミガメなどが該当する絶滅危惧ⅠB類(近い将来、絶滅の危険性が高い種)の要件「今後10年間もしくは3世代のどちらか長い期間を通じて、50%以上の減少があると予測される」に相当します。さらにこの先を推計しても当てにはならないかもしれませんが、仮に出生率も死亡率も不変で、移民も無いとした場合、西暦3000年までには1000人を切るという試算もあります。民族と生物種を同列に比較したり、1000年近く仮定値を固定して推計したりというのは少し乱暴な議論かもしれませんが、世界最速と懸念されるわが国の人口減少が実感されたのではないでしょうか。
30年以上前の予言
人口の動きは、株価や為替経済の動きと比べてもはるかに高精度な予測が可能です。しかも長期的な予測が得意です。定義上、人口減少の始期を特定することは難しいのですが、いま現在その転換期にあることは間違いありません。ところが実は、1970年代半ばにはすでに人口減少の前兆があったのです。「人口置換水準」という1つの基準があります。合計特殊出生率と呼ばれる出生率の水準がこの置換水準を超えていれば人口は長期的に増加し続け、下回れば減少します。日本の場合およそ2.07と推定されるこの水準を切ったのが1974年(2.05)であり、それ以降も下回り続けました。いわゆる少子化もここから始まったとされます。もちろん総人口はすぐに減り始めるわけではありません。一種の惰性が働き、先述の安定人口平均世代間隔のおよそ30年を経てから総人口の動きとしてようやく表れるのです。逆に言えば、仮にいますぐに出生率が人口置換水準まで回復しても、人口増加にはその後30余年かかるでしょう。少子化対策が望まれる昨今ですが、その効果が数十年先にしか表れないものに政策の優先順位は低くなりがちです。国の財政も厳しく、いまの深刻な不況対策のために使うのか、将来の子や孫といった次世代のために少子化対策に使うのか決断しがたいところですが、今まさに少子化対策に着手しなければわが国の将来は非常に危うくなります。
出生率を上げるために
人口減少を食い止めるためには、やはり出生率を上昇させなければなりません。つまり少子化の克服です。他の国々の例をみてみましょう。よく引き合いに出されるフランスですが、この国ではとりわけ出生率を上げるための家族政策が伝統的に実施されてきました。第2子以降には所得制限なく給付される高額な家族手当やベビーシッターのための補助金、子どもが多いほど有利な課税方式などが挙げられます。また北欧諸国は、女性が働きながら出産もできる環境を整えることで高水準の出生率を維持しています。アメリカやオーストラリアでは移民を多く受け入れて総人口自体も増加させるとともに、またその移民が積極的な出生行動を取っています。そこでわが国はどのようにすべきでしょうか。近年、子ども手当が注目されていますが、やはり財源面から潤沢には支給できません。ワークライフバランスもこの不況では、企業の現場では難しいようです。ましてや移民受け入れなどは議論さえタブー視されているのではないでしょうか。そこで私が、日本独自あるいは広く東アジア的視点から勧めたい出生率上昇の方策としては、親族や地域コミュニティの力を強めることです。都道府県別で最も出生率の高い沖縄県を調査した際、「ゆいまーる」という相互扶助の精神を知りました。また市区町村別で出生率が全国上位3位(2003-07年平均)を占める鹿児島県徳之島の3町にも「くゎーどぅ宝」、子どもはみんなの財産として地域みんなで育てましょうという考え方が浸透しています。子どもは大人になればその国全体に利益をもたらすにもかかわらず、現在の育児は、まだ若い親という個人へ負担が押し付けられています。親族や地域のコミュニティが育児に積極的にかかわり、地域社会全体で子どもを育てられるような雰囲気づくり、すなわち、個人ベースから社会ベースへと、育児環境の転換が必要であると言えます。
- 和田 光平(わだ・こうへい)/中央大学経済学部教授
専門分野 人口統計学、応用人口学 - 宮城県出身。1969年生まれ。1991年中央大学商学部卒業。1993年中央大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。1997年同博士後期課程中退。中央大学経済学部助手・助教授を経て2006年より現職。オーストラリア国立大学人口研究所客員研究員(2008-2010年)。内閣府(少子化問題担当)や財務省などで人口問題関係の研究会委員を、また国際人口学会で高齢化部会委員などを歴任。
- 現在の研究課題は、人口および世帯の推計、ならびに人口統計の地域経済分析やマーケティングへの応用などです。また、主要単著書に『Excelで学ぶ人口統計学』(オーム社、2006年、日本人口学会普及奨励賞ならびに中央大学学術研究奨励賞受賞)、共著に『人口減・少子化社会の未来』(2007年、明石書店)、『人口減少時代の日本経済』(2006年、原書房)、『少子化と日本経済』(2006年、日本評論社)など多数あります。








