トップ>HAKUMON Chuo【2015年冬号】>【表紙の人】中央大学ボランティアセンター
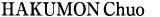 一覧
一覧
【表紙の人】中央大学ボランティアセンター

行動の意味 常に問いながら
越智つぐみさん(文3)
虫の目 女川で1ヵ月フル活動
東日本大震災(2011・3・11)の発生から、来春で5年を迎える。大きな被害を受けた宮城県女川町でこの夏1カ月、中央大学ボランティアセンターの一員として、文学部3年の越智つぐみさんがフル活動した。子供たちと触れ合い、地元に解け合った。
彼女が「虫の目」で見た現地をリポートする。
あの日からずっと…

「あの大震災は、決して過去の話ではない」
女川町に滞在した私が最初に感じたことだ。強い日差しが降り注ぐ8月下旬、現地の子供のための放課後学校「女川向学館」へ赴いた。
同校の運営は認定NPO(民間非営利団体)法人カタリバで、カタリバが目指すコラボ・スクール(別掲)だ。
1カ月間、ボランティアとして子供たちと関わった。彼ら彼女らとの出会いが教えてくれたことは数知れない。子供の背中越しに見える女川町の現状。ここでは子供たちの居場所が少ないという問題。私たちボランティアとしてのあり方…。数多くの問題に直面するたび、東京との隔たりを肌で感じた。
「もう4年経つんだね」。東京で耳にした声が妙に心に残っている。復興イベントに訪れた人がふと漏らした何気ない一言。現地を一時離れても、私の気持ちは女川町にある。
女川町には新入生対象の「スタディーツアー」(主催・中大ボランティアセンター)などで数回訪問している。帰京後も現地の今を伝える写真展や物産展などの手伝いをしてきた。「もう4年」の “ もう ” という言い方が、震災の風化を如実に表した。愕然(がくぜん)とする温度差を感じた。
常識を根底から覆した、あの大きな震災を置き去りにすることはできない。向学館の職員は、子供たちが徐々に元気で健康に戻る体と心に寄り添い、放課後の居場所として、どうあるべきかを日々考えている。
子供たちは、はっきりとは口にしないが、大震災による痛みを胸に抱えている。町の方々は、あまりにも多くのものを一度に失ってからというもの、目の前に突きつけられた厳しい現実と格闘し続けている。想像すらしなかった暮らしや時間が、あの日から刻一刻と流れ出した。
向学館でのある一日

女川向学館で小学生の話を聴く越智さん
午後4時過ぎの女川町。小学校で授業が終わるころ。私は向学館職員室で準備をしていた。プリントを印刷したり、その日取り組む問題を解いたり、慌ただしく動き回っていると窓の外が騒がしくなってきた。小学生たちがやってきた。
町の小・中学生の多くは、学校で授業を終えると向学館のバスに乗って移動する。町の中には、かさ上げ工事や道路建設工事などで、四六時中、大型トラックが走っている。子供が工事現場周辺を歩くのは危険だ。向学館からは遠方に位置する仮設住宅などで暮らす子供も多い。
小学生の到着確認後、教材を持って6年生のクラスへと急ぐ。始業前、男の子たちは新聞紙を細長く巻いてチャンバラごっこをしている。(相変わらず、きょうも元気だな)。そう独りごつ。ふと窓際の席に目をやると、女の子が机に座って静かに読書をしている。
チャイムが鳴り、先生が教室に入ってきた。私は “サポートの先生”。男の子たちは、まだ遊び足りないのか席に着くのを拒む。先生がピシャリと叱る。ようやく始まった。
先生が十数人のクラスを学力別に2つに分けた。私はその一方の指導にあたる。生徒はプリントされた問題に取り組む。すぐ、方々から「先生!」と私を呼ぶ声が相次ぐ。席に寄って一人に教えている最中、今度は問題に行き詰まった子供から「ねぇ」と服の袖を引っ張られる。
再びチャイムが鳴り、終わりを告げた。帰宅する彼らを玄関で見送って職員室へ。次の準備をまた始める。
午後6時前。中学生が到着する時刻が近づいた。授業補助とは別に、私には彼らに1個100円のおにぎりを用意する仕事もある。顔を覚えるため、おにぎりを手渡す際にちらっと見る。おにぎりはわずか数分で完売した。
中学生の授業が始まった。この日は小学生のときと同様に、クラス分けされたグループの一方を教えた。グループの中にも学力差は存在する。私は、どちらかというと勉強が苦手な生徒を構いがちになってしまう。
授業が終わっても、ほっと一息ついている暇はない。教室の生徒を速やかにバスに乗るよう促す。スタッフとともにバス乗降場の駐車場へ駆け足だ。ステップを踏んでバスに乗り込み、生徒名簿を手に点呼をとる。全員乗車を確認、運転手にそう伝えるとバスは発車した。乗客となった中学生に手を振る。しかし、おしゃべりしたり、携帯電話の画面を見たり、めったにこちらを振り向かない。
こうして生徒を送り出し、職員室に戻る。この日を振り返り、翌日の準備などをすませ、一日の業務が終わる。
ボランティアをするということ
ボランティアとして向学館へ赴いてから去るまで、常に頭を悩ませた問題がある。子供たちとの「距離感」である。
「先生、おとなしいね」。ボランティア1週目、女子中学生にこう言われた。向学館には2011年7月の設立後、多くのボランティアやインターン生が関わってきた。生徒たちも多くの先生と接してきた。
(私はおとなしい…)
子供たちにもっと近づけということなのか。初めて接したとき、ぎこちない態度になっていた。子供たちの輪に入っていけない。すぐ近くでは、ほかのインターン・ボランティア生が楽しそうに生徒と話をしている。私は茫然(ぼうぜん)と立ちすくんでいた。
2週目になると徐々に彼らと打ち解けた。子供たちはよく甘えてくる。難解な問題に出くわすと、すぐに「先生、わかんなーい」と言ってくる。解答をあえて遠ざけ、生徒が自分で考え、自ら答えを出せるようなヒントや考え方を伝える。
ひらめいて解答した生徒がいる一方で、「もう疲れた」と思考停止したかに見える生徒もいる。
私は戸惑った。そうした「甘え」をいつも受け止めていては、子供たちのためにならない。ボランティアとしてのあり方が問われた気がした。
私がここにいる意味とは何なのか。子供にべったり寄り添っていては、私が去ったあと、寂しがらせてしまう。
子供たちの心に勇気を持って踏み込まなければ、彼ら彼女らのことは何も知ることができない。
子供も、私が来た意味を疑い出すだろう。限られた時間の中で、ボランティアとして彼ら彼女らに何を残せるか。その答えが見つからないまま、悶々とした日々が続いた。
それでも、自分にできることは全力で取り組んだ。1カ月はあっという間に終わった。

3月21日、大漁旗の出迎えを受け女川駅に入る列車

石巻線が全線開通し、臨時列車を見送る地元の子供たち
今後の目標

ボランティアの存在意義を向学館で感じた。これまで関わってきた私のボランティア活動にも通ずる部分がある。
自分では一生懸命に取り組んでいるつもりでも、必ずしも現地のためになっているとは限らない。時間が経過し、状況が変われば、人々が求めるものも形を変えてゆく。
精力的な活動をする一方で、客観的な視点でその時々の自らの行動を振り返っていく必要がある。
環境や状況の変化に伴って変わりゆく人々が、その都度求めるものを敏感に感じ取る柔軟性。自分の行動の意味を常に問う慎重性。これは今後ボランティアをする上で大切にしたいことである。
私はこれからもボランティア活動を続けていく。
鳥の目
この夏、中央大学ボランティアセンターを通じて学生75人が東北被災地支援ボランティアを行った。
活動地は岩手・宮城で13カ所。活動内容はさまざまだ。ある学生は仮設住宅で高齢者の話に耳を傾け、ある学生は子供たちと走り回った。漁師とともに漁具を修理した学生もいれば、畑で桑の収穫作業を手伝った学生もいた。
震災からもうすぐ5年が経つ。初めて被災地を訪れた学生は、広大な更地を目にして「復興していない」と驚いた。何年か通っている学生は、工事の音に復興の兆しを感じつつも、なじみの人たちの暮らしを考えると、「この夏もまだ先が見えない」と胸を痛めていた。
「被災地」へ足を運びボランティアをしてみれば、地域それぞれ、人それぞれに、個別の問題を抱えていることが分かる。どの学生も「少しでも役に立ちたい」と、地域の人たちの気持ちに寄り添おうと一生懸命だった。
それまで漠然と「被災地」と呼んでいた場所は「お世話になった○○さんが暮らす町」に変わり、「被災者」は「自分と笑い合った○○さん」となった。
地域の人からの「ありがとう」「また来てね」「勉強がんばれよ」という温かい言葉と、本当は心の内に『3・11』から変わることのない痛みがあり、希望を持ち続けようと闘う姿に、「ボランティアをしに行ったけれど現地からいただくものの方が多かった」と、学生たちは涙していた。
ことしの夏も、学生はかけがえのない体験と学びをいただいた。地域の皆様には本当に感謝している。
(中央大学ボランティアセンター 松本真理子)
もっと知りたい へぇ~
「女川向学館」などのコラボ・スクールは、認定NPO法人カタリバ(本部・東京都杉並区)が運営する東日本大震災復興支援の一つで、子供たちのための放課後学校。2011年7月から始まった。津波で家が流され、手狭な仮設住宅などで暮らす小・中学生や高校生約300人に、落ち着いた場所での学習指導と心のケアなどを行っている。同団体は2001年の設立以来、主に高校生へのキャリア教育を行ってきた。(HPなどから)
東日本大震災は、被災地・宮城県女川町にも人口変動をもたらした。震災前の2011年2月末の人口は1万16人、世帯数は3852 だった。2015年10月末では人口6911人、世帯数3165 と減少した。女川町のHPには「とりもどそう 笑顔あふれる 女川町」とある。(HPから)








