トップ>HAKUMON Chuo【2013年夏号】>【特集】ボランティアなう ボランティアを一人でも多く増やしたい
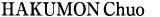 一覧
一覧
【特集】ボランティアなう
ボランティアを一人でも多く増やしたい
~中大初のボランティアコーディネーター、松本真理子さん~

松本 真理子氏 【略歴】
ボランティアをしたい学生の支援窓口として「中央大学ボランティアステーション」が4月1日に設立された。同所の“顔”となるボランティアコーディネーターに経験豊かな松本真理子さんが着任し、5月の東日本大震災・被災地ツアーでは大震災を風化させないと尽力した。
文&写真 学生記者 澤田紫門(総合政策学部2年)
ボランティアコーディネーターとは、どのような仕事をするのか。
「学生が何か社会に貢献できるような活動をしたいと強く望みながらも、何から始めてよいのか、どうやってボランティアに参加すればいいのかが分からないという学生たちと、学生の手を必要としている地域を結び付けます」
松本さんの回答は明解だった。
「ボランティア団体のカタログを見せるだけではなく、学生の話に耳を傾け、彼ら彼女らに合ったボランティアを一緒に探したい」
“一緒に”という言葉に力が入った。
学生経験を原動力に
中大着任前は、震災後、宮城県女川町に開校された、子どもたちの学習指導と心のケアを行う「女川向学館」で復興支援をしていた。女川は津波で壊滅的な被害を受けた町。向学館は、NPO(非営利組織)「カタリバ」が寄付を集めて地域と協働で運営する、被災地の子どもを支える活動だ。ここでは地域コーディネーターとして、刻々と変わる被災地のニーズを拾い、支援活動を適切なものに調整する役を務めた。
明治大学の学生だったころは、現在のイメージの行動派というタイプではなく、勉学に励むのみだった。「このまま何もしないでいるのはもったいない」。モヤモヤとしていた自分を奮い立たせ、大学の外の世界へ飛び込んだ。
最初の一歩は、毎日新聞で学生が作る紙面『キャンパる』での活動だった。記者ではなく挿絵志望で入ったものの、突如取材を命じられた。初めて書いた記事は読者から反響があった。未知の世界に飛び込んでいくことは面白い。興味が広がり、様々なことに挑戦するようになった。

そして、友人たちとNPOを立ち上げた。高校生が主体的に自分の進路を選ぶきっかけを提供する団体だ。これが初めてのボランティアとなる。「一人ひとりが変われば社会は変わる。新しい世の中をつくっていこう、と思っていました」
しかし世間のNPOやボランティアへの理解度は低く、「NPO? なにそれ?」と門前払いされることも。「新しいことがすぐに受け入れられないのは当たり前。そうした社会の壁にぶつかる経験をして、初めて大人になれるんだと思います」
この時点で将来ボランティアに携わりたいと明確に思ったわけではない。
「大学生活4年間は、それまでの18年間よりも、多様な人と出会いました。就職活動をしながら考えたことは、目の前の人のやりたいと思っていることを応援したいということだけでした」
それに一番近いと思い、「社会教育主事」の資格を取得し、卒業後は千葉県の公民館に勤務、町づくりの仕事に携わった。
その後、地域コミュニティ紙「船橋よみうり」(発行部数約12万5000部)で記者を5年間勤め、我が街を良くしようと取り組む地域の人々を伝え続けた。
あの忌まわしい「3.11」が起こる。町が根こそぎなくなるようなこの出来事に心を揺さぶられて思った。「町の再生に携わりたい」。10月には女川にいて、NPOカタリバのコラボ・スクールに本格的に取り組んだ。
昨年初冬、友人が「中大でボランティアコーディネーターの仕事があるみたい」と連絡をくれた。
中大入りには考えることが多かったという。被災地にいて感じたのは、忘れ去られる危機感。東京発信の被災地報道の量は減り、原発や悲惨な出来事に限り大きく扱われる。現場レベルでも、ボランティア志願者と被災地のニーズがかみ合わない現状も新たな課題になっていた。被災地の“今”が東京に伝わっていないと痛感した。
東京へ行って、被災地の現状に詳しい私がパイプ役となり、いま求められるボランティア活動への理解を深めよう。
ここで決定打となったのは、大学生時代に感じたあの「モヤモヤ」だ。学生のころ、彼女自身も「このまま何もせず終わっていいのだろうか?」という焦燥感、「何か自分にできることはないか?」という情熱を抱いていた。同じような思いを持つ学生の背中を押し、一歩踏み出すための手助けをしたいと思い至ったという。
「ボランティアは、相手との人間関係や社会の課題や矛盾など、簡単には解決できない問題が周辺に転がっています。くじけそうになるときもあると思いますが、学生たちには、そうした現実に向き合うことで少しでも成長してもらいたい。それが自分と社会の未来をつくることになり、本物のボランティアになっていくと思います」
学生の熱意を東北の被災地に繋げる仕事がしたいという思いが、ボランティアコーディネーターにつながった。
きっかけづくり
NPOは人気ランキング第3位
米国の文系大学生の人気就職先は
①ウォルト・ディズニー・カンパニー②国連本部③NPO④Google⑤国務省。
※NHK番組から
装いも新たにした中大ボランティア活動には、Facebookによる情報交流で800人以上(6月現在)が関心を示している。八王子や日野の社会福祉協議会と連携し地域のボランティア活動情報を呼びかけ、5月には被災地スタディーツアーを行った。
「社会に出てすぐに役立つぐらいに自分の力を高めるには、どんどん社会に出ていく必要があります。その“きっかけ”をたくさん作りたいと思っています。目標はシンプルにこれだけです」
中大唯一のボランティアコーディネーター・松本真理子さんが語る、学生への熱き思いとボランティアに対する造詣の深さは、「話題の嵐」を巻き起こすほどの潜在力を持っている。
- 松本 真理子氏(まつもと・まりこ)
- 1981年9月26日、千葉県船橋市出身。県立船橋東高―明治大学政治経済学部卒。2人姉妹の長女。「宿題は最初に終わらせるタイプ」という。
-
被災地スタディーツアー in 宮城県女川町

高台から見た女川の町
あの日から2年半が経とうとしています。「もうボランティアにはやれることはない」と考える人も少なくないように感じます。しかし、そうではないことを一人でも多くの学生に気付いてもらうため、5月24~26日、宮城県女川町への「被災地スタディーツアー」を行い、まだ被災地に行ったことのない1年生25人を連れていきました。
女川町は人口の1割を失い、8割の建物が壊れ、被害率は被災地内最大です。高台から町を見下ろ すと更地が広がっています。そこにかつて人々の営みがあったこと、3.11に起きたこと、これからどう復興するのかを想像することは容易ではありません。
そこで、町の人々に話を聞きました。女川町の木「桜」を植樹し魅力ある町に復活させようという「女川桜守りの会」のメンバー、仮設商店街の店主、震災後に東京から戻ってきて復興に携わる20代、津波に流されたけれど助かった人、町のために役に立ちたいと話す高校生など、年齢も立場もさまざまでした。
「この店が、町、東北、日本、世界を照らす灯台になるようにしたい」
「みなさんには同じ悲しみを味わってほしくない。私の被災経験を役立ててほしい」
「女川に来てくれることがありがたい。復興を見届けてほしい」町の人は、身近な人を亡くした悲しみを知り、窮屈な仮設住宅の暮らしに耐え、命の岐路に立たされた経験をしています。しかし、それに負けずに新しい町への夢を語り、震災の教訓を生かしてほしいと全力で伝えてくれました。
そうした女川の人々から、学生は多くのことを学びました。
「誰もが被災者になりうると気付いた」
「女川の人に負けないように、自分たちもがんばりたい」
「女川へ行く前は被災地を特別視し、困っている人に奉仕することがボランティアだと思っていたけれど、そうではない。共に在ることが大事だ」そして自分たちが今できることを、それぞれに真剣に考え動き始めています。
「できることから始めてみる」というボランティアの基本姿勢を、女川の人たちから教えていただいた旅となりました。
多忙ななか、本学学生のために時間を割いてくださった、温かな女川のみなさまに心から感謝します。

被災地スタディーツアーに参加した学生と「女川桜守りの会」のみなさん(左側に松本コーディネーター)
ボランティアコーディネーター 松本真理子
(写真提供=中央大学ボランティアステーション)








