トップ>HAKUMON Chuo【2013年早春号】>【陸上競技部 駅伝チーム】箱根駅伝【学生記者現場レポート】たすきが軽くなる日
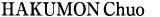 一覧
一覧
陸上競技部 駅伝チーム
箱根駅伝【学生記者現場レポート】
たすきが軽くなる日
田中 未来/中大文学部1年

「パン」という心地よいスタートの合図とともに、選手が走りだした。ことしも東京・大手町にはたくさんの人が詰め掛けた。強風の音すらかき消すような観衆の熱気。色とりどりの大学カラーの応援旗が沿道をにぎやかに飾る。今や正月の風物詩としても名高い箱根駅伝。今回のテレビ視聴率は歴代3位の28.5%を記録した。
最もつらいとされる往路5区、日体大・服部選手、早大・山本選手。少し遅れて東洋大・定方選手が熾烈な首位争いを繰り広げていた。
私は体に電流が走ったような衝撃を感じた。大げさではなく、沿道にこだまする歓声が、何も聞こえなくなったのだ。この日のために買った新品のデジタルカメラには、結局手をかけることすら出来なかった。
一瞬のことだったが、走って行った選手の息遣いや地面を力強く踏み付ける足の音は、今でも鮮明に響いてくる。
印象深いのはその“顔”だ。歯を食いしばり、悲痛な表情。しかし目は力強く前を見据えていた。なるほど、この“顔”を見てしまうから、人は箱根駅伝に夢中になってしまうのか。
追う者、追われる者の顔。テレビで見ているだけだと、それは必死に走っている顔に過ぎないかもしれない。沿道から間近にその顔を見てしまうとハッとさせられる。たくさんの重圧やプレッシャーを重い荷物のように背負って走っている、と気づかされてしまうのだ。
それなのに、あんなにも軽々と走ることができるのは、きっと待っていてくれる人がいるからなのだろう。誰かのためにまっすぐ走っている姿は、こんなにも人の心を揺さぶるのか。
2区で不調だった新庄選手も、きっとあのとき背負っているものの重さに苦しんでいたことだろう。エース区間を走ること、そして中大の伝統を守ること。何度も足が止まりそうになったはずだ。“自分を待ってくれる人にたすきをつなぐ”その一心で走っていたと思う。

その姿を駅伝を強くする会のバスのテレビで見ていた。車内からざわめきが聞こえた。「新庄が…」そんな声が口々に漏れる。よろめきながら走る新庄選手を、私は何かが胸に突き刺さった思いで見ていた。もう走る力はほとんど残っていないはずなのに、何かに憑き動かされているように死に物狂いで走る姿が今も忘れられない。
たすきを3区の選手に渡したそのとき、称賛ではない声が上がったかもしれない。下位に落ちたことに変わりはなかった。しかしほとんど倒れ込むようにして、たすきを渡した姿は駅伝に懸けるまっすぐな執念であったと思う。
そんな執念を、私は持っているのだろうか。彼の走りを見て、そんなふうに思った。
たすきは4区を最後に繋がれることはなかった。しかしそのたすきの重さこそが明日の中大を強くするだろう。そしてうそのようにたすきが軽くなる日が来るはずだ。
それはあのときの悔しさを忘れたからではなく、伝統の重みが消えたからでもない。選手がその重みに耐えうるくらい強くなったとき、たすきを軽く感じることができるだろう。
今回の敗北が中大の新たな伝統をつくるきっかけとなった。中大の一員として、はたまた駅伝ファンとして、今後が楽しみでならない。
チーム再建のいい機会だ

学生記者の取材を受ける鈴木会長
中大駅伝チームの支援団体、「中央大学箱根駅伝を強くする会」(鈴木修会長=スズキ株式会社取締役会長)では、今回の箱根駅伝でも恒例の応援バスを仕立てた。レース後は都内で選手たちを慰労し、激励した。OBOGらの声を集めた。(順不同、敬称略)
鈴木修会長 「過去を振り返るよりも、事実を受けとめ、これからどうしていくか考えるほうがいい」
中村重郎さん 「チームを立て直すいい機会だ。落ちるところまで落ちて、初めて気付くこともあるだろう」
須藤菊乃さん 「新たな気持ちでアクシデントをいい方向へもっていってほしい」
佐々木伎予子さん 「復路は1年生に走らせたほうがいいという意見もあったようですが、やはり当初のメンバーでよかった。記録は残らなくても、みんなの記憶には残るでしょう」
清水康弘さん 「悔しい気持ちを来年にぶつけて、新しい中大の伝統をつくってほしい」
松浦靖さん 「私たちも大変つらいが、歯を食いしばって懸命に応援します」
朝倉博さん 「この悔しさをバネに来年は今以上に頑張ってほしい。われわれは勝ち負けで応援はしない」
渡辺辰彦さん 「伝統があるから壁にぶつかる。逃げ出さずに、乗り越えたら、さらにステップアップできるはずです」
※ほか多数の方々からコメントをいただきました。取材協力に感謝します。








