トップ>Hakumonちゅうおう【2010年125周年記念号】>【創立125周年を迎えて】特別講演 ~時代が永遠の命を与えた“奇跡の歌”~
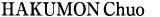 一覧
一覧
【創立125周年を迎えて】特別講演
本学OB・ジャーナリスト 門田隆将氏が語る大先輩・藤江英輔氏と『惜別の歌』
~時代が永遠の命を与えた“奇跡の歌”~
講演会では、藤江英輔氏に先立ち、本学OBのジャーナリスト、門田隆将氏に講演をしていただいた。ベストセラーの著書『康子十九歳 戦渦の日記』(文藝春秋)で、藤江氏に取材し、『惜別の歌』が生まれたいきさつを書いた門田氏は、講演で、『惜別の歌』は「時代が永遠の命を与えた“奇跡の歌”です」と強調した。(編集室)
中大、新潮社の大先輩

門田隆将(かどた・りゅうしょう)氏
ご紹介にあずかりました、門田隆将です。こんにちは。母校に呼んでいただき、非常に感激しています。きょう、講演される藤江英輔さんは、私にとっては大学の先輩のみならず、新潮社という出版社の大先輩、あまりに年が違いすぎて、「先輩」というのも申しわけないのですが、『週刊新潮』編集部の大先輩という関係でもあります。
そして去年、『康子十九歳 戦渦の日記』という本を僕が文藝春秋から出した際、藤江さんに取材で大変お世話になりました。大学、会社、そして私がジャーナリストとして世に問う作品に至るまでお世話になった、そういう関係でございます。きょうは、その藤江さんの講演が大学であるということで、はせ参じたわけでございます。
私が新潮社に入社したのが昭和58年ですが、入社したときに、「中央大学から新潮社に入ったのは、君が戦後2人目だ」と言われました。1人目が藤江さんでした。新潮社は私が入った頃、指定校制度があり、旧帝大系、早稲田、慶應、あるいは一橋とか、そういう大学を指定校にしていましたが、中央大学にはそれまで門戸が開かれていなかったのが、私が入社した年に開かれ、その第1号が私でした。
当時、藤江さんは広告部長をされていて、僕と社内で一緒に仕事をすることはなかったのですが、陸軍造兵廠のお話を藤江さんに伺いに、お邪魔したときに、「ああ、君か」ということで、会社の後輩のみならず、大学の後輩であるということで、本当にいろいろな話をしていただきました。
学問の場から命のやりとりへ
『康子十九歳 戦渦の日記』というのは、昭和19年から20年の話です。この昭和19年から20年というのは、日本の歴史の中で若者が最も大きな悲劇の渦の中に巻き込まれた2年間だったと思います。今も私は連日、太平洋戦争生還者の証言ということで全国を飛び回って、もう90歳を過ぎた方、90歳に近い方もいらっしゃいますが、大正生まれの元兵士の方々のお話に耳を傾けています。
この方々の受けた悲劇というのは、私たちの想像をはるかに超えています。とくに学問の場にいて、そこから戦場に行った人たち、私は次の作品でもそういう作品を書くのですが、『康子十九歳 戦渦の日記』を書かせてもらったときも、当時の若者の心情、時代というものを描きたいと思い、藤江さんのところに取材に行ったわけです。
戦後生まれの方は、僕も含めて、やはり文献でしか当時の悲劇がわからないのですが、とくに昭和19年から20年にかけて戦場に向かうというのは、イコール「死」を表しています。昭和12年に始まった日中戦争と、昭和16年以降の、とくに19年、20年の太平洋戦争とでは、全く意味が違います。もちろん、支那派遣軍も大変な苦労をし、多くの戦死者を出していますが、太平洋戦争は、これはもう半端なものではありません。戦場に行くということは、そのまま死を表す時代でした。
そのときに、若者はどういう気持ちでペンを銃に持ち替えたのか。学問をする、本を読む、友達と議論をする、そういう大学というものと離れ、自分が命のやりとりをしに行く。「命のやりとり」というのは究極の戦いです。命のやりとりの場に、学問の場からいきなり行かざるを得なくなった人たちが現実にたくさんいらっしゃいました。
中大予科の藤江さんを取材
藤江さんの代は、勤労動員によって、陸軍造兵廠で高射砲の弾をつくっていたわけです。その中にも、年齢がきて、召集令状によって戦場に次々と赴いて行く仲間が出てきたわけです。そのときに藤江さんは、陸軍造兵廠の中で、その召集令状を仲間に配る役割を負っていました。
私が『康子十九歳 戦渦の日記』で描こうとしたのは、東京女高師(現・お茶の水女子大学)専攻科の粟屋康子さんという女性で、この人の残した日記です。これはものすごく内容の深い美しい日記で、その中に登場してくるのが中大の予科の学生の名前だったのです。そこには梁敬宣さんという台湾からきた方、そして、後に三菱地所の社長・会長を務められた高木丈太郎さん、そういった方の名前が出てきます。
そして私は必然的に、この当時の中央大学予科の人に取材させてもらうことになったのですが、そのときに新潮社の先輩でもある藤江さんのところに、『惜別の歌』についてお話を伺いに行きました。
『惜別の歌』というのは、皆さん、中央大学の方なのでご存じの方が多いと思います。これは島崎藤村の『高楼』という詩、嫁いで行くお姉さんと、その妹との間の対詠の形式を取った詩です。この詩をもとに、藤江さんがメロディーをつけ、『惜別の歌』をつくられたわけです。
「諦観」を意識していた若者

大先輩の藤江氏について語る門田氏
私は当時の若者は「諦観」を持っていたのではないか、と思っています。
「諦観」というと諦めのようなイメージを持つかもしれませんが、当時の若者の「諦観」というのは諦めではないのです。これは「生きることの意味を突き詰める」という意味の仏教用語です。私は当時、戦場に向かう若者は、この「諦観」というものをすごく意識していたのではないかと思います。学問の場から死ぬことを意味する戦場に行くということは、国のために殉じなければいけないという使命感もあったと思います。しかし、「国のため」というそんな大きな概念だけではなかった。やはり家族というものが基にあり、そして友というものもあったと思います。文学青年だった藤江さんは、その気持ちが非常に強い青年だったと、僕はお話を伺いながら思いました。
送り出すときに、番茶1杯で、「じゃあな」と言って永遠の別れになることを、藤江さんはよしとせず、『惜別の歌』というこの歌をつくりました。そこには藤江さんの心情がすべて表れています。
女高師出身の先生が歌う
僕は、この『惜別の歌』は奇跡の歌だと思っています。それはなぜかというと、藤江さんは陸軍造兵廠の十条工場の第六区隊というところにおられました。私が書いた粟屋康子さんというのは第四区隊です。藤江さんは、粟屋さんとは区隊は違いますが、藤江さんの第六区隊にも東京女高師の人がいるわけです。この陸軍造兵廠には勤労動員してきた他の大学、他の予科の人もいるのですが、基本的に中大予科と東京女高師が中心でした。
それぞれの区隊で交流がありまして、そこで、藤江さんのつくられた名曲は、口ずさまれることによって、だんだん広まっていくのです。友達を送り出すときに、涙を流しながら歌った歌というのは、これは気持ちに残ります。その気持ちに残ったメロディーというのは、離そうとしても離れません。
東京女高師というのは女子高等師範学校です。すなわち学校教育に携わる女性の教師を育成するのが東京女高師です。戦後、女高師の生徒たちは、大学を卒業した後、全国の教育の場に散らばっていきました。学校というのは出会いと別れの場です。卒業式のときになると、その女高師出身の先生方が、この歌を自分の教え子に向かって歌い、別れを惜しむようになります。
口伝えで全国に広まる
そうすると、歌ってもらった生徒の心にも残ります。次第に全国にこの歌が広まっていきました。これは、藤江さんとともに一生懸命、造兵廠で武器・弾薬をつくった、そこに勤労動員された女子生徒、後に学校現場でものを教えていく先生となる人たちが口伝えで全国に広めていったものです。今の流行歌とはまったく違う経緯で、この歌は全国に広まっていきました。そして、その歌を生んだ、藤江英輔さんを擁する中央大学では、第2学生歌として広まっていきました。
皆さんは、小林旭の『惜別の歌』という流行歌としてご存じの方が多いと思います。それは口伝えで広まっていった『惜別の歌』が、当時、はやり始めた歌声喫茶のヒット曲となり、そしてレコード会社の耳に入り、レコーディングに向かっていく。そういう不思議な歌です。
私が奇跡の歌であるというのは、そこです。当時の若者の、この諦観、どうにもならない時代の流れの中、僕は当時の若者には時代に対する怒りがあったと思いますが、その運命を淡々と受け入れて、将来の日本に希望を託したのが当時の若者であったと思います。
藤江さんの魂に触れ、感動

門田氏は著書『康子十九歳 戦渦の日記』で藤江氏を取材した
私は田山花袋の言葉で好きな言葉があります。それは、「運命に従う者を勇者という」というものです。運命に従って、淡々と生き、淡々と死んでいった多くの日本人、先人、先輩方がいます。それを田山花袋はそういう言葉で表しています。私は当時の若者の心情というものは、そういうものであったと思っています。そのことを私は藤江さんの取材を通じて教えられました。
私は昭和33年の生まれなので、戦争のことは正直、お話を聞くことでしかわかりません。しかし、当時の自分の身に置き換えたときに、学問の場から命のやりとりをするところへ行かざるを得なかった人たち、その心情を慮ることはできます。悔しかっただろうと思います。子孫を残すこともできず、多くの若者が戦場で命を散らしていったのはご承知のとおりです。230万人が死んでおります。その中に学徒動員で行った人もたくさんいます。そういう犠牲の下に今の日本が成り立っているわけです。
私は中大の予科の方にたくさんお会いし、お話を伺いました。その中でいちばん感銘を受けたのは藤江さんです。取材というのは、人と人の魂のふれあいであり、ぶつかりあいです。僕は藤江さんの魂に触れたときに、本当に感動しました。
「人間は揺れこそが美しい」
本の中にも書かせていただきましたが、藤江さんはこうおっしゃいました。「人間は揺れこそが美しい」。揺れです。人間というのは、信念を持っていても、しっかりした考えがあっても、揺れるものなのだと。その揺れこそが人間なのだ、揺れこそが美しいということを、藤江さんは後輩である私に教えてくれました。僕はこういう先輩を持っている自分自身が誇らしかったです。中央大学を非常に誇らしく感じたのは、これは事実です。
「歴史の波動を書け」とも
そして、藤江さんは私にこういうことも言ってくれました。「君は歴史の波動を書いてくれ」と。これは後輩に託してくれた藤江さんの本当の真心の言葉だと僕は思っています。歴史の波動を書き残さなければいけない。歴史の波動を、何とか現代に伝えないといけないと思い、私は今も日々、取材に明け暮れています。

学生代表から贈られた花束を手にする藤江氏(右)と門田氏(左)
過去の出来事というものは、年月がたてば、歴史となります。けれども、それは“1行”の文章で表わせる単なる「事実」ではなく、人間の思いが凝縮されたものであり、その生(なま)の証言以上に貴重なものはありません。私は時間との戦いで、今、生の証言をできるだけ記録する作業を行っています。
僕も長い間、ジャーナリズムの世界にいるので、今の単純正義というものに毒された日本のジャーナリズム、そして社会というものに対して憤りというものがあります。正義というのは複層的なものであるのに、すぐに物事を類型化して論じてしまう今のジャーナリズムというものに、僕は非常に批判的です。大学生のときに、そういうものに毒されない、さまざまな勉強をして、中央大学の後輩にも社会に出て行ってほしいと思っています。僕はそういう気持ちで本を書かせてもらっています。
二つの言葉を忘れずに
その僕の気持ちを見通したかのような「人間は揺れこそが美しい」という言葉と、「君は歴史の波動を書いてくれ」という言葉、この二つを私は藤江先輩に託されました。これは藤江さんの生のお言葉をいただいた、非常に貴重な体験でした。
きょうは、その藤江さんが母校へわざわざ来てくれて、その『惜別の歌』に込めた心情、母校への思いを講演いただけるということで、本当に私はすべてを投げ打ってやってまいりました。こんな貴重な機会を持てる中央大学は本当に幸せだなと、私もOBの一人として思っています。
私は歴史に関すること、あるいは事件・事故など、さまざまなジャンルを扱っているので、これからもいろいろな本を書いていきますが、藤江さんの「人間は揺れこそが美しい」という言葉と、「君は歴史の波動を書いてくれ」、この二つをこれからも忘れることはないと思います。大先輩、藤江さんの話を本当に一つでも二つでも記憶に、永遠に残していっていただければと思います。きょうは母校に呼んでいただき、ありがとうございました。
- 門田隆将(かどた・りゅうしょう)氏
- 本名・門脇護。1958年高知県生まれ。中央大学法学部政治学科卒業後、新潮社に入社。週刊新潮編集部に配属され、記者、デスク、次長、副部長を経て、2008年4月に独立。新潮社に勤務当時から政治、経済、司法、事件、歴史、スポーツなど幅広いジャンルを対象に精力的に取材・執筆している。
- 主な著書に、『裁判官が日本を滅ぼす』(新潮社)、『甲子園への遺言―伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯』(講談社)、『なぜ君は絶望と闘えたのか―本村洋の3300日』(新潮社)、『康子十九歳 戦渦の日記』(文藝春秋)、『この命、義に捧ぐ―台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』(集英社)、『風にそよぐ墓標―父と息子の日航機墜落事故』(集英社)などがある。
- このほど『この命、義に捧ぐ』で第19回山本七平賞を受賞した。








