トップ>Hakumonちゅうおう【2009年冬季号】>【特別企画】「Hakumon ちゅうおう」学生記者有志主催講演会 法学部OB・ジャーナリスト 門田隆将氏「裁判員裁判が問いかけるもの」
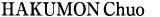 一覧
一覧
特別企画 「Hakumon ちゅうおう」学生記者有志主催講演会
法学部OB・ジャーナリスト 門田隆将氏「裁判員裁判が問いかけるもの」
ことし5月、国民参加の「裁判員制度」がスタートし、8月には第1号の裁判員裁判が行われました。法学部OBのジャーナリスト、門田隆将さんは、「相場主義」や「事なかれ主義」に陥っていた日本の「官僚裁判官制度」を破壊するものとして裁判員裁判の意義を強調されています。著書の『裁判官が日本を滅ぼす』(新潮社)、『なぜ君は絶望と闘えたのか-本村洋の3300日』(新潮社)などで、官僚裁判官の問題点を鋭く指摘されている門田さんに「裁判員裁判が問いかけるもの」をテーマに講演していただきました。
皆さん、こんにちは。門田隆将でございます。きょうは母校に呼んでいただきまして、非常に興奮しております。私は新潮社に長いこと勤めておりまして、去年の3月いっぱいで、25年勤めた新潮社を退職しました。在職中から本を書いてきて、この『裁判官が日本を滅ぼす』(新潮社)は、僕のデビュー作です。その後、何冊も本を書き、一番新しい本がこれです。文藝春秋から今年7月に『康子十九歳 戦渦の日記』という本を出しました。これまで全部で10冊ぐらいの本を書いております。
中央大学を卒業した高畠導宏さんという伝説の打撃コーチ、プロ野球界では非常に有名な存在でしたが、一般には全く無名だったこのコーチの生涯を描いた『甲子園への遺言』(講談社)は、NHKの土曜ドラマ『フルスイング』(全6回)になり、単発の視聴率では土曜ドラマの中で1番の14%台を記録し、お陰さまで再放送までしていただきました。
裁判員裁判の意義は…
公僕を忘れた官僚裁判官

門田 隆将さん 【略歴】
私はさまざまなジャンルについて記事や本を書いてまいりましたので、いろいろな所に呼んでもらっておりますが、今年は中でも司法関係の講演が非常に多くなっております。それは、裁判員制度がスタートしたからです。私は『裁判官が日本を滅ぼす』を書き、そして去年『なぜ君は絶望と闘えたのか―本村洋の3300日』を出しました。これは、今、20刷で13万部ほどになっています。そして今年3月には『激突! 裁判員制度 井上薫vs門田隆将』という対談本も出しました。井上薫さんは数年前まで裁判官をやっておられましたが、今は弁護士をしています。この人は『つぶせ! 裁判員制度』という本をベストセラーにした、裁判員制度反対の急先鋒です。
実を言うと、井上薫さんと私とは個人的には非常に親しく、激突といっても、問題点、すなわち官僚裁判官の問題については、全く意見が一致しています。その末に裁判員制度に賛成するか、反対するか、そこに意見の最後の違いがあるだけで、ほかはほとんど一致しています。
本日は「裁判員裁判が問いかけるもの」というテーマで、私が今までのジャーナリスト活動を通じて、見て、聞いて、知ったことを学生の皆さんにお話しさせていただきたいと思います。
裁判官は特別公務員なので、公僕ですから国民の奉仕者になります。公僕は、国民から質問が出た場合には当然、答えなければいけないので、私は裁判官を訪ねて、いろいろな質問をさせてもらいました。「裁判官、あなたはこのことについてどう思っているんですか」と、私は普通に聞くわけですが、裁判官はビクッとします。なぜかというと、彼らは一対一で物事と対峙したことのない人たちだからです。
皆さんは、法廷へ行ったことがありますか。あの一段高いところに座って、黒い法衣をまとって、法廷のすべてを牛耳っているのが裁判官です。そういう世界に長年いた裁判官は、自分を“神様”のように思っています。公務員であること、公僕であること、国民の奉仕者であることを忘れています。
私の質問に対してきちんとした意見を述べた方は、一人もいません。私はいつも「あなたは国民の奉仕者なのだから、きちんと答えなさい」と言いますが、「広報を通してください」「判決がすべてです」ということしか言いません。この言葉は、彼らが、自分たちが世間の批判から逃れるために利用してきた「便利な言葉」なのです。この日本の官僚裁判官たちがなぜ「日本を滅ぼす」のか。具体的にお話をさせていただきます。
光市母子殺害事件の年に
内閣が司法制度改革審設置
皆さんは、光市母子殺害事件をご存じだと思います。この事件を例にとって官僚裁判官の実態というものをお伝えしたいと思います。また、この事件は裁判員制度ときわめて深くかかわっているので、この裁判の経緯についてご説明します。
光市母子殺害事件は、山口県光市で1999年4月14日に起こりました。本村洋さんは広島大学工学部を出た、新日鐵のエンジニアで、その奥さんの弥生さん23歳と、お子さんの夕夏ちゃん11カ月が、18歳になったばかりのF君によって殺害された事件です。

著書を手に講演する門田さん
この事件の3カ月後に、偶然ですが、小渕恵三首相(当時)が内閣に司法制度改革審議会を設置しました。小渕さんは司法問題について非常に関心の深い人でした。そして法曹のあり方、司法が国民に何をなすべきか、法曹人口の少なさ、長期化する裁判……等々、さまざまなことを話し合うためにこの審議会を設置したのです。
私は当時『週刊新潮』のデスクをしておりました。神戸の酒鬼薔薇事件が97年5月に起きまして、その被害者となった土師(はせ)淳君のお父さん、土師守さんの『淳』という手記本を1年後に私は新潮社から出版して、非常に親しくさせていただいておりました。その土師さんから連絡がありまして、「光市母子殺害事件の被害者の本村さんという遺族がいるのだけれども、あの事件のことをご存じですか」と言われました。
実は土師さんと本村さんは被害者同士で非常に近い関係にありました。家族が殺され、絶望の中にいる人は、その苦しみのわからない一般の人がいくら慰めの言葉をかけても、立ち直ることはできません。それを知っている奥村哲郎という山口県警の刑事さんは、わざわざ県警の壁を超えて兵庫県警の土師さんの担当刑事に電話してきて、淳君のお父さんから本村さんに励ましの言葉をかけてほしいと頼んできたのです。
これは縦割りの警察の社会では非常に珍しいことです。その結果、土師さんは本村さんに励ましの電話をするわけです。そして、その上で土師さんから、私のところに連絡が来たわけです。
8月11日に山口地裁で事件の初公判が開かれましたが、ほかならない土師さんのお話ですので、私は行くことにしました。本村さんはもともと小倉の男で、九州男児です。8月11日の公判が終わって、故郷の小倉に戻りました。長時間の取材、お話をするために、私は小倉で本村さんと待ち合わせました。
被害者本村さんの言葉に衝撃
「絶対に殺す」「僕はひどい男」
私は、そのときに大きな衝撃を受けました。あまりに衝撃だったので、この本(『なぜ君は絶望と闘えたのか―本村洋の3300日』)は、最初に本村君と会ったときのことをそのまま描かせてもらいました。こちらのほうがわかりやすいので、ちょっと読ませていただきます。
プロローグ。―
青年は、こぶしを握りしめて震えていた。
視線は一点に注がれ、そこから動かない。テーブルの上にあるコップを見ているのか。それともその中にある水を凝視しているのか……。いや、どちらでもない。
彼の視界には、何も入っていない。彼は、空を見ている。そう思えた。
大きく息を吐いて、その青年は、こう言った。
「僕は……、僕は、絶対に殺します」
不気味に迫力のある声だった。押し殺しているだけに、それは余計凄味を感じさせた。
その瞬間、店の中の客が、何人かぎょっとして私たちの方を振り向いた。
一九九九年八月十一日、北九州市・小倉北区の薄暗い喫茶店で、私と青年は向かい合っていた。
紺色のTシャツに縁なしのめがねをかけ、スポーツ刈りよりも短く切りそろえた髪。本来なら優しくて愛嬌のあるはずの目が、これ以上はないほどの憎しみに震えていた。
どうにもならないこの感情をどうすればいいのか。その目は、怒りと憎悪の行き場が見つからない苛立ちと、もどかしさに支配されていた。
まだ二十三歳で、学生の雰囲気を残している青年の名は、本村洋。のちに、日本の司法を大変革させていくことになる人物である。
しかし、本人も、これから自分がそんな大それたことをやってのけるようになるとは、この時、想像もしていない。
いや、司法の世界に、変革していかなければならない問題があることすら、彼にはわかっていなかった。
「殺す」
と言った相手は、彼の最愛の妻と娘を殺めた十八歳の少年・Fである。
この日、妻・弥生と、一人娘・夕夏が惨殺された光市母子殺害事件の初公判が山口地裁で開かれた。
本村は、検察が朗読した冒頭陳述によって、初めて事件の詳細を知った。犯人が少年であったことから、本村には事件の細かな経緯やどんな家庭環境に育った少年であるかも知らされていなかった。
しかし、冒頭陳述では、母親のもとに必死で這っていく夕夏が床にたたきつけられ、弥生が死後レイプされる事件のありようが細かく描写されていった。
傍聴席で泣き崩れる弥生の母親を慰め、悔しさと無念さにみずからも涙があふれ出た本村は、初公判が終わった後、故郷・小倉に戻ってきた。
旧盆を間近に控えた小倉の喫茶店で、私は初めて本村と向かい合った。初公判の衝撃は、裁判が開かれた山口を離れても、本村の身体全体から窺えた。
「僕は、ひどい男です。僕は自分自身が許せない。絶対に許せない……」
本村は、店内の客の視線がやっとほかに移りだした頃、そう語り始めた。
「どういうこと? なんで自分が許せないの?」
怪訝に思った私が問うと、本村はふたたび感情を昂ぶらせた。
「僕は弥生を抱きしめることができなかった。死ぬその時まで、僕の名前を呼んだに違いない弥生を、僕は抱きしめることもできなかったんですよ」
そんなひどい奴がいますか。そんな情けない人間がいますか。僕は、変わり果てた弥生を抱きしめることができなかったんですよ……。
本村はそう繰り返した。
彼はそのことで自分を責めているのだ。次第に語気が強まる。
「僕は……僕は、そんなひどい男なんです!」……
正義信じていた司法に絶望
先に結論ありの「相場主義」

ボードを使って事件の経緯を説明
これはずっと続いていきますので、この辺りで止めさせていただきます。
私が衝撃と言ったのは、二つです。「絶対に殺します」と彼が言った、そのときの表情、目、これは本当に殺すだろうと僕は思いました。二つ目は、彼が自分自身を責めていたことです。自分自身を絶対に許すことができないと言って、彼は泣きました。その理由が、変わり果てた弥生さんを抱きしめることができなかったという一点だけです。弥生さんは絞殺で、首を絞められて殺されています。そうすると汚物が出ます。この犯罪は、それを拭き取ってまで、死後レイプしたという鬼畜の犯罪です。その遺体がどのような状態であったのかは、想像がつくと思います。それを第一発見者として彼は見つけたわけです。そのときに仰天し、腰が抜けた本村さんは、自分の名前を最後まで呼び続けたであろう最愛の妻を抱きしめることができなかった。そのことをもって、現在も彼は自分自身を責めつづけているのです。
1999年8月11日の本村さんとの出会いが、私がこの本を書くことになったきっかけです。その後、本村さんは、東京へやってくると私の家に泊まり、うちの子どもたちも非常になつくような関係になりました。
私は当初、「本村君、これは無理だよ。日本の刑事裁判は結論が決まっているし、セレモニーなんだよ。個別の事案は関係ないんだ」と何度ものどから出そうになりました。日本の官僚裁判官、日本の刑事裁判の実態というものを、何度も本村さんに伝えようとしましたが、なかなか言えませんでした。僕が言えるようなったのは、この2000年を越えてからです。

手にするのは著書『なぜ君は絶望と闘えたのか』
本村さんは、司法の正義を信じておりました。2人の命をあんな無惨な方法で奪った人間が、自らの命で罪を償わないなどということはあり得ないと、彼は信じておりました。しかし、日本の刑事裁判は、最初から結論は決まっております。これは後にも詳しく話していきますが、「相場主義」というものがあります。日本の刑事裁判では、判決は「相場主義」によって弾き出され、最初から結論が決まっている。つまり、個別の事案が争われているわけではないんだ、と。こう言うと、「そんなことはありません」と専門家の方が言うでしょう。しかし、日本の刑事裁判は、実際にはすべてマニュアル化されていて、個別の事案は形としてやっていますが、セレモニー化しています。結論は最初から決まっているのです。そのことも、後で少し話をさせていただきます。
僕は、2000年の3月22日に第一審判決が出るときに、無期懲役だということを言いました。結果は、やはり無期懲役でした。このときのことは、今でも思い出します。裁判を報じるニュースの映像で、今も必ず出てくるものがあります。それは山口地裁から道路一つ隔てた山口県林業会館で開かれた本村君の衝撃的な記者会見です。
彼は「司法に絶望した。控訴、上告は望まない。犯人を今すぐ僕の前に出してください。僕がこの手で殺します」と言いました。これは日本の電波に「殺人予告」が流れた、おそらく初めてのケースだと思います。僕は彼から「絶対に殺します」という言葉を聞いておりましたので、本村君は遂にこの言葉を公の場で言ってしまったな、と思いましたが、テレビで流れたその言葉を聞いた人は、衝撃を受けたと思います。
その記者会見の終わり際に、本村さんは涙があふれてきました。そして、こういう意味のことを言いました。これは僕の記憶に基づくものですが、「いつまでも犯人が憎い、殺したい、憎悪だけで過ごしていくのはつらい。被害者だって、もとの人間的な気持ちを取り戻すには、死ぬような努力が必要なんです」と言って、本村さんは言葉に詰まり、グッと泣きました。そのときメモしていた記者たちの目からも涙がボタボタ落ちました。記者たちにも家族がいるからです。小さな子ども、そして妻がいるからです。その気持ちが痛いほどわかるので、記者たちも涙をボタボタこぼしながら、その記者会見をメモしておりました。非常に印象的なシーンでした。
被害者心情くみ涙した小渕総理
国民参加の裁判促す司法審意見書
そこから予想していなかったことが、山口から遠く離れた東京で起こりました。昼のニュースが過ぎ、小渕総理が官邸から出てきたところで、記者たちに取り囲まれました。そこで言った言葉を知った私は、仰天しました。小渕総理は「無辜の被害者の救済がこのままでいいのか。政治家として本村さんの気持ちに応えなければならない」と言って、涙を浮かべたのです。取り囲んでいた記者たちは、びっくりしました。本村さんの気持ちに応えなければならないということは、事実上の判決へのクレームと捉えられても仕方がない発言だからです。本村さんは記者会見で司法に絶望したと、判決批判を繰り広げたわけですから。これは明らかに司法に対する行政の介入です。少なくとも、私にはそう思えます。
けれども、これは問題になりませんでした。これは司法への介入ですね、と言った記者もいませんでした。記者たちも、小渕さんの心情が痛いほどわかったからだと思います。小渕さんは、その1週間後に倒れ、さらにその1カ月後にこの世を去ります。この本村さんの気持ちに「政治家として応えなければならない」という小渕さんの涙のコメントは、結果的に彼の遺言となりました。
そして、司法制度改革審議会が2001年6月に最終意見書を提出します。小渕さんの後、森(喜朗)内閣ができました。森内閣は短命で終わり、2001年6月に意見書を受けとった総理大臣は小泉(純一郎)さんです。その最終意見書には、「裁判の過程に国民が参加し、裁判の内容に国民の健全なる社会常識を反映させる」という、裁判員制度の導入を促す画期的な文言が入っておりました。裁判の内容に国民の健全なる社会常識を反映させる。まさに小渕さんの遺志、遺言が入った意見書でした。
これは誰も言わないので、私は講演のたびに言わせてもらっております。国民の健全なる社会常識を生かすということは、官僚裁判官がいかに健全な社会常識を持たないかということを、国が認めたことでもあります。そして、この最終意見書から、裁判員制度スタートに向かって猛然と動いていくわけです。それから8年が経ち、2009年5月21日に遂に裁判員制度がスタートしました。そして8月に裁判員裁判第1号がありました。この第1号裁判の弁護人を務めた伊達俊二弁護士は中央大学出身です。
裁判員制度がスタートするまでには、多くの涙が流されております。今、言ったように、無期懲役の判決を受け取った本村さんが、その後、F君の極刑判決を勝ち取るために、激しい闘いをやっていくのはご存じのとおりです。
証拠採用された犯人の手紙
無期懲役の結論は変わらず
2000年3月22日の第一審判決に対して検察側は控訴し、舞台は広島高裁の二審に移りました。そこで出されてきた証拠を覚えておられますか。ワイドショーなどでも盛んに報じていたので、ご記憶の方もいると思います。それは犯人のF君が友達に宛てて出した手紙の数々です。その中には、こんなくだりがありました。
犬がある日かわいい犬と出合った。……そのまま「やっちゃった」、……これはつみでしょうか
ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよアケチ君。

テーマは「裁判員裁判が問いかけるもの」
こういう手紙が二十通以上出てきました。これは反省などしていない証拠として、検察側が出してきたものです。しかし、皆さんも不思議に思うでしょうが、そんな手紙がなぜ法廷に出てきたのでしょうか。私も長年いろいろなジャンルの取材をしておりますが、これほど検察・警察、つまり捜査側の執念を見た裁判は初めてです。
どういうことかというと、山口市の外れの山口刑務所に少年拘置所が併設されていますが、そこから犯人のF君はいろいろなところに手紙を出していました。手紙を出すときには、相手の名前だけが記録として残されております。日本中のどこの人に出したかはわかりませんが、名前だけは出ています。その一人ひとりを検察、警察が捜し出し、訪ねて行きました。
そして、手紙を見せてくださいと頼みました。多くが断りました。当たり前です。通信の自由を侵すようなことは、たとえ警察や検察のお願いであっても、断る人のほうが多い。けれども、額を床に擦りつけて、どうしても見せてくださいという、捜査陣の必死の訴えに何人かが応じました。それが、あの法廷に出てきた手紙の数々です。
しかし、これが出てきたときの法廷の衝撃は想像がつくと思います。当然、これは憲法違反だ、通信の自由を侵しているという抵抗が弁護人の側からありました。こんなものが証拠として採用されてたまるかと、激しい闘いになったのです。20通を超える手紙は宙ぶらりんのまま、なかなか証拠採用されませんでした。
しかし、遂に何通かが採用されました。なぜなら、「結論は決まっている」からです。無期懲役です。証拠採用しても結論は変わらないのだから、ここは我慢してくれ、おそらく重吉孝一郎裁判長は被告人の側には言いたかったと思います。

門田さんの話に耳を傾ける学生達
証拠採用されたうえに、二審の判決が出ました。2002年3月14日です。やはり広島高裁は検察の控訴を棄却しました。すなわち無期懲役です。そのときの判決理由として、重吉裁判長は「不十分だが反省している」としました。あの手紙を見れば、不十分だが反省しているどころか、誰も反省していないと思うでしょう。皆さんもそう思うでしょうが、結論が決まっている場合は、それでも罪一等減ずるために「不十分だが」という注釈を付けた上で「反省している」、よって「無期懲役」ということになりました。
そのときに興味深いシーンがありました。重吉孝一郎裁判長は検察側の控訴を棄却するという主文を朗読し、本来はすぐ出ていくはずが、そのまま法廷にとどまりました。弥生さんのお母さんは泣き崩れていました。本村さんは、申し訳ありません、自分の力が足りないために、と言いながら、お母さんを抱きかかえておりました。その姿を重吉裁判長はじっと見ておりました。やがて本村さんは重吉裁判長が自分たちを見ていることに気づきました。そして、そちら側を向いたときに、重吉裁判長は本村さんに向かって深々と頭を下げ、法廷を出ていきました。
重吉さんは「どうしようもないのです。現行の制度である限り、これは無期懲役なのです」と言いたかったのだと思います。これは私の主観ですから、重吉さんの本心を聞かないとわかりませんが、おそらくそうではなかったかと思います。
刑罰権は国家が独占するが…
無視された被害者・遺族の権利
これは、刑事裁判の中身がだんだん変わってきているということを象徴的に表すシーンだと思います。なぜなら、1999年8月11日に初公判が始まり、第一審の審理の過程では、本村さんは遺影さえ持ち込むことができませんでした。揉めに揉めた末に本村さんが許されたのは、黒い布を巻いて遺影を法廷に入れることでした。なぜ黒い布を巻かなければいけないのか。その理由について、裁判官は本村さんに言う必要もないわけです。ただ廷吏を通じてこういうことを言いました。「刑事裁判は裁判官と検察側と弁護側の三者で行うものなので、被害者には何の権利もありません」と。しかし、これは本当にそうなのでしょうか。たしかに法律には刑事裁判とは、裁判官と検察側と弁護側との三者で行われるということが書いてあります。
しかし、それを文字通り受け取ってしまうことに法律家の致命的な欠陥が見えるわけです。この人たちは司法試験の勉強のために、青春を棒に振って必死で法の条文を記憶します。そして、司法試験に無事合格します。それはそれでいいのですが、その結果、字面だけしか頭に入っていない、いわゆる法律バカになってしまう傾向が極めて強くなります。そういう人が司法の世界には実に多いのです。刑事裁判を「三者でやる」と書いてあったら、「三者以外はすべてアウト」と取ってしまうのが、彼らの特徴です。
ここに国家の刑罰権問題が出てきます。何かというと、皆さんもご存じのように刑罰権というのは国家が独占しております。私たち国民には刑罰権はありません。これはどこの国でもそうです。それはよくわかります。一人ひとりに刑罰権が存在したら、治安が維持できなくなってしまうからです。近代国家では、国家が刑罰権を独占しているのです。
しかし、江戸時代はどうでしたか。江戸時代には仇討ちの権利が認められておりました。そういうものを奪い去ったら、不満を抑えられない。幕府はたぶんそう思っていたのでしょう。刑罰権というのはそれほど微妙なものなのです。しかし、この問題について、法律家たちは二言目には、「刑事裁判は仇討ちの場ではない」と言います。確かにそうです。刑事裁判は仇討ちの場ではありません。裁判は三者で行われるのです。
しかし、もし刑事裁判が、被害者の無念の思いや遺族の絶望、そういった気持ちを酌み取ることのできないものだったら、国家が「刑罰権を独占」している根拠は何なのでしょうか。僕は説明ができなくなると思います。少なくとも、被害者の無念の思いや遺族の絶望の気持ちを酌み取った上で刑事裁判というものが行われなければ、被害者や遺族から国家が刑罰権を取り上げている根拠がなくなるのではないでしょうか。少なくともその気持ちを酌み取って刑事裁判を行わなければ、国民の信頼は得られないと、僕は長年にわたって考えておりました。
しかし、官僚裁判官にはそういうものは一切通じません。被害者、遺族の権利などは、全く無視されてきました。本村さんが幹事をやっている「全国犯罪被害者の会(あすの会)」が、この無視されてきた権利というものを具体的にアピールするようになって、やっと日本の司法、そしてマスコミは動き始めたわけです。
「出世」のため事なかれ主義に
低い量刑、高い有罪率
日本の官僚裁判官は、なぜそこまで“字面”だけを追う存在になってしまったのでしょうか。皆さんも不思議に思うと思います。この中にも、司法の世界を志向している方がいらっしゃると思いますので、僕はそういう人にはぜひ立派な司法人になってほしいと思います。字面に流されるような司法の人間にはなってほしくないと思っています。
なぜ日本の官僚裁判官はそれほど相場主義に捉われ、裁判そのものを形骸化させ、法律に書いてあること以外の、要するに人間的な気持ちを失ってしまったのでしょうか。あまりにも答えが単純すぎて、笑いが漏れると申し訳ないのですが、答えを書きます。答えは「出世」です。これがすべてです。
どういうことかというと、全国には地裁があり、またその先には支部があります。裁判官はどこにでもおります。出世から外れ、東京や大阪に行くことなく、支部から支部の地方回りをさせられている裁判官がたくさんいます。それにならないために、彼ら法律のエリート中のエリートたちは、最高裁事務総局の人事局に目をつけられないように、ひたすら事なかれ主義を貫くわけです。量刑が相場から外れたり、あるいは無罪判決を出したりすると、たちまち最高裁が目を付けます。この男の判決はおかしいんじゃないか、と一度目を付けられた終わりです。だから彼らはそうならないように、マニュアルに沿って、個別の事案をそこに当てはめ、相場に基づいて無難に判決を出していくだけなのです。確かに審理はしています。しかし、審理しているふりをしているだけで、答えは最初から決まっています。セレモニー化されているわけです。
皆さん、世界的に見て、日本の量刑は低いと言われております。それはなぜか、ご存じですか。私が日本の量刑が低いことまで「官僚裁判官の出世によるもの」だということを聞かされたのは、この『激突! 裁判員制度』での対談を通じてです。
井上さんは裁判官でしたから、対談の中で、いろいろな裏話を披露してくださいました。そして私に言いました。「門田さん、なんで日本の判決で量刑が低いのか知っていますか?」。「なぜですか?」と聞いたら、「それは出世だからだよ」と、こう言いました。一審判決で控訴してくるのは、大半が被告人の側だそうです。割合から見て圧倒的にこちらが多いそうです。控訴されると、もちろん二審で審理されます。そうしたときに、一審の事実認定がおかしいとされたときには、自分の査定に響く可能性が出てくるわけです。「それを僕たち裁判官は嫌がるんですよ」と。だから、そもそも量刑そのものを低く出し、なるべく被告人の側の控訴を少なくするんです、というのです。
では、世界的に司法の人たちを驚かせる、日本の刑事裁判の99.7とか99.8%という有罪率は何かということになります。よろしいですか。「有罪率は高くして量刑は低く抑える」、これが日本の官僚裁判官が無難に法廷を運営し、自分が出世していくための「方策」にほかならないのです。
最高裁の目を気にする裁判官
無難な法廷運営に流される
どのようにしてそれをやるのか。現実に、長年にわたって日本の司法で行われてきた刑事裁判での訴訟指揮をお話しします。裁判官になった人は、こういうことは絶対にやめてくださいという意味を込めて、話をさせてもらいます。
ここに被告人がおります。被告人が供述録取書を取られます。いわゆる供述調書です。逮捕された日から始まって、1、2、3、……ずっとあります。 20通ぐらい供述録取書を取られるのは当たり前です。また証人がA、B、C、D、E、F、これだけいたとします。
しかし、法廷に出てくる供述録取書は全部ではありません。検察にとって都合のいい、有罪になるような供述録取書だけしか出てきません。Aさんは「犯人である」と言いました。けれどもB、C、Dさんは「違うと思うよ」と言った場合に、検察は法廷にはAさんの供述録取書以外は出してきません。検察がすべての証拠を握っていますから当然です。
そして、弁護人が「ちょっと待ってください、逮捕直後の調書も出してください」、あるいは「Bさんという人の調書も出してください」と法廷で主張します。
そのときに法廷のすべてを牛耳っているのが裁判官です。その要求に応じたら、面倒な判断を迫られる場合が出てくる。すると裁判官はどうするか。簡単なことです。これを「却下」するわけです。そうすると、検察にとって都合がいい証拠だけで審理は進み、99.8%という見事な有罪率が維持されます。これも形骸化した日本の刑事裁判の実態を表す数字と言えます。裁判員制度では、公判前整理手続きというものがあり、ここには弁護側が要求する調書など、類型証拠はすべて出さなければならなくなりました。今までのような官僚裁判官による恣意的な法廷運営はできなくなりました。
先ほども言いましたが、無罪判決を出していくと、最高裁に目を付けられます。裁判官も全国の支部から支部を、回りたくありません。「ヒラメ裁判官」という言葉があります。ヒラメは海の底で下から上ばかりを見ています。足元の自分の審理ではなく、上ばかり見て、上の意向どおりの判決を出す裁判官を司法の世界では「ヒラメ裁判官」と呼びますが、実はそういう人がほとんどなのです。こういう中で、99.8%という驚異的な有罪率が維持され、さらに出世のためには、先ほど申し上げたように量刑を低くして、なるべく控訴されないように動くわけです。こうして無難に法廷を運営して、彼らは順調に出世していくわけです。
形骸化した裁判に9年の闘い
正義感と骨のある最高裁判事
腹立たしい具体的な事例はたくさんあります。私は、すべて具体例で話をすることにしています。なぜかというと、こういう司法の問題は、抽象論で言っても皆さんに信じてもらえない。ですから、必ず大きな、皆さんの知っている裁判を例にとって、僕はいつもお話をします。
皆さんが、平穏に暮らしているわが子、わが娘、お姉ちゃん、妹、そういった人を殺されたときに、結論が決まっている、セレモニー化した裁判を見つづける勇気がありますか。本村さんは、そういう形骸化した日本の刑事裁判そのものに対して闘いを挑んだのです。本村さんは、なぜあんなに強いのだろうか。あの人は何に対して闘っているのか、一般の人にはわからないと思います。しかし、自分がその身になったときに、初めてわかると僕は思います。
そういう闘いが9年間行われ、去年4月22日に差し戻し控訴審において、逆転の死刑判決が下されました。広島高裁に差し戻した最高裁第三小法廷の濱田邦夫さんという裁判官は、官僚裁判官ではありません。第二東京弁護士会の弁護士出身の最高裁判事でした。濱田さんは非常に正義感の強い人でした。F君の弁護人が最高裁に出廷しないことで大騒動になりましたが、そのときに濱田さんは、法廷にいることを命ずるという、前代未聞の「在廷命令」を出しました。その上で、審理を広島高裁に差し戻しました。気骨のある人だと思います。ちなみにこの人は中大ではなく、東大の出身です。
F君側はさまざまな戦略を駆使して闘いましたが、差し戻された広島高裁の判決で、遂に死刑判決が下されたわけです。僕は死刑がいいとか悪いとかの死刑制度の是非ではなく、「実質的な審理が行われたこと」を意義深いと思いました。相場とか、そういう形骸化したものではなく、二人の命が奪われた事件の審理がきちんと行われたのが、あの差し戻し控訴審だったと思います。これは司法にとって本当に素晴らしい出来事だったと思います。
「胸のつかえが下りた」と犯人
官僚裁判官制度を壊す裁判員裁判

学生記者から記念品を贈呈
私は、『なぜ君は絶望と闘えたのか』のエピローグで、僕とF君との対決の場面を書き、本は締め括りました。詳しくは是非、本で確認してください。
私は最後の最後に、広島拘置所にいるF君との面会に臨みました。去年4月22日のあの裁判を日本全国のメディア、全局が生中継しました。日本中のジャーナリストが集まったのではないかというぐらいの喧噪の中で、翌日、本人に会いに行ったのは私だけでした。1メートルもない、非常に幅の狭い面会室の中、仕切りの両側15センチづつ、あわせて30センチぐらいの距離で、私はF君と向かい合いました。
最初に私が気持ちを聞いたときに、F君は「胸のつかえが下りました……」と言いました。そのときに空気がため息のように出たのを、僕は今でも昨日のことのように覚えています。その目を見たときに、私は「死刑判決の重さ」というものを垣間見ました。憑きものが取れたような、法廷で見ていたF君とは全く違う人間になっていると感じました。死刑判決とは、これほどすごいのかと思いました。これは僕の正直な感想です。
死刑判決が下った翌朝、彼は胸のつかえが下りましたと私にしみじみ語り、そして、「人の命を奪った者は、自らの命で償うのは当然だと思います」と語りました。これは私が9年前に本村君から、つまりあの初公判の日に彼から聞いた言葉と全く同じものでした。正反対の立場で闘った二人の青年が、9年間の闘いの末に「同じ言葉に到達した」ことに、私は非常に心を揺さぶられました。
私は、本村さんたちの闘いの末にでき上がった裁判員制度が「問いかけるもの」は、本当に大きいと思っています。この制度には国民に対する大きな負担があって、欠陥がたくさんあります。しかし、それをもってしても、私はこの制度が存在する意義は深いと思っています。なぜならば、これは官僚裁判官制度を破壊する、巨大爆弾だからです。
私はジャーナリズムの中で数少ない裁判員制度の容認派としてテレビや講演に呼ばれています。これは私が実際の事件、その被害者、犯人、さまざまなものを取材させてもらった末に、僕自身が得た結論を語るからだと思います。この裁判員制度というものが、いかに重要かということを皆さんにも理解していただきたい。司法を目指す人には、きょう僕が指摘したような法律家にならずに、本当に人間の気持ちの通った、法律の“字面”に流されない法律家になっていただきたいと、心から思います。
きょうは、どうもありがとうございました。(拍手)
- 門田 隆将(かどた・りゅうしょう) 本名・門脇護(かどわき・まもる)
- 1958年高知県生まれ。中央大学法学部政治学科を卒業し、新潮社の週刊新潮編集部で政治、経済、司法、事件、歴史、スポーツなどの幅広いジャンルで多数の特集記事を執筆、2008年春退職し、独立した。08年7月に独立第1作として発表した光市母子殺害事件の9年間を追った『なぜ君は絶望と闘えたのか-本村洋の3300日』は、ベストセラー街道を今も走っている。








