トップ>Hakumonちゅうおう【2009年秋季特別号】>【創立125周年に向けて】中央大学のルーツ(上)
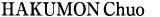 一覧
一覧
創立125周年に向けて
中央大学のルーツ(上)
英吉利法律学校はなぜつくられ、その目的は?
18人の創立者はどういう人?
「実地応用」の建学の理念が生まれたわけは?
法学部総合講座 『中央大学と近現代の日本』
菅原彬州教授/本間修平教授/有澤秀重准教授に聞く
シリーズ「創立125周年に向けて」の第2弾は、中央大学の『ルーツ』を上下2回にわたって辿る。1885(明治18)年に開校した英吉利法律学校は、なぜつくられ、その目的は。創立者はどういう人たちで、『実地応用の素を養う』という建学の理念(精神)が発祥したわけは?―。法学部総合講座『中央大学と近現代の日本』を担当する菅原彬州、本間修平、有澤秀重の3人の先生にうかがった。
近現代の日本史と関連づける
「自校史」で大学の歴史を学ぶ
―― はじめに法学部総合講座『中央大学と近現代の日本』を開設した目的から聞かせてください。

菅原彬州教授
菅原彬州教授 2004年度4月から、はじめは『中央大学と近代日本』という通年4単位の総合講座でスタートしました。そのころ、「UI」、ユニバーシティー・アイデンティティということがしきりに言われていました。日本語で言えば愛校心に通じるのですが、自分たち学生が中央大学に帰属していることを意識してもらおうというねらいもありました。
自分の学校の歴史を教えるのは、「自校史」と言われていまして、中大で言えば「中大史」ですね。それでタイトルは、いろいろ考えまして『中央大学と近代日本』ということになったんです。
私としては、愛校心を持ってもらうためにこの講座を開いたのではありません。結果として愛校心を持ってもらうのはよいのですが、自分の学んでいる大学と自分とは、どういう関係があるのかを認識し、理解してほしい。それが本来の講義の目的でした。

有澤秀重准教授
ただ、それだと大学の講義科目としては不十分ですので、歴史とかみ合わせながら論理力を養ってもらう。近代日本の歴史を、特に中央大学とつなげて考え、理解してもらうのが講座の趣旨です。
法学部のカリキュラム改革で、今年4月からは『中央大学と近現代の日本』というテーマで再スタートしました。本学100年史の編纂にかかわっていた私と本間先生、急遽お願いした有澤先生、それから100年史の仕事をサポートしてくれた大学史編纂課の職員の方々にも参加していただいて、当初から8人で講座を担当しています。
―― 1885(明治18)年に、中央大学の前身の英吉利法律学校が誕生しました。「英吉利法律学校」と、イギリスは漢字表記になっていますが…。
有澤秀重准教授 外国の国名、地名は江戸時代の終わりころから漢字で表記しています。
菅原 昭和初年ぐらいまで、そうです。『宛字外来語辞典』というのがありますが、アメリカは亜米利加と書いていましたね。
法学に対する社会的需要が急増
当時の法学教育は司法省と東大
―― そういった時代に英吉利法律学校ができました。その時代の背景と、開校の目的を教えてください。

本間修平教授
本間修平教授 それは、法学教育に対する社会的な需要が大きかったということです。例えばですね、明治9年から14年くらいまでの間に判事さん、検事さんが600人以上増えているんです。ところが、この間に法学教育を受けて社会に出た人は100人くらいしかいない。つまり500人はまったくの素人ということです。
それで明治20年代の終わりごろから、この人達は裁判官、検事にふさわしい教育をしっかりと受けていない、ということで退職に追い込まれるんです。きちんと法学教育を受けた人を早く育てなければならないという時代だったということです。
―― 誰でも判事、検事になれたのですか?
本間 試験がないですから(笑)。当時は公務員も裁判官も試験制度がなくて、明治17年に初めて試験制度ができるんです。弁護士も当初は資格がない。弁護士を当時は代言人と言っていたんですが、明治9年に代言人試験制度がはじまったんですけれど、これも素人に毛が生えたような試験しかやっていない。
それが明治13年に代言人規則が改正され、本格的な試験制度に変わるわけです。でも当時、法学教育を行っていたのは、司法省法学校と東京大学法学部ですが、どちらも一通りの教育を終えるまで8年かかっていました。
そういう教育システムだと十分な需要を満たすことができない。それで、速成コースが司法省と東大にもできるんですが、文部省が教育統制を行いまして、最も高級なエリートコースは東京大学ということで、司法省法学校を切るんですね。いずれにしても、法学教育が足りないという事情もあって、私立の法律学校ができるようになったのです。
「私立五大法律学校」が誕生
創立者18人は弁護士や官員ら
―― 最初にできたのは、どこですか?

初代校長・増島六一郎
本間 専修大学です。それ以前にも小さな塾はあるんですが、本格的な法律学校は明治13年の専修学校です。英米法系ですね。それに次いで翌14年に司法省法学校の卒業生たちがつくる明治法律学校(明治大学)、明治15年に東京法学校(法政大学)ができて、少しずつ機運が高まっていくんですね。東京専門学校(早稲田大学)が15年で、英吉利法律学校の中央大学が18年。明治22年には日本法律学校ができました。今の日本大学です。
―― 「私立五大法律学校」と言われていたようですが…。
本間 専修、明治、法政、早稲田、中央ですね。
―― 英吉利法律学校は増島六一郎先生をはじめ、18人の少壮の法律家(注1)がつくられました。18人というのは多いですね。
本間 中心になったのは増島六一郎、高橋一勝、高橋健三、岡山兼吉の4人だといわれています。
―― 社会的にどういう立場の人達だったのですか。
本間 増島六一郎は弁護士です。東大で講師もしていました。岡山兼吉も当時で言う代言人、弁護士です。高橋一勝も弁護士です。高橋健三は官員、役人ですね。18人の中には役人だった人も多いですが、その後、弁護士に転じた人も多いんです。
創立者の大半が東大で英法学ぶ
イギリス法の日本での普及目指す
―― 英吉利法律学校ということですが、なぜイギリス法を教えるようになったのですか。
本間 これはまた難しいところでして…(笑)。英吉利法律学校をつくったのは、初代校長の増島六一郎ら18人ですが、このうちのほとんどが東京大学法学部にかかわっていました。第二代校長となりました菊池武夫は、東京開成学校(東京大学の前身)時代の明治8年に文部省の派遣留学生でアメリカ(ボストン大学ロースクール)に留学します。翌年に穂積陳重がイギリス(ミドル・テンプル)に留学する。増島も明治14年にイギリスのミドル・テンプルに入学します。高橋健三のように東京大学法学部を中退した人もいますから、全員が卒業生ではありませんが、ほとんどが東京大学にかかわった人達ですね。

英国ミドル・テンプル
東京大学は英法教育が中心です。なぜかと言いますと、前身の東京開成学校時代に英、独、仏と語学を教えていましたが、外国人教師を招くにはお金がかかるんです。それでどれか一つに絞りましょうということで、世界で一番広く使われている英語になりました。
なぜ、イギリス法かと言うと、イギリスが当時の日本と最も関係が深い国だったということです。
ちなみにフランス法のことでお話しますと、司法省法学校は最初からフランス法を教えていたんですね。司法省で法典編纂に取り組むわけですが、その時のモデルがフランス法典なんです。
従いまして、フランス法を真似するにはフランス法の教育を行って、人材を養成しなくてはならないということで、司法省法学校ではフランス法で教育を行っていたんです。その卒業生たちが明治とか法政をつくったんです。
―― 中央の場合は東大ということですね?
本間 東大系ということです。専修の場合は英米法系ですけれども、つくった人がアメリカに留学した人が中心なので、英米法系ではありますが、東大とのつながりはあまり強くないんです。
―― 英吉利法律学校は東大系ということなのでしょうか。
有澤 東大系という説明に、私は納得していません。スタートはそうですが、そのまま現代まで来ているわけではないですからね。
本間 まとめて言うならば、東大を出た人達がイギリス法の素晴らしさに着目して、これを日本に普及させようとして、英吉利法律学校をつくったということになります。
「実地応用」に優れている英法
事実の積み重ねでできた判例法
―― 東京大学法学部は明治11年からですか?
本間 明治11年に第1期卒業生が出ます。
―― ちょっと調べてきたのですが、東大法学部は明治11年の第1期卒業生から英吉利法律学校ができる前の明治17年までに52人が卒業していて、そのうち12人が英吉利法律学校の創設に参加されたそうですね。圧倒的に東大系ですね。
本間 そうですね。英吉利法律学校をつくった18人には、イギリス法が素晴らしいという確信があったんだと思います。イギリス法を体系的にちゃんと教えたいということですね。イギリス法の特徴は「実地応用」に優れているということです。中央大学の建学の理念(注2)ですね。
イギリス法は判例法ですので、どういう事実があって、それにどういう法律を適用するか、それをセットで教えるんですね。そうしますと、事情がいろいろ違っている場合でも、法の適用原理が身につく。凄く応用力に富んだものだということです。
有澤 ちょっと本間先生を批判することになるかもしれませんが…(笑)。当時の近代法というのはヨーロッパなんですよ。ヨーロッパとアメリカにはふたつの違う流れがあって、簡単に言うと大陸法と英米法ですね。
大陸法というのはドイツ法、フランス法でナポレオン法典に基礎をおく。英米法というのは文字通りイギリス、アメリカです。大陸法とどこが違うかというと、判例を基準にして事実の積み重ねでできている。今回の事件は、あの時の事件と似ているから、その時の処理の仕方で行きましょうというものです。第何条では、と条文に照らす考え方ではないんです。
本間 憲法も民法も何もないんですよ。簡単に言うと、前例主義です。判例法主義とか慣習法主義というもので、憲法もいろいろな文章などの積み重ねで、法典の形にはなっていないでしょう。
事件を研究し、実社会に活かす
判例法主義で問題に柔軟に対処
―― 「実地応用」というのは、判例法主義からでてきたということですね?
有澤 そうですね。実際に起きた事件をもとにして、どういうルールにするかということが決められるんです。
本間 具体的に法律を適用するとき、グレーゾーンや境界領域というのが一番処理に困るわけです。そういったときに、実例として今までどのように処理が行われているのか、イギリスではどのように処理が行われているのかという研究が、常に教育とセットになっているわけです。
―― 事実経過をきちんと追うことが、勉強の大きな柱になっているということですね。そうすると、社会の仕組みがおのずと分かってくると…。
有澤 そうです。具体的な個別の事件を研究して、勉強して、そして実際にどのように社会を運営するかという発想をすることを「実地応用」と称した。
判例というのは応用した結果ですよね。こんな事件があってこうやりました、という記録ですから。ところが大陸法は発想が違うんですよ。ルールをバシッと決めると、ありえない事件であっても起こった場合には処理しなきゃいけない、という発想から体系的にやる。第一条第何項、という形で体系を作るんですね。
本間 ちょっと脱線しますが、例えばインドでは、どうしてイギリス法かということを考える必要がないんですね。イギリスの植民地ですから。アジアの国々は、植民地になっていたために、どういう法を選ぶかという選択の自由がないんです。日本だけは選択の自由があった。
有澤 ところがね、日本で英米法を採用するにしても、基礎になる伝統が違いますから、イギリス法をそのまま日本に持ってくるのにはきついものがあった。
本間 明治18年の段階では、選択肢としてはフランス法のほうが強かったんです。
菅原 ただ、国際社会はやはりイギリスが中心となって動いていたわけですよ。しかも日本はイギリスと一番関係が深いわけです。アメリカのペリーが日本を開国させたのですが、その後は日英関係が柱をなしています。
それに、さっき出た「実地応用」ですね。それを重視して、イギリス法を教えようということになったわけです。
本間 イギリス法を勉強すれば、実際に問題にぶつかったときに一番柔軟に対処できるということです。

学生記者のインタビューに答える3人の先生
身近な問題を処理できる人材育成
原書科で、英語で学ぶコースも
菅原 隣の家の木の枝が、わが家に伸びてきて、切っていいのか、というような身近な問題に対処できるような人を育てていきたい、ということです。
本間 隣から、タケノコが生えてきたときに食べていいかとか(笑)。
有澤 江戸時代だってタケノコは生えていましたからね(笑)。食べていいかどうかは、江戸時代以前の慣習とか、いろんなお定めで決まっていたわけです。ところが、それをやめて、世界共通のグローバルスタンダードでいこうと決めたからには、もう必死で学ぶしかないでしょ。今までの自分達の経験や慣習は役にたたないとなったわけですね。
―― 東大法学部は当時、英語で教えていたそうですが、英吉利法律学校は日本語で教えていたというのはどうしてなのですか?
本間 英語で教えるのが大変だったんですよ。司法省法学校はフランス語で教えているんですよ。英語、フランス語を学ぶのに4年間かかります。8年コースといいますけど、そのうち4年間は語学なんです。
当時は法律に対する知識がないでしょう。例えば、オブリゲーションを何て訳すかということも決まっていない。そういう段階だと日本語で教えられないわけですよ。そうすると外国人教師に頼って授業をすることになる。
それを、だんだんと日本語で教えられるようにしたいということで、準備期間があって、ようやく日本語でできるようになるのが明治10年代です。ただ、英吉利法律学校が特殊なのは、日本語で教えながら、他方、きちんとした英法教育をするには英語でなきゃだめだということで、明治19年に「原書科」という私立大学では滅多にない英語で法学を学ぶコースを作ったんです。
評判が悪かった当時の「代言人」
悪風除去し、立派な弁護士育てる
―― 増島六一郎はじめ18人の創立者は、人格教育に熱心であったようですが…。
本間 そもそも、なぜ法律を教えるのかということですが、日本には、当時の代言人、弁護士なんてものは社会に認められない存在だったんですよ。昔からですが、争いごとをお金儲けの手段にしていた。つまり、礼金を目的に紛争を起こしたりするとか、ですね。全ての弁護士がそういうわけではないですけどね。
ところが、イギリスでは弁護士はジェントルマンとして高い尊敬を受けていた。それなのでイギリスの弁護士は非常に高い自覚を持っているわけですね。これこそ日本に欠けているものだと、なったわけです。
日本の弁護士、当時の代言人があまりにも評判が悪すぎるので、これを改善しないと世の中よくならない、という思いが強かったと思いますね。
そういう点で増島六一郎は開校式(明治18年9月19日)の挨拶で、代言人の悪風、悪い風習は教育を通じて除去する。立派な弁護士を育てあげ、従来のような品格のない金儲けを目的とした弁護士じゃない者を育てる。それが自分達の希望だと言っています。そういう点で、非常に人格教育に増島六一郎は熱意を持っているんですよ。
―― 18人は志をひとつにしていたんですね。
有澤 中央大学の場合は、慶応や早稲田のように創立者にヒーローという人はいないですよ。一人のヒーローではなくて、チームなんですね。18人の若き法律家のチームなんです。
菅原 創立100周年のころに、「カンパニー精神」という言い方で、建学の精神のひとつの特徴をあげているんです。
―― カンパニー精神というのは?
菅原 18人が、みんなで学校を運営していこう、という発想ですね。
有澤 今の政治学の言葉で言えばアソシエイションでしょうね。要するにチームで共同してやる、というところに積極的な意味を置くべきじゃないかと思います。
菅原 今も「オール中央」という標語がありますけど、それと同じような意味で、「カンパニー精神」と創立100周年のころに言ったのかもしれません。
有澤 危機意識を共有しているから誰が目立とうとか、誰が取り仕切ろうとか、という競争なんてなかったと思いますよ。18人を支えたのは、「早く、この国をなんとかしなきゃいけない」という危機意識だったのだと思います。
注1:創立者は増島六一郎、高橋一勝、岡山兼吉、高橋健三、岡村輝彦、山田喜之助、菊池武夫、西川鉄次郎、江木衷、磯部醇、藤田隆三郎、土方寧、奥田義人、穂積陳重、合川正道、元田肇、渡辺安積、渋谷慥爾の18人。
注2:東京府に提出された英吉利法律学校設置願の「本校設置ノ目的」では、「邦語ニテ英吉利法律学ヲ教授シ、其実地応用ヲ習練セシムルニアリトス」とある。また『朝野新聞附録』に掲載された英吉利法律学校設置広告では、「実地応用ノ素ヲ養フ」とある。
【インタビュー/構成】
学生記者 野村茉莉亜(商学部3年)/石川可南子(法学部2年)/堀滝登(文学部2年) +編集室








