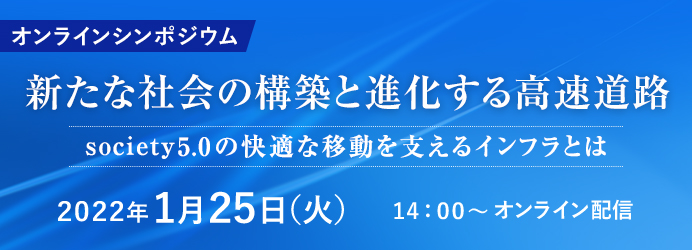
2022年3月11日
未来貢献プロジェクトのオンラインシンポジウム「新たな社会の構築と進化する高速道路」(読売新聞社主催、国土交通省、NEXCO東日本後援)が1月25日、読売新聞東京本社で開かれた。道路と車が相互に連携する「路車協調」などについて、国立科学博物館産業技術史資料情報センター長の鈴木一義さんが基調講演。パネルディスカッションでは、自動運転社会の到来に向け、車と道路が通信でつながる必要性を巡って意見が交わされた。
- 主催:
- 読売新聞社
- 後援:
- 国土交通省・NEXCO東日本
基調講演
車と道路 つながる時代

1957年、新潟県生まれ。東京都立大院修了。経済産業省の「ものづくり日本大賞」選考委員なども務めている。
国立科学博物館産業技術史資料情報センター長 鈴木 一義氏
日本で現在の道路法につながる法律が最初に制定されたのは1919年(大正8年)になる。国道が造られ、翌年には東京や横浜といった都市間で舗装道路が造られた。23年の関東大震災で鉄道輸送が機能停止。その頃から車の利便性に注目が集まり、昭和に入って大手自動車メーカーが生まれた。
戦後間もなく、日本の道路はほとんどが未舗装だった。52年に本格的な道路整備計画が始まり、東京五輪が開催された64年に首都高速道路が整備された。その後は名神高速や東名高速が全線開通し、国内の保有自動車数は1000万台に到達した。20世紀後半までの50年間で、道路整備と車の普及が急速に進み、物流、人流が活発になって社会が発展した。
2000年以降は、道路整備の新たな位置付けが必要になっている。日本でもデジタル技術で車社会の課題を解決する道路整備が始まる。30年に予想される交通社会では、車を運転して移動したい高齢者をどうするか、人口が減る地方の交通手段をどう確保するかも課題になるだろう。
これらを克服するために、インターネットの技術を応用した自動運転に関する法律、技術の整備が始まっている。高速道路など一定の条件下で自動運転する「レベル3」、特定の条件下での完全自動運転である「レベル4」の実験が国内でも行われている。自動料金収受システム(ETC)が情報を配信する技術が応用される。
日本の自動運転技術は世界でもトップレベルにある。法整備は世界に先駆けて進んでおり、ホンダからレベル3に対応した車が発売された。ドイツも開発が進んだものの、法整備などの面で欧州や世界の基準に合わせることが難しく、発売には至らなかった。自動運転車の普及には、法律と道路環境の整備が不可欠なことがわかる。
今年から25年にかけ、自動運転技術の急速な普及が考えられる。車と道路だけではなく、車同士の通信ができるような環境を整えなければならない。
戦後から2000年まで、日本の道路は、道路と自動車の両輪で発達してきた。2000年からは(通信を伴う)新たな両輪が必要になると思う。
パネル討論
自動運転 変わる移動
パネルディスカッションは、「自動運転社会の実現をめざして」をテーマにした。国立科学博物館産業技術史資料情報センター長の鈴木一義さん、自動車技術総合機構の児島亨さん、一般社団法人「Public Meets Innovation」代表理事の石山アンジュさん、読売新聞東京本社調査研究本部の高橋徹主任研究員がそれぞれの専門分野を基に活発な意見交換を行った。司会進行は三菱総合研究所の杉浦孝明さんが務めた。
「地域経済活動 伸ばす」鈴木氏/「近い将来 交通円滑に」児島氏/「日本の隅々まで旅行」石山氏/「若者の意識 吸収必要」杉浦氏

一般社団法人「Public MeetsInnovation」代表理事
石山アンジュ氏
1989年、神奈川県生まれ。国際基督教大卒。「一般社団法人シェアリングエコノミー協会」常任理事としても活躍する。

自動車技術総合機構
児島亨氏
1966年、神奈川県生まれ。芝浦工業大院修了。自動車安全研究部上席研究員として自動運転などの研究に尽力している。

三菱総合研究所
杉浦孝明氏
1970年、愛知県生まれ。慶応大院修了。三菱総合研究所では、営業本部に所属している。

読売新聞東京本社調査研究本部
高橋徹主任研究員
1965年、山形県生まれ。読売新聞社の経済部次長など経て現職。日本証券アナリスト協会認定アナリスト。早大院修了。
石山さんは東京都と大分県で「2拠点居住生活」を送る。「月の7割が東京、3割が大分だったが、リモート化が進み、比率が逆転した」と、コロナ禍での生活の大きな変化を強調した。
総務省によると、2021年は東京23区で初めて転出者が転入者を上回る「転出超過」となった。石山さんは、これまでの東京一極集中から、「働き方や暮らし方の分散化が起きている」と指摘。「変化の激しい時代だからこそ、一つに依存するより、複数収入口やコミュニティーに属することができるライフスタイルが求められている」と話した。
人流抑制が求められたコロナ禍は、移動への意識や行動の転換点となった。児島さんは、会議の多くが対面からオンラインになったことに触れ、「移動時間を削減できる点はメリット」と述べた。一方で、モニター越しでは雑談が乏しくなるだけでなく、相手の主張や真意を深く理解するのが難しいとし、「長所と短所をうまく活用することが重要」と述べた。
調査会社クロス・マーケティング(東京)が昨年5月、20~69歳の男女を対象に実施した調査では、コロナ前と比べて「自家用車の利用が増えた」とする回答は約4割だった。
石山さんは、「駅からすぐのシンボル的な場所ではなく、車でしか移動できない所を旅行したい人が増えている」と分析した。
デジタル化進展を背景に、インターネットに常時つながる車「コネクティッドカー」が増えている。現在はカーナビの自動更新や緊急時の自動通報といった機能が中心だ。
児島さんは「近い将来、車と道路などのインフラ間の通信で、衝突の回避や交通の円滑化につながることが考えられる」と予想した。杉浦さんは「運転中はスマートフォンを使えない。車自体がつながってサポートすれば便利になり、安心して出かけられる」と話した。
安全で快適な運転には運転支援機能の活用も有効だ。アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)はその一つ。車を事前に設定した速度で走行させる機能で、前方の車をカメラやレーダーが認識し、適切な車間距離を保つ。
児島さんは「最近は、渋滞時に前の車が止まった場合、自分の車も完全に停止できるのが主流になった」と進化を説明した。鈴木さんは月1000キロ・メートルほど運転するという。「ACCがあると安心で非常に楽。アクセルを踏み続けなくてもよく、前方を見ることだけを意識するので疲労が少ない」と評した。
ただし、ACCはあくまで「支援」。自動運転ではない。悪天候の場合に対応が難しいなど、機能には限界がある。自動運転社会が来れば、同乗者の車内の過ごし方が変わるだけでなく、ドライバーの負担が一段と軽くなることが予想される。石山さんは「車で行ける距離が伸び、日本の魅力ある地域を隅々まで旅できるようになる」と期待した。
自動車専用道である高速道路は、ACCをはじめとする新技術を導入しやすい。車での移動機会を増やしてきたインフラ(社会基盤)の役割をこれまで以上に果たすとされる。児島さんは、「一般道に比べると導入の技術的なハードルは低い。今後もシステムの普及が進み、『新しい高速道路』になっていく可能性がある」と予想した。
新技術により、東京、名古屋、大阪といった大都市経済圏の在り方が変わるとの見方がある。例えば、安全に遠出できるようになれば、運転に自信がない人の行動範囲が広がる。従来は行かなかった地方の店に出向くなど、大都市圏に集中していた個人消費に変化をもたらしうる。
鈴木さんは、日本の様々な魅力を知る機会が増えるとし、「地方の人口減少を防ぎ、経済活動を伸ばすための道路網の整備を期待したい」と話した。石山さんも、「移動することが『楽しい』『苦痛にならない』『安全』という意識が高まれば、地方創生の大きなチャンスになる」と述べた。
一方、杉浦さんは、「大手自動車メーカーや高速道路会社は、若者の意識を吸収しないと、そっぽを向かれかねない」と指摘した。新技術の実用化だけでは、近年続く若者の「クルマ離れ」を抑える効果が限定的となる。
高橋主任研究員は、「国土交通省と自動車メーカーは、自動運転を高速道路がどうサポートしていくかという研究を進めている。2、3年後に出る結論に期待したい」と述べた。


写真=シンポジウム「新たな社会の構築と進化する高速道路」でのパネルディスカッションの様子(25日、読売新聞東京本社で)=永井秀典撮影