
2023年もたくさんの日本映画が世に出たが、中でも、12月22日全国公開の「PERFECT DAYS」はユニークな一本だ。ドイツの名匠、ヴィム・ヴェンダース監督が東京を舞台に撮った作品。描かれているのは、役所広司さんが演じる東京・渋谷の公共トイレ清掃員・平山の一見、地味で代わり映えのしない日常だが、なぜか、見るほどに心動かされる。役所さんは、本作の演技でカンヌ国際映画祭最優秀男優賞にも輝いた。一体何が、こうも人の心を引きつけるのか。映画の母体となったプロジェクト「THE TOKYO TOILET」(TTT)の発案者・資金提供者である柳井康治さんと対談したヴェンダース監督は、「平山さんは、今の私たちの世界が必要としているキャラクターだ」と話す。

◇ THE TOKYO TOILET(TTT) 日本人が本当に世界に誇れるものを問い、かたちにしたプロジェクト。世界で活躍するクリエイターが設計・デザインした個性豊かな公共トイレを、柳井康治さんと日本財団が資金提供し、東京・渋谷区内の17か所に設置。従来の公共トイレのネガティブなイメージを払拭し、誰もが利用しやすく、日本の「おもてなし」文化の象徴となる施設に生まれ変わらせることを目指した。
役所さんが主人公にリアルさ与えた

「PERFECT DAYS」は、TTTの一環として、柳井さんの企画・プロデュースによって生まれた映画だ。主人公の平山は、東京・押上のアパートで一人、簡素に暮らしながら、毎日、渋谷の公共トイレへ仕事に出かける。同じことを繰り返しているようだが、ひとつとして同じ日はない。

ヴィム・ヴェンダース 1945年、ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。現代映画界を代表する映画監督。「パリ、テキサス」「ベルリン・天使の詩」などの数々の名作で映画ファンを魅了。「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」「Pina/ピナ・バウシュ踊り続けるいのち」などドキュメンタリーでも名高い。プロデューサー、写真家、作家としても活動。
ヴェンダース 平山さんは、我々の多くがかなえられずにいる夢を思い出させる存在だと思います。彼は、多くを持っていなくても幸せです。余計なものを持たず、持っているもの、自分にとって本当に大切なものをきちんといつくしみながら生活している。
多くの人が、本当は、彼のようになりたい、生きたいと思っているのだけれど、かなえられずにいます。「ものを持ちすぎる病気」にかかっていて、苦しんだりもしている。
ですから、平山さんは現実には存在していないかもしれません。でも、役所さんが非常にリアルな存在にしてくださったおかげで、この映画の観客の方も、「自分も平山さんみたいになれるかもしれない」と夢見ることができるようになったと思います。作り手である私自身もそうでした。そういった意味で、今の私たちの世界が必要としている、とても重要なキャラクターなのではないでしょうか。
柳井 映画づくりのどの段階で、そのように思いましたか。脚本を書いている段階から、そういうことをお考えになっていたのでしょうか。
ヴェンダース ストーリー探しの始まりの段階から、平山さんがこういう人であるかもしれないという夢は抱いていました。英語のケアテイカー(caretaker)という言葉に、平山さんにこうあってほしいという私の夢が入っています。この言葉には、職業としての清掃員ということ以上の意味、ケアをする人という意味が込められている。平山さんは、丁寧に生き、好きな仕事をして、自分が愛するものの面倒をしっかり見る、ケアをする……。柳井さんが手がけた、すばらしい、美しいトイレも、誰かがケアしなければいけないものでもあるわけで、最初から、そういう人が必要だったのだと思います。

やない・こうじ 1977年、山口県生まれ。ファーストリテイリング取締役。普段はユニクロのグローバルマーケティング・PR担当役員として従事。日本財団と渋谷区が実施した「THE TOKYO TOILET」の発案者。日本財団とともに資金提供した。個人プロジェクトとして、映画「PERFECT DAYS」の企画発案、出資、製作を手がける。
柳井 監督は、ストーリーを作る段階で、TTTのトイレは、東京の喧騒の中の小さなサンクチュアリ、つまり静謐な聖域で、そこを清掃する人は、神聖な場所を守るmonk(修道僧)のような雰囲気を持つ人だというようなことをお話しなさった。それをうかがって、何かとても美しいものができそうだな、と感じたことをすごく覚えています。
完成した映画を今年2月、ベルリンで見せていただいて、終映直後の数分間は、本当に言葉にならず一言も発せられなかったんですけれど、「まずは君からどう思うかを話さなくてはダメだ」と言われて、なんとか感じたことをいろいろお話しました。その後、監督からは、「この映画には、利他の精神が息づいている」というお話がありました。このプロジェクトを始めた僕自身、平山さんというキャラクターを作った役所さん、それを届けたいと思った監督自身や(「PERFECT DAYS」チームの中心人物の一人)高崎(卓馬)さんの利他の心が、この映画には出ているんだと。利他という言葉は僕の中でもキーワードではあったので嬉しかったですね。
人はみな違い、毎日も一日一日が違う

柳井 僕は、TTTのプロジェクトをやる時に、かつて父に言われた「人間は一人一人が全員違う」という言葉を大切に思っていました。男性用もあるし、女性用もあるし、そのどちらでもないと自分が思う人のためにユニバーサルトイレもある。一人一人が本当に違うんだと伝わるといいなと思っていました。「PERFECT DAYS」の平山さんの毎日も、一日一日、みんな違う。毎日同じようなルーティンを繰り返すんだけれども、同じ日は一日としてなくて、誕生日とかクリスマスだけでなく、普通の日も本当は特別で、その日しかない日である。今思えば、そういうことを監督はおっしゃりたかったのかなというふうに思います。
ヴェンダース そうですね。多くの人はルーティンという言葉をネガティブに捉えると思います。退屈さとか、自由の逆をいく状況を連想しがちですから。でも、平山さんが映画の中で重ねるルーティンを見ていくと、彼はまさにそのルーティンの中からたくさんの喜びを得ている。ルーティンがあるからこそ彼の日々にはストラクチャー、構造があり、構造があるからこそ自由が生まれるんです。
今は、多くの人が人生の中のストラクチャーを見失って苦しんでいる気がします。朝同じ時間に起きるといったことだけでは、ストラクチャーにはなりません。それは単なる習慣、必要性です。ストラクチャーとは人生に目的を与え、私たちの助けになるもの。ストラクチャーがあって、リミットがあればこそ、自分にはどのくらい自由があるのかがわかる。平山さんは、そういったパラメーターを再定義してくれる存在です。
ものを持ちすぎることの恥ずかしさ
ヴェンダース 私たちは、常に必要よりも多くのものを買ってしまいがちです。本屋さんに入っても、つい2、3冊、買ってしまいませんか。(映画の中の平山のように)1冊だけ、自分が本当に読むために買って、終わってからもう1冊買いに行くというのは革命的なことだと思うんです。真に革新的だと思うんです。必要なものだけを買う。
柳井 それは究極ですね。ユニクロも必要なものだけ売りたいんですけど……いや、やっぱりたくさん買ってほしいですかね。(笑)
ヴェンダース 僕は、(妻の)ドナータから食料品の買い物を頼まれた時にも、1個で済むところを、「もしかしたら2日後にまた食べるかも」などと考えて、3、4個買ってしまう。だから、僕が買い物に行くと、買い過ぎてしまって、結局は消費期限が過ぎてしまったヨーグルトを捨てるはめになったりするのです。
だけど、平山さんは、本は1冊しか買わない。朝はコーヒーを1缶。若かった時に手に入れた音楽のカセットを聴いている。それはもちろん今も好きで、新しく買う必要はないからなのですけれど。
僕はと言えば、1回しか聴いていない音楽をたくさん持っています。レコード2万枚、CDも2万枚。もしかしたら、これから数年間の間に聴けるのは、その1%ぐらいじゃないかとも思います。加えて、何千本というフィルムライブラリーを持っています。これは職業病かもしれません。大好きな監督の作品は全部ありますが、それを改めて全部見ることができるかどうか……。
そうしたものを今は、それを手放し始めています。いろいろなものをたくさん持ちすぎていることを恥ずかしく思っているんです。撮影の後、帰国して、本の半分をほかの方に譲りました。ドナータと二人で「半分に減らしましょう」と言って。次の年、またさらに半分にしましょうと決めました。
「平山さんに会いに行こう」と撮影へ

誰かと出会って影響を受ける。ヴェンダース監督は平山との「出会い」を通じて、そういう体験をしたようだ。
ヴェンダース 出会ってからずっと、私の心の中に平山さんはいます。柳井さんはご存じですが、私は実際に毎日、「平山さんに会いに行こう」と言って撮影していたんです。
柳井 撮影中の監督の反応を見ていると、役所さんがお芝居をするたびに、その反応をすごく喜ばれて、「じゃあこんなパターンをやってみて」「こういうパターンもやってみよう」という感じでしたね。そこでどんどん平山さんが生まれていっているように見えました。
ヴェンダース 最初のうちは、そうでした。クランクインしてから最初の数日間は、平山さんは、フィクションの存在であり、役所さんはそれを演じる演者であった。けれども、日が過ぎていくうちに、ドキュメンタリーを撮っているような感じになりました。私が提案しなくても平山さんは存在し始めていって、フィクションを置いて先に進んでいったドキュメンタリーのキャラクターを追っていくような感覚になったのです。平山さんは、僕らにとって、そのぐらいリアルな存在になったんですよ。
実は、役所さんおひとりのシーンは、テストもしないで撮影していたんです。リハーサルをせずにすぐ本番。私が何か修正したり加える必要もなくて、本当に平山さんが存在しているということがうれしくてうれしくて仕方がありませんでした。
ほかのキャストがいる場合は、またちょっと状況は変わって、もちろんテストはしました。そうすると、フィクション作りにまた戻るわけです。その場合はもちろん、ほかの演技者たちをリスペクトしなければならない。
でも、平山さんは常にほかの登場人物よりもリアルな存在だったのです。ほかは架空、フィクションなんだけれども、平山さんはまた別次元、リアルな世界に現実に存在していました。本当に役所さんから特別な贈り物をもらったと思っています。
柳井 役所さんを連れてきたことが、僕の最大の功績だと言われました。
ヴェンダース おかげで僕の仕事が楽になりました。
「今」を大切に 平山と重なる田中泯さん

「PERFECT DAYS」には、ダンサーの田中泯さんも出演している。平山が折に触れて出会うホームレスの役。公園の片隅に、街の真ん中に、その肉体は確実に存在し、踊りながら息づいている。ヴェンダース監督は「PERFECT DAYS」とは別に、田中泯さんのダンスを見せる9分の短編「Somebody Comes into the Light」を作り、今年秋の東京国際映画祭で世界初上映した。
ヴェンダース その短編のアイデアは後から生まれたものです。田中泯さんのことを(「PERFECT DAYS」の中で)使えるよりも多く撮影していたんです。平山さんの夢の中でもっと大きな存在として出てくるという構想もあったので。ただ、1人のキャラクターがすごい存在感を持ってしまうと、平山さんの夢の性質が変わってしまうことに途中で気づき、偉大なる泯さんの美しい即興の舞踊(の映像)が使われずに残ってしまった。そのことに対する罪悪感があり、「短編作れるよ」と(「PERFECT DAYS」チームの)高崎卓馬さんに提案したのです。
柳井 作品に出ていただいたのをきっかけに、僕も、田中泯さんのご自宅にお邪魔してお話をしたりするようになったのですが、泯さんご自身、平山さんにある種似ていて、あまり物を持たない。ご自分の踊りを記録したり、何か作品にとどめるということにもあまり執着がなくて、その場で起こることが全て、という考え方でいらっしゃる。でも、だからこそ、監督や僕らもそうですけれども、あの踊りに魅力を感じて残したくなる。残せないと言われると残したくなる感じもあるというか……。
平山の毎日がそうであるように、泯さんにとっても毎回の踊りが本当にスペシャルで、すべてが違う。同じテーマで踊っても彼の今日のダンスと明日のダンスは違う。同じ踊りは二度とできない。それがヴィムさんの気持ちを捉えて、何かに残してみたいと思われたのかなと思うと、僕もそれは見てみたいなと思いましたね。
ヴェンダース まさに柳井さんがおっしゃるように、泯さんと平山さんには共通しているところがあると思います。2人とも本当に心が広くて、寛大さというのも生来備わっている。泯さんのパフォーマンスは一度きりのもので、その瞬間、それを目撃する人たちだけが見ることができるもの。今その瞬間を生きることの意味、今ここに存在することの意味を見せてくれる。そんなふうに一回一回、踊ることができるのは、心が広いからだと思います。
「PERFECT DAYS」の中の平山さんも重要なレッスンとして、同じことを姪に教えようとするわけです。「今度は今度、今は今」という遊び心をこめた言葉を通じて、今は今しかない、過去は過去なんだと。2人とも同じメッセージを私たちに伝えてくれている存在です。
柳井 本質的には全部つながっているんだと思います。
ヴェンダース そのとおりだと思います。
現場の笑顔がみんなのベストを生む

柳井 平山さんは少しユーモアを感じさせるキャラクターでもあります。そうなったのは、監督のキャラクターのおかげだというふうに役所さんはおっしゃっていました。僕も、監督のパーソナリティーがすごく反映されていると思います。現場での監督のたたずまいが周りを楽しくさせ、みんな笑顔で撮影をしているという、あの環境じゃなければ、あの平山は生まれない。
ヴェンダース 映画は、関わっている人の仕事の質が反映される。だから、みんなに最高のものを出してもらいたいのであれば、みんながそれを出したいと思わせる現場でないといけない。自分がリスペクトされ、大事にされていると感じられなければ、みんなベストなんか出してくれません。
小津(安二郎)組の名キャメラマン、厚田雄春さんにお話をうかがった時、小津さんの現場ではみんなたくさん笑っていたと聞いて、すごくうれしかったです。小津監督も常にジョークを飛ばしていたそうで、それを聞いたときに、だから良かったんだ、素晴らしい監督なんだと思いました。
柳井 役所さんも、巨匠と呼ばれるような監督の現場は常に面白いと思うとおっしゃっていました。今村昌平監督の現場も、ヴィムさんとの現場も、それが共通していると。そうなんでしょうね。
ヴェンダース そうですね。カメラの反対側、映らないほうはマルクス兄弟ということで。
過去の作品に学び、未来につなげる
ヴェンダース監督は、かつてパリで画家を目指していたが、シネマテークフランセーズでの映画上映に通うようになり開眼。映画の道を選んだ。シネマテーク通いの日々を、監督の公式プロフィルは「映画史の特訓」と表現している。

柳井 僕はヴェンダース監督の映画作品を何本も見ていますが、いつまでもずっと見ていたくなる、その映像の世界観がすごく好きです。監督が初めて、このプロジェクトのために日本にいらした時、奥様のドナータさんにそのことをお話ししたら、彼女も同じ考えで、「なぜヴィムがそういうものを撮れるか知っている?」と聞かれたんです。もちろん、僕は知りませんので、そう答えたら、ドナータさんは、「それはヴィムの才能で、ヴィムが撮れば必ずそういう映像になる」とおっしゃいました。
そうしたら、近くにいらしたヴェンダース監督は、それまで僕らの会話を聞いていないふうだったのに、ぱっとこちらを向いて、「違う」と。「自分は全部計算してそういうものを撮っている」とおっしゃったんです。それに対しては、ドナータさんも「えっ、本当? ナチュラルにそういうことができるんじゃなくて?」と驚いていましたが、「違う、違う」と。
監督は、素晴らしい過去の映画監督の作品を見て学び、ご自分なりのやり方を見つけ、それを今、未来につなげているんだとおっしゃっていた。「I learned a lot from the past and I bring it to the future」というその言葉が、僕にとっては、ものすごくかっこよくて、監督から僕は今、まさに学ばなくてはいけない、そして学んだものを何とか頑張って、監督ほどじゃないにしても、次の人に届けられたらいいなとは思いました。
ヴェンダース 画家になっていたら自分はどんな人間になっていただろうな、と、今、一瞬、想像してしまいました。かつての僕はとてもシャイな人間でした。あまり社交的ではなくて、すごく真面目で、シリアスすぎて友人たちも僕を怖がっていました。画家になっていたら、そういう人間のままだったんじゃないかと思います。だけど、映画はほかの人がいい仕事をしてくれることに頼らなければいけない。だから、映画作りを通して、僕は、よりオープンな人間になることができたんです。
柳井 そうした映画作りにおけるアプローチについて、映画監督同士でお話したりするんですか。
ヴェンダース しません。何カ月か前に、フランスの女性の小説家3人のパネルディスカッションを見ました。仕事のやり方、どうやって小説を書くのか、どこからアイデアが来るのか、1日のどんな時間が一番書けるのか、タイプライターを使うのか、手で書くのか。自分たちの創作の工程を明かし、話し合っていました。
そこには、とても新鮮に見えるものがありました。そして、僕は、ほかの映画作家とそういうことをしたことが一度もなかったということに気づきました。アイデアがどんなところから来るのか、ほかの映画作家と話したことがない。映画づくりのメソッドについても話したことがない。映画作家はお互いの秘密を話さない。とても仲がいい友達であっても、現場でどんな感じなのか全然知らないです。
柳井 知りたいと思いませんか。
ヴェンダース どうなんでしょう。話したことがないんですよね。でも、例えばあと2人の監督と一緒に座って、お互いどうやって作っているのか、やり方、メソッドをお互いに話し合えたら最高じゃないかとちょっと思いました。でも、そんな勇気のあるほかの監督を2人も見つけられるかどうか。
映画の炎を、役者や製作陣、観客へ渡す

柳井 映画はすごく大勢の人で作るものですけれども、監督が最後の決断をしたりする時はすごく孤独なような気がします。そういう孤独との向き合い方はあるのでしょうか。
ヴェンダース 確かに、孤独な状態になる時が、特に脚本を書いている時にあります。脚本を書くという作業はすごく孤独だし、怖いし、すごく深いところで自分のもろさをさらけ出すことでもあるので、僕は少なくとも誰かと共同で脚本を書きたいと以前から思っています。撮影の場合は、俳優と腕のいい監督助手は必須です。映画というのはろうそくのようなもので、火をつけたら、そのろうそくをほかの人に渡さなければいけないし、渡された人はその炎が消えないようにしなければいけない。役者やカメラマン、編集者、作曲家、プロデューサーもみな同様に。
柳井 ともしびのリレーですね。
ヴェンダース そうです。もし灯りが消えたら、映画は消失してしまう。監督の仕事というのは誇張されて、すごく大きなものに思われることもあるんですけれど、基本的には、映画の炎が生き続けるようにちゃんと見守るケアテイカーなんです。本当に大事なのは火が消えないようにすること。だから、すべての重荷を背負っているわけではないのです。
「PERFECT DAYS」では、その炎を、役所さんが守ってくれた。高崎さんが守ってくれた。柳井さんが守ってくれた。編集のトニー・フロシュハマーも守ってくれたし、カメラマンのフランツ・ラスティグも鍵となる守護者でした。今も炎が生き続けている。今、言えるのはここまで。そして、ここからは観客の皆さん、見ていただく人にかかっている。もし、ご覧になって、ちょっと生き方を変えようかな、と思ってくれたら、その人がこの炎を守ってくれたことになると思います。そうやって次に渡していけるというところが映画の好きなところなのです。
僕自身も映画を見た後、自分の中でこの映画は生き続けるんだと思えるような映画が大好きだし、世界の見方が変わったなと思わせてくれる体験が大好きです。そんなにたくさんは起きないけれども、間違いなくそういうことが映画を見て起きるし、それが映画の力だと思います。
柳井さんは、映画のプロデューサーとなられたわけですけれども、これからも炎を守っていっていただければ。
柳井 僕は映画のプロデューサーを目指していたわけではなく、今回はいろいろな偶然が重なった結果です。個人的には本業のユニクロの仕事に邁進する事が自分に課せられた使命だと感じています。ただトイレのプロジェクトにしても今回の映画にしても、すべて繋がっていると確信しています。ユニクロの仕事でも映画の仕事でも炎を守る行為は続けていきたいです。ちなみに映画の炎に関してはヴェンダース組専属でお願いしたいと思っています。
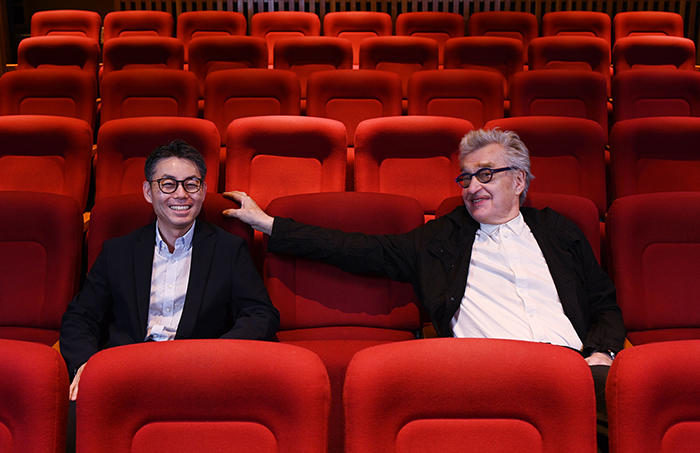
「東京画」ゆかりの鎌倉・川喜多映画記念館で
柳井さんとヴェンダースさんの対談は、鎌倉市川喜多映画記念館で行われた。戦前から映画を通じた国際交流で大きな足跡を残した川喜多長政・かしこ夫妻の旧宅跡に建つ施設だ。現在も残る旧川喜多別邸(旧和辻邸)は、ヴェンダース監督が小津安二郎監督にオマージュをささげたドキュメンタリー映画「東京画」(1985年)の中で、俳優・笠智衆にインタビューを行った場所でもある。
「東京画」は、小津、東京、そして映画をめぐる旅のエッセーのような味わいの映画だ。印象的な光景はいくつもあるが、夜を走る電車をとらえたシーンもその一つ。車窓にともる光の連なりが画面を横切っていくさまは、映画のフィルムそのものの流れを想起させながら強い印象を残す。それは、ヴェンダース監督自身にとっても「特別な瞬間」だったという。このシーンには、同作の撮影に同行し、サポートした川喜多和子さんの存在も大きくかかわっている。和子さんは、長政・かしこ夫妻の長女で、世界の優れた映画と映画作家の紹介に尽力した人だ。1993年、くも膜下出血を起こし53歳で急逝。今年が没後30年にあたる。
ヴェンダース 僕とカメラマンのエド・ラックマンは、(83年の東京で)「東京画」を2人で撮っていました。お金も、よりどころもないままの撮影で、僕は録音技師も兼ねていました。滞在していたホテルは本当に狭くて、ベッドの横にぎりぎり立てるくらいスペースがあるくらい。僕らは、そこにそれぞれ撮影・録音の機材を置いていました。当時は枝豆ばかり食べていましたが、それは安かったから。あとはホテルの自販機で売っているコカ・コーラと缶コーヒーばかり飲んでいました。
そんな中、ほかの作品の配給をしてくださっていた川喜多和子さんが、僕が困っているのに気づいて助けてくれた。映画に出てくださった笠智衆さんや小津組のカメラマンの厚田雄春さんと引き合わせてくれたのも、旧和辻邸での撮影を可能にしてくれたのも、彼女でした。
笠智衆さんの撮影の日のことです。撮影を終えた私とエド・ラックマン、そして川喜多和子さんは、3人で東京に戻りました。撮影したものに本当に私たちは満足していて、電車の中ではもうやることも特にありませんでした。和子さんは撮影機材のそばにいて、その姿が窓に反射していました。私はエドにこっそり、カメラを回すように言いました。和子さんは、僕たちが撮影していると知ったら、「絶対に出たくない」とおっしゃるような人だったのですが、僕は、「東京画」の守護天使である和子さんを、一瞬だけでも映画の中に登場させたかったのです。
それで、車窓に映る彼女を撮っていたら、信じられないことが起きました。左右から違う電車が次々と窓の向こうを移動していって、電車のダンスのような情景になったのです。それは、そんなふうに撮ろうとしても準備なんかできないぐらいのスペクタクルで、フィルムがなくなるまでカメラを回しました。和子さんがいて、そのシーンがさらに電車のダンスになっていった。フィルムメーカーであると、自分が値しないようなものが与えられることがある。そういうお話です。今日も彼女は、この記念館のどこかにいらっしゃったと思います。
取材・構成=読売新聞編集委員 恩田泰子
対談写真撮影=秋元和夫
映画「PERFECT DAYS」場面写真=©2023 MASTER MIND Ltd.
◇ PERFECT DAYS THE TOKYO TOILET(TTT)の一環として作られた映画。TTTを生んだ柳井康治さんが、クリエイティブディレクターの高崎卓馬さんと企画を始動させた。公共トイレを作ってみて、メンテナンスの重要性を知ったことが、企画のきっかけ。清掃する人への感謝をあらわすと同時に、使う人の意識をよき方向に変えたいとの思いもこめられている。脚本は、高崎さんとヴィム・ヴェンダース監督の共同。第76回カンヌ国際映画祭で世界初上映され、主演の役所広司さんが最優秀男優賞に輝いた。現在、世界87の国・地域での公開が決定。米アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表にも選ばれている。

◇ THE TOKYO TOILET(TTT)と映画「PERFECT DAYS」をめぐる柳井康治さんの対談シリーズ「きづきのきづき」は不定期で更新予定です。