広 告 企画・制作 読売新聞社広告局
Sponsored by 株式会社ツムラ
不調からがん医療まで活用進む
病院の検査では異常なしと言われたけれど、やっぱり体がつらい……。そんなとき、つらさを緩和する手立ての一つとして挙げられるのが「漢方」です。漢方とはどんな医学で、不調や病気に対してどんな力を発揮するのでしょうか。内科医で、日本東洋医学会会長である佐藤弘先生にお話をうかがいました。

日本東洋医学会会長、新潟医療福祉大学教授、東京女子医科大学名誉教授
佐藤 弘 先生
漢方はもともと中国で生まれ、2000年前にはすでに医学としてかなり体系化されていたと言われています。よく知られている「葛根湯(かっこんとう)」などは、この時期の医学書にも登場していました。この医学が日本に伝わったのは5~6世紀ごろで、その後日本の風土や日本人の体質などに合わせて独自に発展し、現在の「漢方医学」が出来上がりました。
漢方医学の主な特徴としては、まず自覚症状を重視することが挙げられます。西洋医学では検査結果の数値で診断・治療を行うことが多いのですが、漢方医学では患者さんの訴えを第一の判断材料とします。「検査では異常がないのに体がつらい」と訴える患者さんは少なくありません。病気ではないが健康でもない、西洋医学では診断名がつかないこうした状態は「未病(みびょう)」と呼ばれ、漢方の得意分野とされています。
また漢方医学は、心と体は一体で互いに影響し合うという「心身一如」の考え方に基づいています。体の不調を改善することで心の健康を目指す、あるいはその逆というように、心身全体のバランスを整えることを目的として治療を行うのです。その意味で、漢方はストレスによる慢性的な体調不良などにも向いた治療法と言えるでしょう。

漢方医学で使われる「漢方薬」は、天然の生薬を組み合わせて作られています。複数の成分が含まれる生薬を複数組み合わせるため、ほぼ単一成分でできている西洋薬に対して「多成分系」と呼ばれ、幅広い相乗作用を発揮することで知られています。そのため、検査で異常なしと言われる病気や不調をはじめ、原因不明の慢性病や体質が関係した病気に向いており、胃炎や下痢・便秘、月経痛や更年期障害、精神不安や不眠など幅広い症状の緩和に使われています。
さらに近年は、がん医療の現場でも漢方薬の活用が進んでいます。がん医療では、術後の体調不良や抗がん剤・放射線の副作用を和らげる「支持療法」や「緩和ケア」が重視されつつあり、厚生労働省の「がん対策加速化プラン」では漢方薬の活用もその一つとして位置づけられています。漢方薬だけでがんを抑制するということではなく、標準的な治療と一緒に用いることで、つらい症状の改善や気力・体力の回復、QOL(生活の質)の維持・向上などに役立てられています。
漢方のチカラは、老年医学の分野でも期待されています。西洋医学では、高齢者の身体機能や認知機能が低下した状態を「フレイル※」と言いますが、これを要介護状態ではなく健康に近い状態に導くために、漢方の考え方や漢方薬が有用なのではないかと考えられ始めているのです。西洋医学と漢方医学が連携して患者さんの健康に向き合う──。こうした機会は、今後ますます広がっていくことでしょう。
※加齢とともに、心身の活力(例えば筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態。
漢方医学には、国内だけでなく海外からも注目が集まっています。特に消化器の分野では、漢方薬の「大建中湯(だいけんちゅうとう)」や「六君子湯(りっくんしとう)」の有用性が注目されています。例えば大建中湯を使用することによって、早期回復や合併症の抑制に役立つとされ、長期入院や再手術を防ぐ、つまり医療コストの削減につながるという報告もあります。
医学の進歩とともに、漢方研究においても臨床データの蓄積や作用機序の解析がかなり進んできました。かつては非科学的な印象を持たれることもあった漢方ですが、現在では科学的な裏づけがあるものとして、医療現場で広く理解されつつあります。
検査では異常がないのに心や体がつらい、心身ともに健康な状態を目指したい。そんな方には、漢方という選択肢もあることをぜひ知っていただきたいと思います。「日本東洋医学会」のWebサイトでは、お近くの漢方専門医の検索もできますので、こうした医療機関へ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
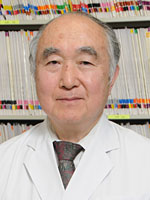
佐藤 弘 先生
日本東洋医学会会長、新潟医療福祉大学教授、東京女子医科大学名誉教授
1974年、東京大学医学部医学科卒業。同大第三内科に入局し肝臓病学を専攻。その後、東京女子医科大学附属東洋医学研究所教授・所長を経て現職。専門分野は漢方医学、内科学、肝臓病学。各種疾患の漢方治療、特に消化器領域の研究に取り組んでいる。日本東洋医学会認定専門医・指導医ほか。







